幸せと友達には、どんな関係があるのでしょうか。
「友達が多いと楽しい」「仲がいいと安心できる」そんな感覚は、誰もが日常で感じていることだと思います。
でも、その気持ちが本当に「幸せ」に関係しているのか、気になったことはありませんか?
今回紹介するのは、『How Friendship Network Characteristics Influence Subjective Well-Being』という研究です。
この研究では、友達の「数」や「会う頻度」、「タイプの違い」がどのように人の幸福に影響するのかを調べています。
あなたの友達関係が、どんなふうにあなたの気分や毎日に影響しているのかを、一緒に考えてみましょう。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
幸せと友達の深いつながりとは?
友達の多さが幸せにどう関係するのか
友達が多い人ほど幸せを感じやすいです。
なぜなら、友達の存在は心の支えになるからです。
この研究では、親しい友達が多い人ほど社会的信頼が高いと分かりました。
社会的信頼とは、「人は信じられる」という気持ちのことです。
信頼できると感じると、不安が少なくなります。
また、友達が多い人はストレスも少なくなる傾向があります。
ただし、友達が多くても性格が合わないと逆効果になることもあります。
特に異なる考え方をもつ友達が多すぎると、信頼感が下がることもあります。
数だけでなく関係の質も大切です。
- 親しい友達の数が多いと幸福感が上がる
- 信頼があると心が安定しやすい
- 数だけでなく、関係の心地よさも重要
つまり友達の多さは幸せに影響しますが、ただの数ではなく、どんな人とかかわるかが大事です。
友達と会う頻度が気分に与える影響
友達とよく会う人は気分が良くなります。
この研究では、顔を合わせて話すことが特に効果的だと示されました。
たとえば、週に何回も会っている人は、幸福度が高いです。
一方で、電話やネットでのやりとりだけでは効果が弱いです。
会って話すと安心感やつながりを感じられます。
また、ストレスが減り、健康にも良い影響があります。
よく会う人は、困ったときにも助けてもらいやすいです。
つまり、交流の「回数」と「顔を合わせること」がカギです。
- 会う回数が多いと幸福感が高まる
- 対面での会話が安心感につながる
- 電話やネットよりも直接のやりとりが効果的
気分を良くするには、定期的に友達と顔を合わせることが大切です。
いろんなタイプの友達がいるとどうなる?
友達が多様だと良い面と悪い面があります。
この研究では、友達が自分と違うほどストレスが増えることが分かりました。
たとえば、年齢や性別、収入や言葉が異なる友達が多いと、気疲れすることがあります。
しかし、ネットワークが多様だと、いろいろな情報や助けをもらえるという利点もあります。
とくに実際の支援を受ける機会は増えます。
ただし、多様性が高いと社会的信頼は下がる傾向にあります。
信頼が薄れると、心の安定に影響します。
- 多様な友達は助けをもらいやすい
- でもストレスや信頼の低下につながることも
- 同じ価値観を持つ友達も大事にしよう
友達がさまざまなのはよいことですが、自分に合う人とのバランスが重要です。
幸せの正体とは?感情と満足感の2つの側面
幸せには2つの面があります。
この研究では「感情」と「満足感」に分けて分析しています。
感情とは、日々の気分や喜び、楽しさのことです。
一方、満足感は、人生全体や仕事、お金、健康への評価です。
どちらも大切で、どちらかだけでは本当の幸せとは言えません。
友達との関係は、この2つの面の両方に影響します。
たとえば、対面で会うことで感情が良くなり、健康満足度も上がります。
つまり、友達とのつながりは広い意味での幸せを作っています。
- 感情=その日の気分や感覚
- 満足感=人生のいろいろな分野の評価
- 友達はどちらにも強く関係している
幸せには気分だけでなく、自分の生活への納得も含まれるのです。
幸せを左右するのは性格より友達?
性格よりも友達との関係の方が幸せに影響します。
多くの人は、「性格で幸せが決まる」と思いがちです。
しかしこの研究では、性格より友人関係のほうが重要な要素とされています。
たとえば、もともと性格が明るくなくても、頻繁に友達と会えば幸せを感じやすくなります。
また、信頼できる人がそばにいると、不安が減ります。
性格は変えにくいですが、友達との関係は自分の行動で変えられます。
ですから、自分に合う関係づくりがより大切なのです。
- 性格よりも友達の影響が大きい
- 自分から関係を作れるのがポイント
- 誰でも幸せになれるチャンスがある
幸せになるには、性格にこだわらず、友達とのつながりを大切にしましょう。
幸せと友達の間にある4つの「秘密の橋」
社会的信頼が心の安定を作る
人を信じられる気持ちは幸せと関係があります。
この研究では、友達が多い人やよく会う人は社会的信頼が高いと分かりました。
社会的信頼とは、「人は信用できる」と感じる心のことです。
この信頼が高いと、安心して他人とかかわれるようになります。
また、信頼があると不安や疑いが少なくなり、心が安定します。
とくに、対面でのやりとりやインターネットでの交流が信頼を高める要因でした。
親しい友達の数が多いことも、信頼感の向上に関係しています。
- 顔を合わせることで信頼が育つ
- 信頼があると心にゆとりができる
- 信じる気持ちは人との絆を強くする
人を信じられることは、友達とのつながりによって育ち、幸福感を高めてくれます。
ストレスの少なさが毎日を明るくする
ストレスが少ないと、日々がもっと楽しくなります。
この研究では、友達とよく会う人ほどストレスが少ないと分かりました。
特に、直接会って話すことが大切でした。
電話やネットでのやりとりには、あまり影響がありませんでした。
また、親しい友達が多い人は、心の負担も少ないようです。
反対に、異なるタイプの友達が多すぎると、ストレスが増える可能性があります。
関係の安心感が、心の安定を支えています。
- 会う頻度がストレスの軽減に役立つ
- 同じような価値観の友達が安心感をくれる
- 異なる友達が多いと疲れることもある
日々を明るく過ごすには、ストレスの少ない友人関係がとても重要です。
健康でいることが幸福感を高める
体が元気だと、心も前向きになります。
この研究では、友達とのつながりが健康にも影響すると分かりました。
友達が多い人やよく会う人は、健康状態も良い傾向がありました。
とくに、対面で会うことで健康意識が高まりやすいです。
さらに、親しい友達が多いと、生活習慣も整いやすくなります。
ただし、友達が多くても、異質な人ばかりだと健康への効果が下がる場合もあります。
- 友達の存在が健康を保つ力になる
- 会話や行動が生活のリズムを整える
- 心と体の健康はつながっている
元気でいるためには、信頼できる友達との交流が欠かせません。
支えてくれる友達のありがたさ
友達からの助けは心の支えになります。
この研究では、友達から助けを受ける人ほど支援の機会が多いと分かりました。
異なる背景をもつ友達が多い人は、さまざまな形での支援を受けやすいです。
また、頻繁に会う人ほど、助けてもらえることが多くなります。
親しい友達がいることで、困ったときも安心できます。
しかし、支援を受ける側の気持ちには注意が必要です。
もしかすると、「助けが必要な状態」は、心がつらい時期でもあるのです。
- よく会う友達ほど支援してくれる
- 異なるタイプの友達は多様な助けをくれる
- 助けてもらうこと自体がありがたい存在証明
支えてくれる友達は、日常を乗り越えるための大切な味方です。
幸せのカギは友達からの“間接的な影響”
友達の影響は、目に見えない形でもあらわれます。
この研究では、友達がいることで、信頼や健康、ストレス軽減などの「間接的な効果」があると分かりました。
これらが積み重なることで、最終的に幸せにつながるのです。
とくに、対面で会うことが直接的にも間接的にも大きな役割を果たしていました。
一方で、友達の数や多様性は、直接の影響よりも「信頼」や「健康」を通じて間接的に働きます。
- 間接的な効果が幸せに大きく影響
- 信頼や健康が友達からもたらされる
- 一緒に過ごす時間が心の力になる
友達はただそばにいるだけでなく、さまざまな方法で私たちの幸せを支えてくれています。
幸せと友達のつながりを深掘りしよう
対面での交流が一番のポイント
友達と直接会うことが幸せに直結します。
この研究では、対面での交流が最も強く幸福感に影響すると示されています。
会って話すことで安心感や信頼が生まれます。
また、顔を見て話すことで、気持ちが伝わりやすくなります。
それにより、ストレスが減り、心の状態が安定します。
さらに、健康への良い影響もありました。
たとえば、週に数回会っている人は、人生の満足度も高い傾向にあります。
- 顔を合わせることで感情が豊かになる
- 健康や信頼感にも効果がある
- 会う回数が多いほどポジティブな影響
友達と直接会って話す時間は、幸せのために欠かせない要素です。
電話よりも顔を合わせることが大切
電話よりも、会って話すほうが効果的です。
研究によると、電話だけのやりとりでは幸福感はあまり変わりませんでした。
声だけの会話では、表情や雰囲気が伝わりにくいためです。
一方、顔を合わせると、安心感や親しみが生まれます。
また、ストレスも軽くなりやすいです。
友達との絆を深めるには、直接会うことがいちばん効果があります。
- 電話は便利でも、心のつながりには限界あり
- 表情やしぐさが伝わることが大事
- 話す内容より「会うこと」自体が効果的
電話よりも直接会うことで、より強い幸せを感じることができます。
SNSやネットでのやりとりは逆効果?
ネットでの交流は、ストレスを増やすことがあります。
この研究では、インターネットでのやりとりが社会的信頼を高める一方で、ストレスとも関係していると示されています。
たとえば、SNSでのやりとりが多い人は、逆に疲れや不安を感じやすいこともあります。
画面越しでは、本音が伝わりにくいことが理由です。
さらに、比較や気配りに疲れることもあるでしょう。
- ネットでは気軽に話せるが、心の距離が残る
- 信頼は生まれても、安心感は弱いこともある
- 長時間のネット交流はストレスになる可能性あり
ネットのやりとりは便利ですが、使い方に気をつけないと逆効果になることもあります。
異なるタイプの友達が多いと疲れることも
多様な友達関係は負担になることもあります。
研究では、年齢や性別、言葉や収入が異なる友達が多いと、ストレスが増えることがわかっています。
たとえば、考え方の違いに気をつかったり、無理に合わせようとすることが原因です。
また、多様な友達は社会的信頼を下げる傾向もありました。
一方で、支援を得やすくなるという良い面もあります。
- 違いが多いと気を使いすぎてしまう
- 信頼感や安心感が持ちにくくなる場合もある
- 助けが必要なときには役立つこともある
異なる友達が多すぎると、楽しい一方で疲れてしまうこともあるので注意が必要です。
親しい友達の存在が信頼を生む
親しい友達が多いと、人を信じやすくなります。
この研究では、親しい友達の数が多い人は、社会的信頼が高いとわかりました。
安心して話せる相手がいると、自分以外の人にも心を開きやすくなります。
また、信頼できる関係があると、ストレスも軽減されます。
さらに、困ったときに助けを求めるハードルも下がります。
- 親しい友達の数は信頼感に影響
- 安心できる相手がいると、他人にも優しくなれる
- 信頼があると毎日の気分が安定する
信頼の土台となるのは、やはりそばにいてくれる親しい友達の存在です。
幸せと友達の「支え合い」がもたらすもの
困ったときの助けが必ずしも幸福に直結しない理由
友達から助けを受けることが、必ずしも幸せとは限りません。
この研究では、支援を受けた人のほうが主観的な幸福度が低いという結果が出ました。
なぜなら、支援を受けるということは、つらい状況にある可能性が高いからです。
たとえば、病気や仕事の悩みなど、助けが必要なときは心も不安定になりがちです。
そのため、助けてもらったとしても、それがそのまま幸せに結びつくわけではありません。
- 助けられる=大変な時期であることが多い
- 心が弱っているときは、支援があっても不安が残る
- 助けが必要な状態自体が、幸福感を下げてしまう
友達からの支援はありがたいものですが、それを受けている状況がつらければ、幸福にはつながりにくいのです。
助けを受ける=つらい状態であることも
支援を受けている人は、同時に困っている人でもあります。
研究では、友人から支援を受けた人の満足度や気分が低い傾向にありました。
つまり、助けをもらうこと自体が「苦しい状態」のあらわれかもしれません。
たとえば、病気で寝込んでいるときやお金に困っているときなどです。
このようなときに支援は必要ですが、その人自身の幸福感は下がっているのです。
- 支援は必要でも、気持ちは前向きになれないこともある
- 困っているからこそ、誰かに頼っている
- 助けてもらっても心のつらさは残る
助けを受けているという事実は、本人の苦しさを映し出している場合があります。
支援されることが自信を下げることもある
人に頼ることが、自信を失わせることもあります。
この研究では、支援を受けた人ほど主観的な幸福度が低い傾向がありました。
なぜなら、「自分でできない」と感じることが、無力感につながるからです。
もちろん支援は大切ですが、常に助けてもらってばかりでは自信を持ちにくくなります。
人は「自分でできた」と思えたときに、達成感や満足感を得やすくなります。
- 頼られる側と比べて、頼る側は気を使う
- 助けられることで「迷惑をかけた」と感じることもある
- 自分の力で解決できない状況が苦しさを生む
助けをもらうことは悪くありませんが、それが続くと心に負担を感じる人もいます。
支援よりも一緒に笑える関係が大切
助けてもらうより、楽しい時間を共有する方が幸せです。
研究では、支援を受けた経験は必ずしも幸福につながらないことがわかりました。
一方で、よく会う友達がいる人は、感情も前向きになりやすいです。
笑ったり話したり、楽しい時間を過ごすことで気持ちが明るくなります。
困っているときに助けられるのも大切ですが、日常で一緒に過ごすことの方が幸せには効果的です。
- 楽しさの共有が心を軽くする
- 助け合いよりも日々のやりとりが重要
- 一緒に過ごすことが信頼関係を育てる
幸せを感じるのは、特別な支援よりも日常の笑顔の積み重ねなのです。
頼られるより、自然に関わり合える関係が心地いい
助けを求めるより、自然な関係が心を落ち着かせます。
この研究では、支援があったかどうかより、どれだけ頻繁に会っているかが重要だと分かりました。
「困ったときだけ会う」のではなく、普段から関わりがある友達の方が、心の安定につながります。
自然に会ったり話したりできる関係は、気を使わず安心できます。
そうした関係があると、困ったときにも無理なく助けを求めやすくなります。
- 普段からの関係があると、気持ちが安定
- 形式ばらないつながりが心を楽にする
- 無理のない関係が信頼と安心感を育てる
支援よりも、自然に関わりあえる関係こそが、心の豊かさを支えてくれます。
幸せと友達の関係をどう育てるか
数よりも「会う頻度」が大事なワケ
友達の人数よりも、どれだけ会っているかが重要です。
この研究では、友達の数そのものよりも、会う頻度のほうが幸福度に強く関係していました。
たとえば、たくさん友達がいても、あまり会わなければ心の支えにはなりません。
逆に、少数でもよく会う友達がいれば、安心感が得られやすいです。
特に、顔を合わせることが大きな意味を持ちます。
実際、対面で会う頻度が高い人は、感情や満足度のスコアが高くなっていました。
- 会う回数が多いと気分が明るくなる
- 顔を合わせることで心がつながる
- 人数よりも「会っているか」が大事
幸せを育てるには、友達の多さよりも、どれだけその人と関わっているかがカギになります。
同じ価値観の友達とのつながりが安心感をくれる
自分と似た考えの友達がいると、心が落ち着きます。
研究では、異なる背景の友達が多いと、信頼が下がる傾向があるとわかりました。
似たような価値観や生活環境の友達が多い人の方が、ストレスが少ないという結果もあります。
たとえば、同じ年代や収入レベル、言葉が通じる友達とは、会話がスムーズです。
気を使いすぎずに話せる関係は、安心感を生みます。
- 同じ立場の友達とは、心が通いやすい
- 違いが少ないと、無理せず話せる
- 似た者同士のつながりは心を休めてくれる
安心できる関係は、共通点のある友達との自然なつながりから生まれます。
自分に合った交友関係が幸せを引き寄せる
自分の性格や生活に合った友達が、幸せを運びます。
この研究では、友情の形がひとつではないことが示されています。
友達が多い人、よく会う人、異なるタイプの友達がいる人など、いろいろなパターンがありました。
大切なのは「自分にとって心地よい関係かどうか」です。
たとえば、にぎやかな集まりが好きな人と、少人数の深いつながりが好きな人では、合う関係が違います。
自分に合った交友の形が、無理のない幸せを作ります。
- 交流のスタイルは人それぞれ
- 無理に広げるより、自分らしい関係を大切に
- 心が落ち着くつながりが幸福につながる
幸せを感じるためには、自分に合った交友の形を見つけることが何より大切です。
ネット上のやりとりはストレスを増やすこともある
インターネットでのやりとりは、注意が必要です。
研究によると、ネットを通じた交流は社会的信頼を高める効果もあります。
しかしその一方で、ストレスの増加とも関係していることが明らかになりました。
たとえば、メッセージのやり取りが続くと、気疲れや比較による不安が生まれることがあります。
また、相手の表情や気持ちが見えにくいため、誤解やすれ違いも起きやすくなります。
- ネット交流は便利でも、心に負担がかかることも
- 感情のすれ違いがストレスにつながる
- 実際に会うほうが安心できる
ネット上での交流は使い方によって良くも悪くもなります。バランスを意識することが大切です。
たくさん友達がいても異質だと信頼は下がる
友達が多くても、タイプが違いすぎると信頼しにくくなります。
この研究では、異質な友達が多い場合、社会的信頼が低くなることが示されています。
たとえば、文化や価値観が大きく異なると、心の距離を感じやすくなります。
人数が多くても、共通点が少ないと不安や緊張が増すことがあります。
その結果、人とのつながりに対して疑いを持ちやすくなるのです。
- 異なる価値観は理解し合うまでに時間がかかる
- 信頼関係を築くには、安心できる土台が必要
- 多様性があるときは丁寧な関わりが求められる
友達の数だけでなく、「どんな人とかかわっているか」が信頼と幸せを左右するのです。
最後に
この記事では、「幸せと友達」の関係について、研究にもとづいて紹介してきました。
大切なのは、友達の「多さ」よりも、「どう関わっているか」です。
とくに、直接会って話す時間があることは、信頼や安心感、健康やストレスの面で大きな効果があります。
また、似た価値観や考えを持つ友達がいると、気持ちが落ち着きやすく、毎日を前向きに過ごせるようになります。
一方で、タイプの違う友達が多すぎたり、ネットだけのやりとりが続いたりすると、逆に疲れやすくなることもあります。
つまり、自分に合った関係を大切にすることが、幸せにつながるカギなのです。
あなたのまわりにいる友達との関係を、あらためて見つめなおしてみませんか?
ちょっとした会話や一緒に過ごす時間が、あなたの心をもっとあたたかくしてくれるかもしれません。
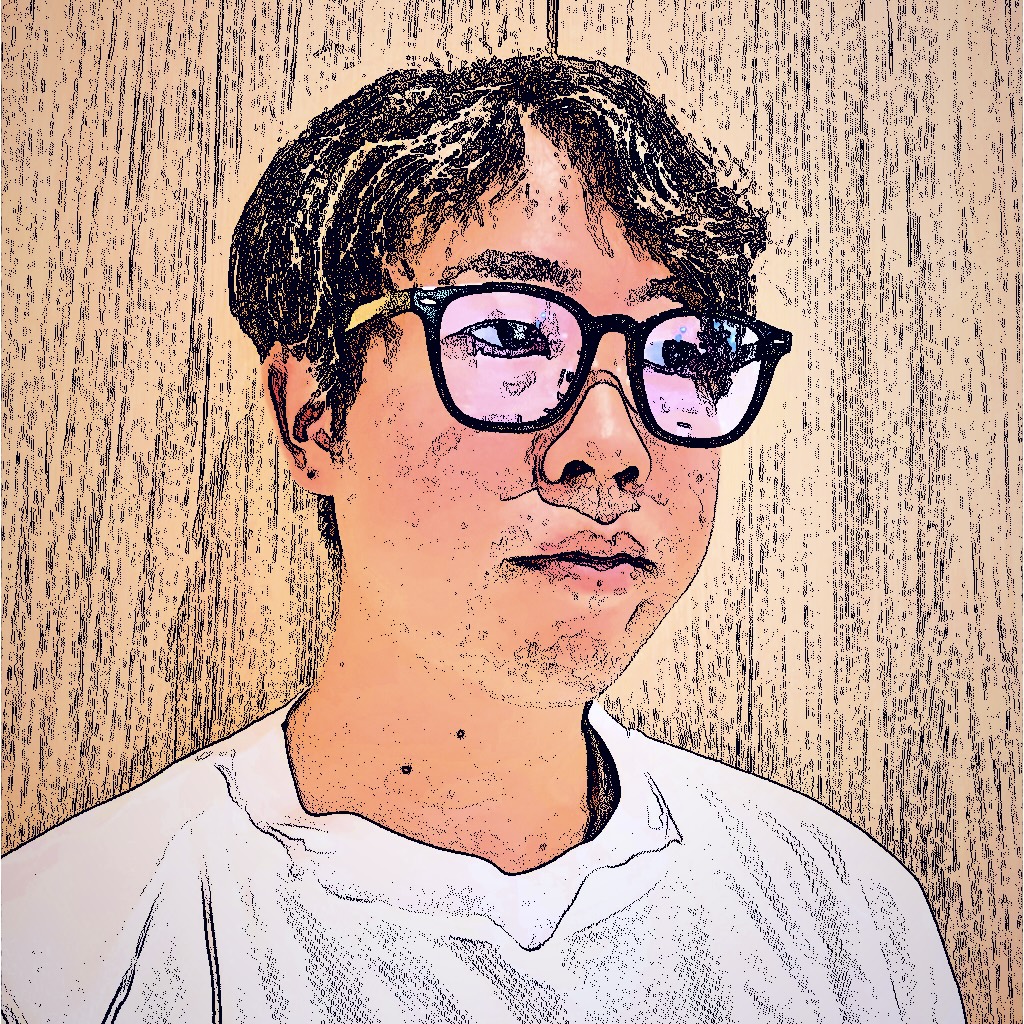
ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。








