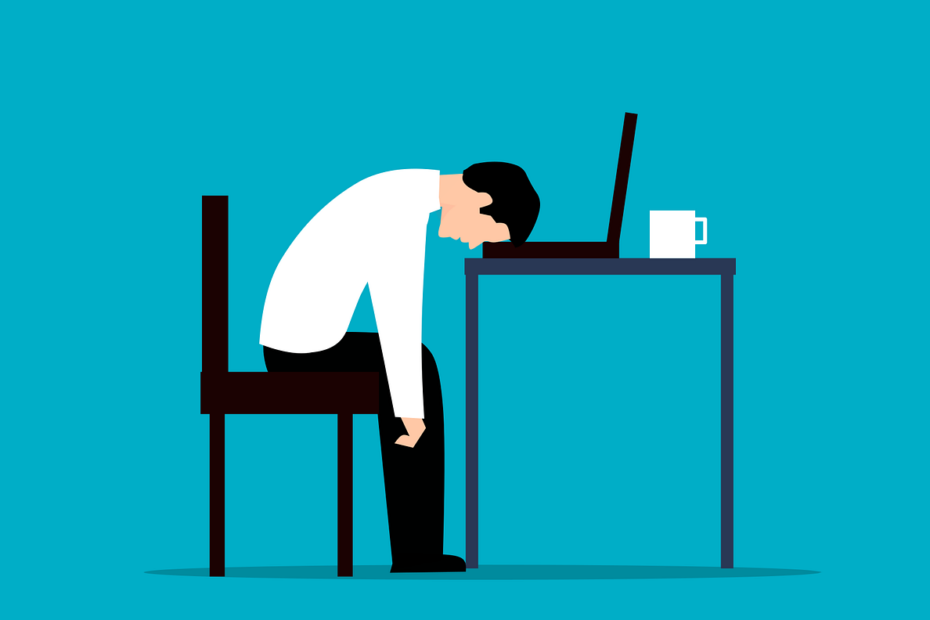バーンアウトという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
最近、学校や職場で、バーンアウトになる人が増えていると言われています。
バーンアウトとは、長期的なストレスによって心身が疲れ果てた状態のことです。
部活動や勉強、アルバイトなど、頑張りすぎて燃え尽きてしまう、そんな経験をしたことはないでしょうか。
実は、アメリカの研究者が、性格とバーンアウトの関係について大規模な調査を行っていました。
その論文のタイトルは、「Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes」です。
この論文をもとに、性格とバーンアウトの関係について、詳しく見ていきたいと思います。
バーンアウトは、私たち一人一人に関わる身近な問題です。
自分の性格を知ることで、バーンアウトを予防することができるかもしれません。
一緒に、バーンアウトについて学んでいきましょう。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
バーンアウトとは?3つの症状と現代社会での広がり
バーンアウトの3つの症状: 情動的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下
バーンアウトは、長期的なストレスによって心身が疲れ果てた状態を指します。
以下の3つの症状が特徴的です。
- 情動的消耗感: 感情的に枯渇し、疲れ切ってしまう状態
- 脱人格化: 仕事や他人に対して無関心になり、シニカルな態度をとること
- 個人的達成感の低下: 自分の仕事ぶりに満足できなくなること
これらの症状が長期間続くと、心身の健康を大きく損なうことになります。
バーンアウトは単なる疲労とは異なり、回復に時間がかかる深刻な状態と言えるでしょう。
現代社会の職場でなぜバーンアウトが広がっているのか
現代社会では、多くの人がバーンアウトの危険にさらされています。
その理由として、以下のような点が挙げられます。
- 長時間労働や過重労働が常態化している
- 人間関係の希薄化により、職場でのサポートが得にくい
- テクノロジーの発達で仕事とプライベートの境界が曖昧になった
- 成果主義の浸透により、常に高いパフォーマンスを求められる
このような職場環境の変化により、多くの人がストレスを抱えています。
そして、そのストレスが長期化することでバーンアウトを引き起こすのです。
バーンアウトは個人の問題というだけでなく、現代社会の構造的な課題と言えるでしょう。
性格特性がバーンアウトに与える影響
神経症傾向が高いとバーンアウトになりやすい
神経症傾向が高い人は、バーンアウトに陥るリスクが高いことが明らかになっています。
これは、ストレスに脆弱で、不安や抑うつを感じやすい性格特性のことです。
このような性格の人は、以下のような理由からバーンアウトになりやすいと考えられます。
- ストレスをコントロールすることが苦手
- 物事を悲観的に捉えがち
- 自分の感情をうまく処理できない
神経症傾向が高い人は、ストレスをため込みやすく、それが蓄積することでバーンアウトを引き起こしてしまうのです。
ストレスへの脆弱性が、バーンアウトの大きなリスク要因だと言えます。
外向的な人はバーンアウトになりにくい
一方、外向的な性格の人は、バーンアウトのリスクが低いことが分かっています。
外向的な人は、以下のような特徴を持っています。
- 人と交流することが好き
- ポジティブな感情を感じやすい
- ストレス解消法を持っている
外向的な人は、人とのつながりを通じてストレスを発散することができます。
また、物事を前向きに捉える傾向があるため、ストレスをため込みにくいのです。
外向性は、バーンアウトに対する防御要因の1つだと考えられます。
協調性の高さはバーンアウトを防ぐ
協調性の高い人も、バーンアウトになりにくい傾向があります。
これは、他者に対して親切で思いやりがあり、協力的な性格特性のことです。
このような性格の人は、以下のような点でバーンアウトを防ぐことができます。
- 良好な人間関係を築くことができる
- 他者からのサポートを得やすい
- ストレスを感じにくい
協調性の高さは、職場での人間関係を円滑にし、ストレスを軽減する効果があります。
また、困ったときに周囲の助けを借りやすいのも、バーンアウトの予防につながります。
協調性は、バーンアウトを防ぐ重要な性格特性の1つと言えるでしょう。
誠実な人もバーンアウトのリスクが低い
誠実性の高い人も、バーンアウトを起こしにくいことが明らかになっています。
誠実な人は、以下のような特徴を持っています。
- 責任感が強く、粘り強い
- 計画的に物事を進める
- 自己管理能力が高い
誠実な人は、仕事に真面目に取り組み、着実に成果を出していくことができます。
また、自分の仕事をコントロールする能力が高いため、ストレスをため込みにくいのです。
誠実性は、バーンアウトを防ぐ重要な性格特性だと考えられます。
開放性はバーンアウトとあまり関係がない
開放性は、バーンアウトとの関連があまり見られない性格特性です。
これは、新しいアイデアや経験に対して開かれている性格特性のことを指します。
これまでの研究では、開放性とバーンアウトの間に明確な関係性は見出されていません。
開放的な人がバーンアウトしやすいわけでも、しにくいわけでもないようです。
ただし、開放性はストレス対処能力と関連している可能性があり、更なる研究が必要とされています。
バーンアウトが仕事や生活に与える深刻な影響
欠勤が増える
バーンアウトは、欠勤の増加につながることが明らかになっています。
バーンアウトによって心身の健康が損なわれると、以下のような理由から欠勤が増えてしまいます。
- 心身の不調により出勤できない
- モチベーションが低下し、仕事を休みがちになる
- ストレスから逃れるために欠勤する
欠勤が増えることで、仕事の進捗に支障をきたすだけでなく、収入の減少にもつながります。
また、周囲の同僚にも負担がかかり、職場全体の士気を下げることにもなりかねません。
バーンアウトによる欠勤の増加は、本人だけでなく職場にも大きな影響を与えるのです。
離職につながる
バーンアウトは、離職のリスクを高めることが分かっています。
バーンアウトが深刻化すると、以下のような理由から離職を考えるようになります。
- 仕事に対するやりがいを感じられなくなる
- ストレスから逃れるために職場を去ろうとする
- 心身の健康を守るために離職を選ぶ
離職は、本人の経済的基盤を揺るがすだけでなく、企業にとっても大きな損失となります。
優秀な人材を失うことで、生産性の低下や業務の停滞を招くことにもなりかねません。
バーンアウトによる離職は、個人と組織の両方に深刻な影響を与えると言えるでしょう。
仕事の成果が下がる
バーンアウトは、仕事のパフォーマンスを大きく下げることが明らかになっています。
バーンアウトに陥ると、以下のような理由から仕事の成果が低下してしまいます。
- 集中力が低下し、ミスが増える
- 創造性やアイデアが枯渇する
- 仕事に対するモチベーションが下がる
パフォーマンスの低下は、本人の評価や処遇に影響を与えるだけでなく、企業の業績にも直結します。
また、顧客対応の質の低下は、企業イメージの悪化につながることもあります。
バーンアウトによるパフォーマンスの低下は、個人のキャリアだけでなく企業の存続をも脅かしかねません。
心身の健康を損なう
バーンアウトは、心身の健康に深刻な影響を与えることが分かっています。
バーンアウトが長期化すると、以下のような健康問題を引き起こします。
- うつ病などのメンタルヘルス不調
- 心臓病などの身体疾患
- アルコールや薬物への依存
これらの健康問題は、仕事のパフォーマンスの低下だけでなく、生活の質の低下につながります。
また、治療には時間とコストがかかるため、経済的な負担も大きくなります。
バーンアウトは、個人の人生に長期的な影響を及ぼす深刻な問題だと言えるでしょう。
バーンアウトの進行プロセスを理解しよう
欠勤につながるバーンアウトの進行パターン
バーンアウトが欠勤につながるプロセスには、以下のような段階があることが明らかになっています。
- 個人的達成感の低下
- 脱人格化
- 情動的消耗感
まず、自分の仕事ぶりに満足できなくなることで個人的達成感が低下します。
次に、仕事や他人に無関心になる脱人格化が起こります。
そして最後に、感情的に枯渇し、疲れ切ってしまう情動的消耗感に至るのです。
このプロセスを理解することで、バーンアウトの兆候を早期に発見し、欠勤を未然に防ぐことができるでしょう。
離職を招くバーンアウトのプロセス
バーンアウトが離職を招くプロセスは、以下のような段階を経ることが分かっています。
- 情動的消耗感
- 個人的達成感の低下
- 脱人格化
まず、感情的に疲れ果ててしまう情動的消耗感が起こります。
次に、自分の仕事に満足できなくなる個人的達成感の低下が生じます。
そして最後に、仕事や他人に無関心になる脱人格化に至るのです。
このプロセスを知ることで、バーンアウトの進行を食い止め、離職を防ぐための対策を講じることができるでしょう。
成果低下をもたらすバーンアウトの段階
バーンアウトが成果低下をもたらすプロセスには、以下のような段階があることが明らかになっています。
- 情動的消耗感
- 脱人格化
- 個人的達成感の低下
まず、感情的に疲れ切ってしまう情動的消耗感が起こります。
次に、仕事や他人に無関心になる脱人格化が生じます。
そして最後に、自分の仕事ぶりに満足できなくなる個人的達成感の低下に至るのです。
このプロセスを理解することで、バーンアウトによる成果低下を防ぐための対策を立てることができるでしょう。
性格特性からバーンアウトを予測できる
性格によってなりやすさが違う
バーンアウトのリスクは、性格特性によって大きく異なることが明らかになっています。
神経症傾向が高い人は、バーンアウトになりやすい傾向があります。
一方、外向的で協調性が高く、誠実な人は、バーンアウトのリスクが低いと考えられています。
このように、性格特性を知ることで、バーンアウトの危険度をある程度予測することができるのです。
性格から予防策を考える
性格特性を踏まえることで、より効果的なバーンアウト予防策を考えることができます。
例えば、神経症傾向が高い人には、ストレスマネジメントの方法を身につけてもらうことが重要です。
外向的な人には、人との交流の機会を積極的に設けることが有効でしょう。
協調性の高い人には、職場の人間関係を円滑にするためのコミュニケーション研修などが役立つかもしれません。
このように、性格に応じたアプローチを取ることで、バーンアウトを効果的に予防することができるのです。
バーンアウト対策で企業にできること
社員の性格特性を理解し予防する
社員の性格特性を把握することは、企業のバーンアウト対策の基盤となります。
人事評価や面談などを通じて、社員一人ひとりの性格を理解することが大切です。
その上で、性格に応じたサポートを提供することが求められます。
例えば、神経症傾向の高い社員には、ストレス対処法のトレーニングを提供したり、上司が定期的に声をかけたりすることが効果的でしょう。
このように、社員の性格特性を踏まえた予防策を講じることで、バーンアウトを未然に防ぐことができるのです。
バーンアウトの兆候を見逃さない
バーンアウトの兆候を早期に発見することは、深刻化を防ぐ上で非常に重要です。 管理職は、部下の様子に日頃から気を配り、以下のようなバーンアウトのサインを見逃さないようにしましょう。
- ミスが増えた
- 遅刻や欠勤が増えた
- 無口になった
- 身だしなみが乱れてきた
これらの兆候を発見したら、すぐに本人に声をかけ、状況を確認することが大切です。 早期の介入が、バーンアウトの深刻化を防ぐ鍵となります。
職場環境の改善でバーンアウトを防ぐ
職場環境を改善することは、バーンアウトの予防に欠かせません。
企業は、以下のような取り組みを通じて、社員がバーンアウトしにくい職場づくりを目指すべきです。
- 適正な業務量の管理
- 柔軟な働き方の導入
- コミュニケーションの活性化
- 上司のマネジメント能力の向上
このような職場環境の改善により、社員のストレスを軽減し、バーンアウトを防ぐことができるのです。
職場環境は、バーンアウト対策の重要な柱の1つだと言えるでしょう。
バーンアウトした社員のサポート体制を整える
万が一バーンアウトした社員が出た場合、適切なサポート体制を整えることが欠かせません。企業は、以下のような支援策を用意しておくことが求められます。
- 産業医や臨床心理士による相談窓口の設置
- 休職制度の整備
- 復職支援プログラムの導入
- 同僚や上司の理解と協力
バーンアウトした社員が安心して休養と治療に専念できる環境を整えることが大切です。
また、職場復帰をスムーズに進めるためのサポートも欠かせません。
バーンアウトした社員への手厚いサポートは、企業の重要な責務と言えるでしょう。
バーンアウト問題にどう向き合うべきか
性格を知ることが対策の第一歩
自分の性格特性を知ることは、バーンアウト対策の出発点となります。
自分がどのような性格であるのかを理解することで、バーンアウトのリスクを把握することができるからです。
神経症傾向が高いと分かれば、ストレスマネジメントに注力することができますし、外向的だと分かれば、人との交流を大切にすることができます。
性格を知ることで、自分に合ったバーンアウト予防策を見つけることができるのです。
バーンアウトを防ぐためには、まず自分の性格と向き合うことが大切だと言えるでしょう。
個人の問題ではなく組織の課題
バーンアウトは、個人の問題というよりも、組織全体の課題だと言えます。
なぜなら、バーンアウトを引き起こす要因の多くは、職場環境に関連しているからです。
長時間労働、過重な業務量、コミュニケーション不足、上司の管理能力の低さなど、職場の問題がバーンアウトを招いているのです。
したがって、バーンアウト対策は、個人の努力だけでなく、組織を挙げての取り組みが不可欠となります。
企業は、バーンアウトを予防し、社員の心身の健康を守るための施策を積極的に進めていく必要があるでしょう。
バーンアウト問題に真摯に向き合うことが、企業の持続的な発展につながるのです。
最後に
バーンアウトは、現代社会の大きな問題となっています。
学校や職場での長期的なストレスによって、心身の健康を損ない、欠勤や離職、成績の低下などにつながることがあります。
しかし、自分の性格を知ることで、バーンアウトのリスクを減らすことができるのです。
神経症傾向が高い人は、ストレスに弱いので注意が必要ですが、外向的で協調性が高く、誠実な人は、バーンアウトになりにくい傾向があります。
また、性格に合わせた対処法を身につけることで、より効果的にバーンアウトを予防できます。
ただし、バーンアウトは個人の問題だけではありません。
職場の環境改善や、バーンアウトした人へのサポート体制など、組織全体で取り組むことが大切です。
一人一人が自分の性格を理解し、周りの人にも理解を求めながら、バーンアウト問題に向き合っていくことが必要不可欠です。
※この記事は以下の本に掲載された論文を参考に執筆しています。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。