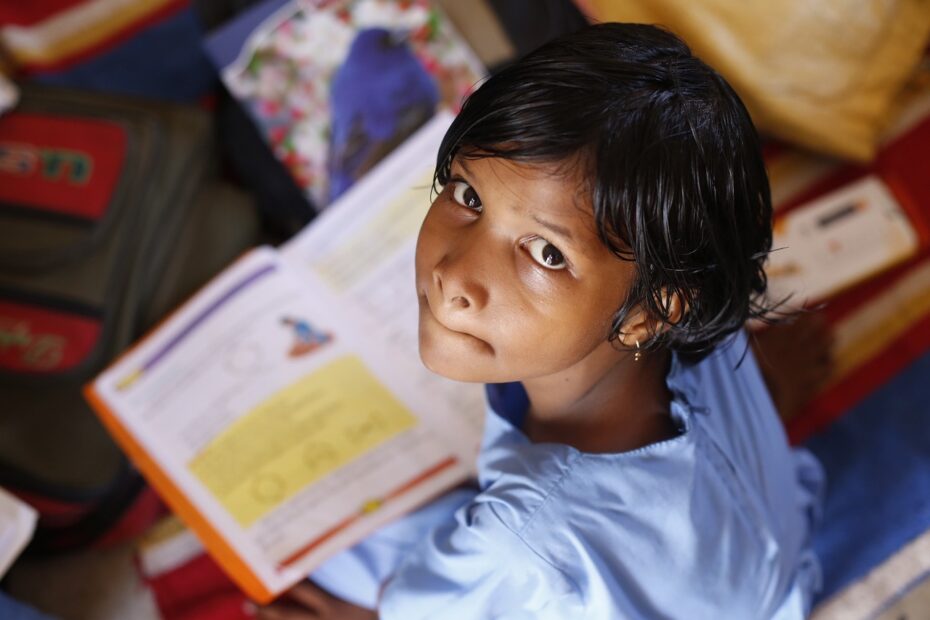学力の性差って本当にあるの?そう思ったことがある人は多いかもしれません。
たとえば「男子のほうが数学に強い」とか、そんな話を聞いたことがあるでしょう。
でも、それってただの思い込みかもしれません。実際のデータでは、どんなちがいがあるのでしょうか?
この記事では、世界中の研究データを集めて調べた論文「Gender Differences in Scholastic Achievement: A Meta-Analysis」にもとづいて、学力における男女のちがいをわかりやすくまとめて紹介します。
成績にちがいが出る教科や、その理由、時代による変化などをくわしく解説します。勉強に対する見方が変わるかもしれませんよ。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
学力の性差は本当にあるのか?
学力の性差が出るのはどの教科?
女子は多くの教科で男子より成績が高いです。
とくに言語科目でその差が目立ちます。
論文によれば、言語では女子が男子より平均0.374ポイント高いです。
これは小さな差に見えますが、広く見られる傾向です。
一方、数学では性差がとても小さくなっています。
女子と男子の成績差は0.069ポイントにとどまります。
このように教科によって差の大きさが変わります。
たとえば、
- 言語:女子が大きく上回る
- 社会:女子がやや上
- 理科:少し女子優位
- 数学:ほとんど差がない
この成績差は小学生から大学生まで一貫して見られました。
つまり、どの年代でも女子がやや上の傾向にあるといえます。
成績の性差は、教科ごとに違いがありますが、女子が全体的に有利であることが分かります。
女子が優位な教科、男子が得意な教科
女子は言語、男子は一部の数学にやや強い傾向があります。
しかし、その差はごくわずかです。
女子はとくに次の教科で成績が高いです。
- 国語や英語などの言語系
- 社会や倫理などの読み取り力が問われる教科
- 理科の一部
男子はごく一部の数学分野でわずかに上回ることがあります。
ただし、平均値では女子のほうが成績が高いです。
また、成績は学校の先生が出すため、努力や態度も影響します。
女子は授業中の姿勢や提出物で評価されやすい傾向があります。
このように見ると、教科によって違いがあるものの、女子が得意な教科が多いという傾向が読み取れます。
数学での性差はとても小さい
数学では男女の成績差はほとんど見られません。
効果量という数値で見ると0.069という非常に小さな差です。
つまり、女子と男子の数学の成績はほぼ同じといえます。
一部では男子が得意と思われがちですが、今は違います。
その理由として、
- 教育の平等化が進んでいる
- 女子も理系を選ぶ時代になった
- 学習意欲の差が縮まっている
などが考えられます。
また、数学は一発勝負のテストよりも、継続的な理解力が求められるようになってきています。
このように、昔の「男子=数学が得意」というイメージは現在ではあまり当てはまりません。
数学では男女の差はごくわずかで、ほぼ同じと言える結果が出ています。
理科や社会でも女子のほうが高得点
理科や社会でも女子が男子より成績が高い傾向があります。
この差は言語ほどではないものの、はっきり見られます。
たとえば、理科での効果量は約0.15程度でした。
これは小さい差ですが、統計的に意味のある差です。
社会ではさらに高く、約0.23程度の差がありました。
理由としては、
- 読解力の高さ
- 授業態度の真面目さ
- 宿題や提出物の正確さ
などが女子に多く見られるからだと考えられています。
また、理科の記述問題やレポート課題では、丁寧さや論理性も評価されます。
こうした面も女子の強みとなっています。
まとめると、理科や社会も女子のほうが一貫して高得点を取りやすい傾向にあるのが特徴です。
全体的に女子のほうが成績が高い傾向
総合的に見ると、女子の方が男子より成績が高いです。
この傾向は小学校から大学まで一貫しています。
全体の平均効果量は0.225と報告されています。
これは「小さいけれど確かな差」といえる数値です。
以下のような科目で女子が優位でした。
- 言語(0.374)
- 社会(約0.23)
- 理科(約0.15)
- 数学(0.069)
これらを総合すると、どの教科でも女子が男子よりわずかに高得点である傾向があります。
また、成績はテストだけでなく、日々の提出物や授業中の態度も含まれます。
女子はこのような評価基準に合いやすい面があると言われています。
つまり、学業成績全体で見ると、女子がやや上回っているというのが研究の結論です。
学力の性差が出る理由をさぐる
テストと通知表では評価の中身が違う
まずテストと通知表は評価する内容が違います。
テストは一回きりの実力をはかります。
通知表は毎日の努力や提出物もふくまれます。
つまり、テストでは男子がやや強い場面もありますが、
通知表の成績では女子が有利になる要素が多いです。
通知表には以下のような項目が入ります。
- 授業中の態度
- 提出物の有無
- ノートの書き方
- グループ活動への参加
女子はこうした点で高評価を得やすいです。
そのため、女子が全体として高い成績をとる理由になります。
成績とテストはちがう評価方法です。
通知表では女子のほうが有利な要素が多いといえます。
教室での態度や努力も成績に影響
学校の成績には教室での努力も大きく関係します。
これはテストの点数だけでは分からない部分です。
たとえば、
- 授業中にまじめに聞いているか
- 課題をきちんと出しているか
- 先生の話を理解しようとしているか
こうした日常の行動が通知表に反映されます。
研究によると、女子の方が努力を重ねる傾向があるといいます。
また、クラスでの協力姿勢や集中力にも差が見られます。
男子は集中を切らしやすく、活動が乱れることもあるようです。
これが評価にマイナスになることもあります。
このように、成績はテストだけでなく、ふだんの行動がしっかり見られているのです。
女子は長期的な努力が得意?
女子はこつこつと努力を重ねるのが得意です。
これは短期的な集中よりも、日々の積み重ねが大事な場面で強みになります。
学校の成績では、
- 宿題を毎回出す
- 授業ノートを丁寧にまとめる
- レポートを時間内に提出する
といった行動が高く評価されます。
女子はこうした点で安定した行動を取りやすいのです。
一方で、男子は短期間に集中する場面で力を発揮しやすいです。
しかし、学校成績は長期間の積み重ねが大事なので、女子の強みがよく出ます。
つまり、長期的に安定して取り組める女子が成績で有利になる理由の一つと言えるでしょう。
男子はテストの一発勝負に強い傾向
男子は短期間で実力を発揮するテストに強い傾向があります。
これは通知表の成績とは少しちがいます。
テストでは、
- 問題を速く解く
- 瞬時に判断する
- 状況に合わせて考える
などの力が必要です。
男子はこうした力で良い成績を出すことがあります。
ただし、テストは一回だけの評価です。
毎日の取り組みや努力を見ないため、長期的な習慣が反映されません。
学校成績は日々の行動や提出物など、積み上げた努力が評価されます。
そのため、男子のテストの強さが通知表の成績に直結しないことがあります。
テストで高得点でも、成績が伸びないことがあるのはそのためです。
学校という場が女子に合っている可能性
学校の仕組みは女子に合いやすい面があります。
これは男子と女子の違いによるものです。
学校では以下のような行動が求められます。
- 指示をよく聞く
- 集団で動く
- 時間を守る
- きちんと提出する
女子はこうした行動を自然にこなす傾向があります。
男子は自由な行動や、自分のペースを好むことがあります。
そのため、現在の学校制度では女子の特性が評価されやすくなります。
女子が持つ誠実性(まじめに取り組む力)も大きく影響します。
このように、学校という評価の仕組みそのものが、女子に向いているという可能性があります。
学力の性差を左右する要因とは?
教科の違いが性差の大きさに影響する
教科によって男女の成績差は変わります。
とくに言語では女子の方が大きく上回ります。
数学では差がとても小さいです。
成績の差は、教科の内容や求められる力に関係します。
たとえば、
- 言語:読み取り、表現、文法など
- 数学:論理、計算、空間の理解
- 理科:観察、分析、実験
- 社会:記憶、思考、因果関係の理解
女子は言語や社会のように文系的な要素が強い教科で高い成績をとりやすいです。
男子は一部の数学や理系科目で力を発揮することがありますが、差は小さいです。
つまり、教科ごとの特徴によって男女差が強く出る場合とそうでない場合があるのです。
年齢や学年によっても学力の性差は変わる
年齢によって男女の成績差が変わることがあります。
小学校では女子が強い傾向が目立ちます。
中学校や高校でも女子の優位は続きますが、大学ではやや差が小さくなります。
これは成績のつけ方や、科目選択の違いも関係します。
年齢が上がるにつれて、
- 自分の得意科目を選ぶようになる
- 自主性が求められる
- 専門性が高まる
こうした変化が性差に影響を与えます。
また、大学では一部で男子の方が上回る成績も見られました。
ただし全体としては、年齢が上がっても女子の優位はおおむね続くというのが研究の結果です。
成績のつけ方でも差が広がることがある
成績のつけ方によって男女差が大きくなることがあります。
たとえば、パーセント表示や5段階評価など、いろいろな方法があります。
先生がどう評価するかによって、
- 宿題の重視度
- 提出期限の厳しさ
- 行動や態度の影響
などの違いが出ます。
こうした評価の幅広さが、女子の良さを反映しやすくなることがあります。
一方、男子は努力よりもテスト重視の評価のほうが得意なことがあります。
評価方法によっては、女子の成績がさらに高く出る可能性があるのです。
つまり、どのように成績を出すかによって、性差の大きさも変わるということです。
公立か私立かで見える学力の性差
通っている学校の種類でも成績の差が出ます。
とくに公立と私立で傾向が異なることがあります。
研究では、私立学校では女子と男子の成績差が小さくなることがありました。
理由として、
- 学力が全体的に高い
- 成績の上限が近くなりやすい(天井効果)
- 評価基準が厳格
などが考えられます。
つまり、成績の上限に達する生徒が多くなり、男女差が目立ちにくくなるのです。
一方、公立校では学力や生活習慣に幅があり、成績の差が見えやすくなる場合があります。
このように、学校の種類によって、性差の出方にも違いが見られるのです。
生徒の人種や文化背景も学力の性差に関係する
人種や文化の違いも成績の性差に影響します。
とくにアメリカの研究では、明確な傾向がありました。
たとえば、
- 白人やアジア系の生徒は、女子が高成績になる傾向
- 黒人やヒスパニックの生徒では、成績差がさらに大きくなる場合がある
これは学力だけでなく、生活環境や教育支援の差が関係していると考えられます。
また、文化によって、
- 家庭での勉強時間
- 親の期待
- 学校とのかかわり方
が異なるため、性差の出方も変わってきます。
このように、性別だけでなく、人種や文化の背景も成績に大きく影響することが分かっています。
学力の性差は世界でも見られるのか?
アメリカとカナダでは女子優位が多い
アメリカとカナダでは、女子の方が成績が高い傾向です。
この地域は分析対象の約70%を占めています。
研究によると、
- 女子は小学校から大学まで安定して成績が良い
- とくに言語と社会で大きな差が見られる
- 数学では差は小さいが、女子がやや上
アメリカとカナダの教育では、
- 提出物や授業態度が重視される
- 成績がテストだけで決まらない
こうした仕組みが、女子に有利に働いていると考えられます。
また、多様な人種や文化が存在し、その中でも女子の優位が広く見られるのが特徴です。
このことから、北米では女子の学力の高さが一貫して確認されているといえます。
スカンジナビアでは学力の性差が小さい傾向
スウェーデンやノルウェーなどでは、成績の性差が小さいです。
スカンジナビア諸国では教育制度が特徴的です。
たとえば、
- 男女平等を重視する教育方針
- テストよりも過程を大切にする評価
- 子どもの主体性を育てる指導
このような環境では、男子と女子の差が目立ちにくくなります。
また、社会全体で平等意識が高く、性別による期待の差も少ないとされています。
そのため、成績における性差も自然と小さくなる傾向があるのです。
つまり、教育制度や文化の違いが、性差の出方に影響していると考えられます。
他の国では学力の性差の結果がバラバラ
アジアやヨーロッパなど、他の国では結果にばらつきがあります。
成績の差が大きい国もあれば、ほとんど見られない国もあります。
たとえば、
- トルコでは女子が大きく上回る傾向
- ドイツや台湾などでは小さな差しか見られない
- 一部では男子の方が成績が高い報告もある
これは教育方針や社会の価値観の違いが影響していると考えられます。
また、成績の出し方が統一されていないことも要因の一つです。
こうした背景から、国ごとの比較は慎重に行う必要があります。
世界全体で見ると性差の傾向は一定ではありませんが、女子優位がやや多い結果となっています。
教育制度が学力の性差に影響することも
教育制度の違いが、成績の性差に影響を与えます。
とくに評価の方法や学習の仕組みが関係しています。
たとえば、
- 提出物や授業中の態度を重視する国では女子が有利
- テスト中心の国では男子の差が縮まる場合もある
また、教育の自由度が高い国では、子ども自身の特性がより成績に反映されやすくなります。
これにより、女子の強みがより見えやすくなる可能性があります。
一方で、厳格な試験制度が中心の国では、男女差が小さくなる傾向も見られます。
このように、教育のあり方そのものが、性別による差を大きくしたり小さくしたりする要因になりうるのです。
世界的に見ても女子がやや優位
全体として見ると、世界中で女子がやや優位です。
これはさまざまな国のデータを集めた結果です。
平均して、女子は多くの国で男子より高い成績をおさめています。
特に小中学生の段階では、その傾向がはっきりしています。
また、言語や社会の科目での女子の優位はどの国でも見られやすいです。
ただし、差の大きさは国によって違いがあります。
制度や文化、学校の評価基準が関係しているためです。
結論としては、世界中で女子の学力は男子より少し上という傾向があるといえるでしょう。
学力の性差は時代で変わるのか?
昔から女子が成績上位だった
女子のほうが男子より成績が高い傾向は昔からありました。
この現象は新しいものではありません。
研究によると、1950年代からすでに女子の優位が確認されています。
たとえば、1954年の研究でも、女子のほうが通知表の成績が高かったと報告されています。
その後も1980年代、2000年代と、長い間この傾向は続いています。
このように、
- 小学生でも
- 中高生でも
- 大学生でも
女子が男子より良い成績を取る傾向は一貫しています。
つまり、女子の学力優位は近年だけのものではなく、長い期間見られている特徴なのです。
「男子の学力危機」は本当か?
最近よく耳にする「男子の学力危機」は、実は誤解の可能性があります。
メディアでは「男子が女子にどんどん負けている」と報じられることがあります。
たとえば、2006年のニュース記事では、「男子が置いていかれている」との声がありました。
しかし、研究のデータでは男子の成績が下がった証拠は見つかっていません。
実際には、女子の成績が上がっていることが原因です。
つまり、
- 男子が悪くなったのではなく
- 女子がさらに努力して成績を伸ばした
というのが事実に近いです。
このように、「男子が落ちた」のではなく、「女子が伸びた」ために差が目立ってきたのです。
男子の学力危機という表現は、正確ではないかもしれません。
学力の性差は昔からほぼ変わらない
男女の成績差は、何十年たってもあまり変わっていません。
分析では、発表年と成績差にほとんど関連がないことが分かりました。
研究者たちは、1980年代の研究と2010年代の研究を比較しました。
すると、成績における性差の大きさはほぼ同じでした。
つまり、時代が進んでも、
- 女子の方が成績がやや高く
- 男子との差も安定している
という結果になりました。
これは、教育制度が大きく変わっても、性差に与える影響が少なかったことを示しています。
したがって、男女の成績差は長期間安定しており、最近急に広がったわけではありません。
メディアが誇張している可能性もある
メディアによる「男子劣勢」の話題は、大げさに伝えられている可能性があります。
とくに雑誌や新聞では、不安をあおるような見出しが目立ちます。
しかし、研究結果を詳しく見ると、
- 性差は小さく安定している
- 男子の学力が下がっている証拠はない
- 女子の成績向上が差を広げた
という実態が分かります。
また、実際の成績データは長期間にわたり同じような傾向を示しています。
そのため、ニュースで言われるほど急な変化は起きていません。
このことから、話題として取り上げられている「学力差の危機」は、事実とズレがある可能性が高いといえるでしょう。
性差は一時的なものではなく安定している
男女の成績差は、時代や地域に関係なく安定して存在しています。
これは一時的な現象ではありません。
分析対象となった約500の効果量において、
女子が男子より成績が高い傾向はほとんどすべてで共通していました。
また、
- 国や文化の違い
- 年代の違い
- 教科の違い
があっても、基本的な傾向は変わりませんでした。
つまり、女子の成績が男子よりやや高いという特徴は、世界中で、そして長期間にわたって見られる安定した現象です。
このことから、「学力の性差」は変わることの少ない、確かな傾向であると結論づけることができます。
最後に学力の性差まとめ
この記事でいろいろなデータを見て分かったのは、女子のほうが多くの教科で成績が高いということです。とくに言語や社会の教科でその差が目立ちます。数学や理科では男女差はとても小さく、ほとんど同じレベルでした。
また、女子は日々の努力や提出物、授業態度などで評価されやすい傾向があることもわかりました。これは、学校の成績がテストだけではなく、長期的な行動で決まるからです。
時代が変わってもこの傾向は大きくは変わっていません。メディアで言われる「男子の学力危機」は、女子の成績が伸びたことによるものかもしれません。
成績のちがいには、性別だけでなく、性格や環境なども関係します。自分の学び方を見つけるヒントとして、こうした研究を参考にするのもよいでしょう。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。