友情の遺伝って聞いたことがありますか?
「友だちって、気が合うから仲良くなるんでしょ?」そう思っている人が多いはずです。
でも、もしかすると、友だちになる理由はもっと深いところにあるかもしれません。
たとえば、生まれつき持っている遺伝子が影響している可能性があるのです。
そんなちょっと不思議なテーマを調べたのが、『How social and genetic factors predict friendship networks』という研究です。
アメリカの高校生たちのデータをもとに、誰と誰が友だちになっているのか、そしてそれがどんな環境や遺伝と関係しているのかを分析しました。
この記事では、この研究をもとに、「友情がどうやって生まれるのか」「遺伝がどう関わっているのか」をやさしく紹介していきます。
あなたの周りの友だちとのつながりも、もしかすると違った見え方になるかもしれません。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

友情の遺伝とは何か?
友情ができる理由に遺伝が関係している?
友だちができる理由に、遺伝が関係していることがわかってきました。
アメリカの研究では、ある遺伝子の型が似ている人どうしが友だちになる傾向がありました。
このように、「似たもの同士が集まる」ことを「ホモフィリー」といいます。
ホモフィリーには見た目や趣味、性格などが関係すると思われていました。
ですが、最近の研究では「遺伝子の型」までも似ていることが注目されています。
たとえば、以下のような特徴があります。
- 同じ学校にいること
- 似た性格を持っていること
- 同じような行動をとること
これらが「遺伝と友情の関係」と関わっている可能性があるのです。
友情はただの偶然ではなく、目に見えない共通点があるのかもしれません。
この研究では、そのひとつが「遺伝」だと考えられています。
友情の背景には、知られざる共通点がひそんでいるのです。
遺伝的に似た人と友だちになりやすいって本当?
似た遺伝子を持つ人は、友だちになりやすい傾向があります。
この研究では「DRD2」という遺伝子が注目されました。
これは人の行動や考え方に関わる遺伝子です。
喫煙や政治的な考え方ともつながりがあるとされます。
研究では次のような結果が出ました。
- 友だちどうしの遺伝子型に0.11の関係性が見つかりました
- 統計的に意味のある結果でした
- これは偶然ではない可能性があるという意味です
つまり、性格や行動のもとになるものが共通していると、友だちになりやすくなるのです。
ただし、これはすべての友だちにあてはまるわけではありません。
似た遺伝子を持つ人どうしが自然と引き合うことがあるのです。
遺伝と友人関係の研究が注目されている理由
友情に関わる遺伝子の研究は、社会全体にも関係しています。
なぜなら、友人関係が健康や行動にも影響するからです。
たとえば、肥満や喫煙の広がり方にも友情の影響が見られます。
友人が持つ考え方や行動のパターンが、まわりに伝わるのです。
そのため、研究者たちは次のような理由で注目しています。
- 健康に関わる行動が広がる仕組みを知りたい
- 社会的なつながりのしくみを理解したい
- 遺伝と環境がどう影響しあうかを知りたい
また、誰と友だちになるかによって、その人の生き方にも変化が出ることがあります。
それが学校、職場、家庭にも影響をおよぼすのです。
遺伝と友情を知ることは、人の行動や社会を知るカギになります。
正直謙虚さや開放性は友だち関係とどうつながる?
人の性格と友情は深い関係があります。
とくに「正直謙虚さ(倫理観)」や「開放性(知的好奇心)」は大きな要素です。
こうした性格は、生まれつきの性質と関係しています。
友人関係では、以下のようなことが起こりやすいです。
- 倫理的な人どうしが引き合う
- 保守的な人どうしが気が合う
- 似た考え方の人と行動が重なる
つまり、性格が似ている人は、自然と行動パターンも似てきます。
これが友情のきっかけになることも多いのです。
性格も遺伝の影響を少なからず受けています。
このように、性格と遺伝と友情は三つの輪のようにつながっています。
似た性格の人は、知らないうちに近づいているのかもしれません。
友情の遺伝が注目されるようになった背景
近年、遺伝子と社会のつながりを調べる研究が進んでいます。
これまでは性格や環境が友情に影響すると思われていました。
しかし、遺伝子もその一部を担っているという新しい考えが広まっています。
この研究の注目ポイントは以下のとおりです。
- 遺伝子型が似ている人どうしが友人になる傾向がある
- 社会的な環境もその関係を左右している
- とくに学校という場が大きな影響を持つ
つまり、「友だちを選んでいるようで、実は選ばされている」可能性があるのです。
それは学校の制度や環境による影響かもしれません。
遺伝と友情の関係は、これからの社会を考えるうえで大切な視点となっています。
友情の遺伝を調べた研究
アメリカの高校生を対象にした調査ってどんなもの?
この研究はアメリカの全国的な高校生調査をもとにしています。
調査名は「全米青少年健康調査(Add Health)」です。
1994年に始まり、134校・約9万人の生徒が参加しました。
その中から約2万人が自宅での追加調査を受けました。
この中でも特に注目されたのが、兄弟や双子の遺伝子データがある生徒たちです。
遺伝子の型を調べた上で、友情との関係を分析しました。
調査では次のような情報が集められました。
- 生徒が誰を友人と思っているかの情報
- 性別、人種、年齢、家庭環境などの基本情報
- 遺伝子の型(とくにDRD2という遺伝子)
これにより、友情と遺伝の関係を詳しく調べることが可能になりました。
全国規模で行われたこの調査が、友情の遺伝を明らかにしたのです。
1,500組以上の友だちを分析してわかったこと
研究では1,503組の友人関係を分析しました。
分析の対象は、両者の遺伝子や年齢、性別、人種などがわかっているペアです。
また、どちらかが兄弟のデータを持っていることも条件でした。
これにより、同じ学校内での友人関係に注目することができました。
学校によって友人関係のつながり方が異なることも調べられました。
データの特徴は以下の通りです。
- 平均年齢は約15.7歳
- 約半数が女子でした
- 大多数は白人の生徒でした
この分析によって、学校の社会環境が友情と遺伝の関係に影響を与えることが見えてきました。
たとえば、不平等が大きい学校ほど、似た遺伝子の友人が多く見られました。
友情と遺伝のつながりは、環境とセットで理解することが大切です。
使われた「DRD2遺伝子」って何?
DRD2遺伝子は、人の行動や気分に関わるものです。
これはドーパミンという脳内物質の受け取りに関係しています。
ドーパミンは「やる気」や「ごほうび」の感覚に関係する物質です。
この遺伝子には「TaqIA多型(たくわん・えーたけい)」という違いがあります。
この違いが、人の性格や行動のパターンに影響を与えると考えられています。
たとえば、以下のような行動と関係があります。
- 喫煙しやすさ
- 政治的な考え方
- 物事のとらえ方
つまり、友人を選ぶときの感じ方や考え方に間接的な影響があるのです。
このため、友情の研究でもこの遺伝子が使われました。
DRD2は人と人のつながりを考える上で、重要な手がかりとなる遺伝子です。
友人関係と似た遺伝子がどれくらい一致したの?
友人どうしの遺伝子が似ているかを数値で見た結果があります。
研究では、友人の遺伝子型から予測した場合、0.11の一致度がありました。
この数字は偶然とは言えない程度に意味のあるものでした。
さらに詳しく見ると、こんな特徴が見えました。
- 相手の年齢、人種、性別を調整した上でも結果が出た
- 似ている遺伝子の人どうしが自然と友人になっていた
- とくに「互いに友だちだと認め合っている関係」で強かった
このことから、「ただの偶然ではない」可能性が高いと考えられています。
友人関係には、見た目だけでなく遺伝という深い共通点があるかもしれません。
なぜ学校を単位に調べる必要があったのか?
学校という場は、友情と遺伝を結びつける大きな環境です。
なぜなら、学校はクラス分けや活動の場を決める仕組みがあるからです。
人は同じ場所で過ごす時間が長いほど、関係ができやすくなります。
また、学校によって次のような違いがあります。
- 経済的な不平等の程度(ジニ係数)
- 人種ごとの友人関係の偏り(アルファ指標)
- クラスや活動の分け方(トラッキング制度など)
これらが友情にどう影響しているのかを調べるために、学校ごとの分析が必要でした。
実際、学校によって「似た遺伝子の友人」が多いところと少ないところがありました。
学校という環境が、友情の「選び方」に見えない影響を与えていることがわかりました。
友情の遺伝が強くなるとき
学校の格差が大きいほど友情の遺伝が見られた
学校内の格差が大きいほど、遺伝の似た者同士が友人になりやすいことがわかりました。
この格差は「ジニ係数」という数値で表されます。
ジニ係数は教育の不平等の大きさを示す指標です。
研究では、ジニ係数が高い学校で以下のような傾向が見られました。
- 同じような遺伝子を持つ人同士が友人になる確率が高い
- クラス分けなどにより出会う人が限られていた
- 選べる友人の幅がせまくなっていた
格差が大きい学校では、無意識のうちに似た環境・似た遺伝子の人と一緒にされやすくなります。
この結果、遺伝的に似た人と友人になる確率が高くなるのです。
つまり、格差が友情の形を変えてしまうことがあるのです。
同じクラスにいることで似た者同士が集まりやすくなる
学校でのクラス分けは、友情の遺伝に影響を与えることがあります。
同じクラスにいる人は、長時間一緒に過ごします。
そのため、出会う機会が多くなり、自然と友人関係が生まれやすくなります。
クラス分けは次のような理由で行われます。
- 学力や成績に応じた分け方
- 特別な活動や教科ごとの編成
- 進路にあわせたコース選び
これにより、性格や行動が似ている人が同じクラスに集まりやすくなります。
そして、その中で友人関係が築かれることで、結果的に遺伝的に似た人が集まりやすくなるのです。
同じ時間・場所にいることで、友情の形も似通ってくるのです。
トラッキング(能力別クラス分け)の影響とは?
トラッキング制度とは、学力や進路に応じて生徒を分ける仕組みのことです。
この制度は一見、成績に合わせた公平な方法のように思えます。
しかし、この分け方が、似たタイプの生徒同士を集める結果にもつながります。
トラッキングによって起こることは以下の通りです。
- 同じような成績・性格の人が同じグループになる
- 一緒に過ごす時間が長くなり、交流が増える
- 遺伝的に似た行動パターンを持つ人が関わりやすくなる
つまり、学校側が無意識のうちに「友情の相手」を決めてしまうような状況になるのです。
この制度がある学校ほど、遺伝の似た人どうしが友だちになりやすくなるといえます。
能力別の仕組みが、友情のつながり方に見えない影響を与えているのです。
選んでるようで選んでいない友情の形
私たちは自分で友だちを選んでいるように感じますが、実はそうとは限りません。
学校の制度や環境が、出会う人の範囲を決めているからです。
これが「誘発的な遺伝×環境の関係」と呼ばれる考え方です。
この仕組みでは、次のようなことが起こります。
- 成績や行動に応じてグループが分かれる
- その中で自然と友人ができる
- もともとの遺伝的特徴が、環境を呼び寄せている
つまり、「似た性格の人が似た環境に置かれ、そこで友人になる」ことが起こっているのです。
自分で選んだと思っている友情も、実はまわりの仕組みの中で作られているのかもしれません。
友情は、見えない仕組みによってつくられていることがあります。
社会環境が友情に影響を与えるってどういうこと?
友情は、人の気持ちや性格だけで決まるものではありません。
学校という社会的な場が、友人関係の土台をつくっているのです。
この「社会環境」が、誰と出会い、誰と関係を築くかに大きく関係しています。
研究では次のようなことがわかりました。
- 学校ごとに友情のパターンが大きく異なる
- 格差がある学校ほど遺伝的に似た友人が多かった
- 格差が少ない学校では、友情に遺伝の影響があまり見られなかった
つまり、社会環境の違いが、友情の遺伝の現れ方を変えているのです。
これは、学校だけでなく、地域や社会のあり方にも共通する考え方です。
どんな環境で育つかが、友情の形に深く関わっているのです。
友情の遺伝が弱くなるとき
格差が少ない学校では友情の遺伝が見られなかった
学校内の格差が少ないと、友情に遺伝の影響はあまり見られませんでした。
研究では「ジニ係数」が低い学校で、遺伝的な似た者同士の友情はほとんど確認されませんでした。
これは、自由に友人を選べる環境では、遺伝の影響が小さくなるということを示しています。
格差が小さい学校では次のような特徴がありました。
- 生徒の出会いの幅が広い
- クラス分けによる制限が少ない
- 学力や家庭の背景に左右されにくい
このような環境では、人とのつながり方に多様性が生まれやすくなります。
その結果、遺伝的に違う人とも友人になれる可能性が高まるのです。
格差が少ない環境では、友情がより自由につくられるのです。
多様な人と関われる学校ではどうなる?
いろいろな背景を持つ人が混ざる学校では、遺伝の似ている人とだけ友だちになる傾向は弱くなります。
これは、多様な人と出会えることで、選択の幅が広がるためです。
具体的には以下のような環境が影響しています。
- 異なる人種や文化が共存している
- 経済的な違いを気にせず関われる
- 教室や行事が混合型で構成されている
このような学校では、「似ているから友だちになる」というより、「一緒にいて楽しい人とつながる」傾向が強まります。
結果として、遺伝的な共通点よりも、人柄や関係の楽しさが重視されるのです。
多様性のある環境では、友情の可能性が広がります。
遺伝よりも性格や好みが影響する場合も
友情ができる理由は、遺伝だけではありません。
性格や好きなこと、共通の体験なども大きく関係しています。
とくに、自由に交流できる環境では、性格や好みが友情に与える影響が大きくなります。
研究でも、遺伝的な一致が小さい場合でも、次のような共通点で友人関係が築かれていました。
- 一緒に過ごす時間が長い
- 好きな音楽やスポーツが似ている
- 気持ちが通じやすいと感じる
このように、人は気の合う相手を自然に見つけようとします。
遺伝の一致がなくても、性格や価値観が近ければ友情は十分に成り立つのです。
人との関係は、似ている気持ちから始まることも多いのです。
同じ人種の友だちが多いとどうなる?
人種が同じ人とばかり友だちになると、友情に遺伝が関わるように見える場合があります。
これは「人種的な分かれ」が、遺伝的な分かれにもつながるからです。
たとえば以下のような場合があります。
- 学校が人種で自然に分かれてしまっている
- 文化や言葉の壁で交流がしづらい
- 無意識のうちに同じ人種同士で集まる
このような状況では、似た遺伝子を持つ人とだけ関わる機会が増えてしまいます。
その結果、友情の中に「遺伝の一致」が見えるようになるのです。
ですが、これは遺伝が直接友情をつくっているのではなく、社会の構造が間接的に影響していると考えられます。
同じ人種だけでかたまると、遺伝の影響が強く見えることがあります。
社会的な自由度が友情に与える力
自由に人と関われる学校では、友情のパターンが多様になります。
これは「社会的な自由度」が高いからです。
自由度があるとは、自分で交友関係を選べる余地が大きいという意味です。
具体的には次のような特徴があります。
- クラス分けが柔軟で、出会う相手が多い
- 友だちを選ぶ基準が決めつけられていない
- 教員や制度が生徒の行動を制限しない
このような学校では、遺伝ではなく人柄や相性を重視した友情が生まれやすいです。
そのため、遺伝の一致が見られにくくなるのです。
自由な環境では、自分らしい友情が生まれる可能性が高まります。
友情の遺伝が教えてくれること
遺伝は自分で選べないけど、影響はある
人は生まれつきの遺伝子を自分で選ぶことはできません。
けれども、その遺伝子がまわりの人間関係に影響を与えることがあります。
研究では、遺伝子の違いが友人関係にあらわれる場面が見つかりました。
特に、DRD2という遺伝子の型が似ている人が友人になりやすい傾向がありました。
とはいえ、これは遺伝子がすべてを決めているという意味ではありません。
次のような要因が重なって友情が生まれるのです。
- 遺伝子に影響された性格や行動
- 社会的な環境や出会いの場
- 一緒に過ごす時間や経験の共有
つまり、遺伝子はあくまで「きっかけのひとつ」にすぎません。
自分の意志やまわりの人との関わり方も大きく影響します。
自分で選べない遺伝でも、人とのつながりに関わることがあるのです。
学校や制度が友情をつくっているかもしれない
友情は、学校や制度といった外からの仕組みによってつくられている可能性があります。
私たちは自分で友だちを選んでいるように感じますが、そうとは限りません。
たとえば、次のような場面で制度が影響します。
- 能力別にクラスが分けられる
- 同じ活動に参加する人が限られている
- 学校内での交流の幅が決まっている
こうした仕組みによって、似たタイプの人が集まりやすくなるのです。
結果的に、遺伝子の似ている人が友人になることも増えていきます。
つまり、友情は本人の意思だけでなく、制度によって形づくられている部分もあるのです。
知らないうちに、環境が友情をつくっていることがあります。
遺伝子で決まるのではなく「環境がきっかけ」になる
遺伝子だけでは友情は決まりません。
大切なのは、それを活かす環境や出会いの場です。
研究では、遺伝の影響が見られたのは特定の学校に限られていました。
これは、環境が遺伝子の働きを強めたり弱めたりすることを示しています。
たとえば、次のような環境が影響します。
- 自由な交流ができるかどうか
- 出会いの機会があるかどうか
- 学校が生徒をどう分けているか
遺伝子が友情の「たね」だとすれば、環境はそれを育てる「土」のような存在です。
環境次第で、その影響が表に出たり、見えにくくなったりします。
友情は、環境の中で育つ関係だといえるのです。
自由な交友関係を持てる環境が大切
友人関係が自由につくれる環境は、とても大切です。
なぜなら、その自由さが多様な出会いを生み出し、深い友情を育てるからです。
研究では、格差が少なく自由な学校では、遺伝の影響が小さくなることがわかりました。
これは、いろいろな人と出会い、交流できることで、友情の形が多様になるためです。
自由な環境の特徴には、以下のような点があります。
- クラスや活動に制限が少ない
- 人種や家庭環境にとらわれず交流できる
- 自分の意志で関係をつくる機会がある
このような環境では、人柄や考え方にひかれて友人ができることが多くなります。
結果として、遺伝に関係のない友情が増えるのです。
友情の広がりには、自由な関係性を許す環境が必要です。
友情と遺伝の関係はこれからも注目されるテーマ
この友情と遺伝の関係は、今後も研究が進む分野です。
これまで見えなかった人とのつながりのしくみを明らかにしてくれるからです。
今回の研究から、次のようなポイントがわかってきました。
- 遺伝が友情に影響を与えることがある
- その影響は学校などの社会環境によって変わる
- 似た遺伝子を持つ人が友人になる傾向は一部に見られる
さらに、将来的には以下のような課題にもつながります。
- 学校の制度が友情にどう影響するのか
- 社会の不平等が人間関係に与える影響
- 行動や習慣の広がり方との関係
友情の背景にあるものを知ることで、人との関わり方をもっと深く考えることができます。
友情と遺伝は、人とのつながりを見つめ直すヒントになるのです。
最後に
この記事では、「友情の遺伝」というちょっと意外なテーマについて紹介してきました。
友だちになる理由には、性格や趣味だけでなく、生まれつきの遺伝子や学校などの社会的な環境も関係していることが分かってきました。
とくに、格差の大きい学校では、遺伝子の似た人同士が友だちになりやすいという結果が出ています。
でもそれは、自分で選んだというよりも、学校の仕組みや出会いの場が影響していたのです。
一方で、自由に人と関われる環境では、遺伝の影響はあまり見られず、人柄や気持ちの通じ合いが大事になってくることもわかりました。
つまり、友情は「似ているからできる」だけではなく、「どんな環境にいるか」もとても大きなカギになるのです。
これから友だちを選ぶとき、見えない影響にも目を向けてみると、新しい発見があるかもしれません。
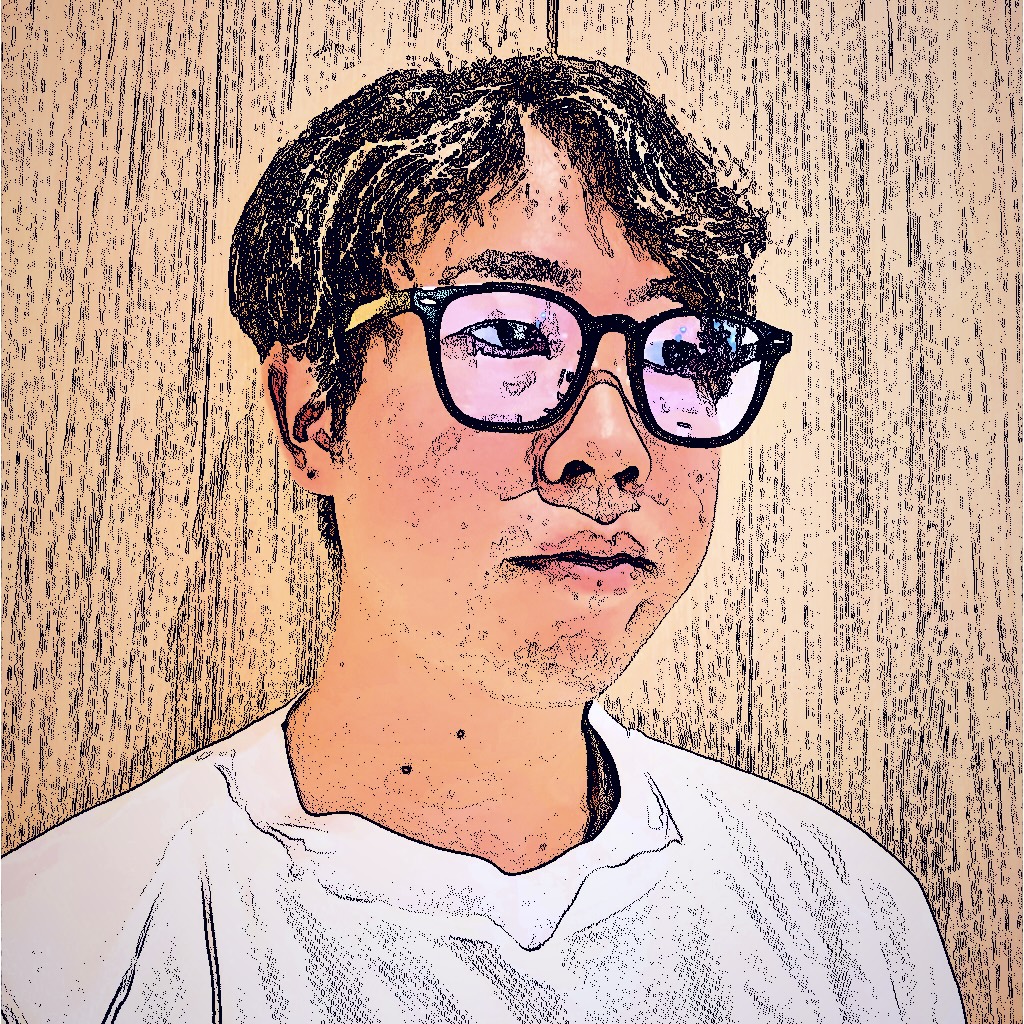
ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。








