学力の要因って、いったいどんなものがあるのでしょうか?
テストの点が良かったり、授業がスラスラわかる人を見ると、「もともと頭がいいから」と思いがちです。
でも本当にそれだけでしょうか?
実は、学力にはたくさんの影響があることがわかっています。
たとえば、自分の性格や、家の環境、学校の雰囲気、先生との関係など、身の回りのすべてが関係しているのです。
この記事では、『学業成績の決定要因:過去25年間のメタ分析の体系的レビュー』という研究をもとに、学力にどんな要因があるのかをわかりやすく紹介します。
「どうして勉強がうまくいかないんだろう?」
「もっと学力を伸ばすにはどうしたらいいの?」
そんな疑問に答えながら、あなたの可能性をひろげるヒントをお届けします。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

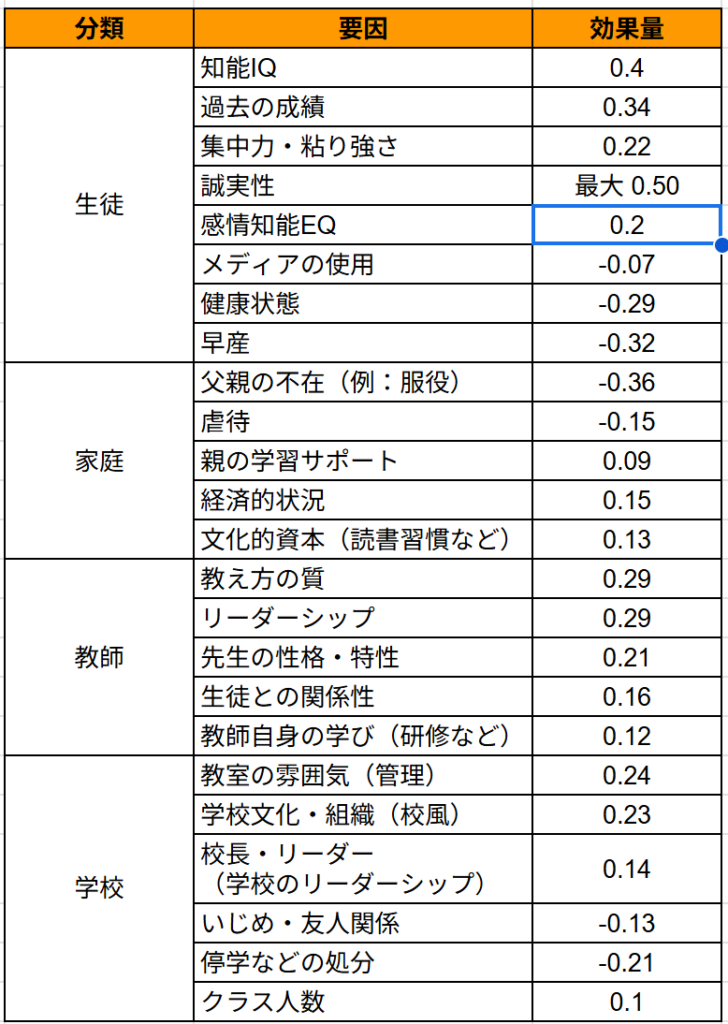
目次
学力の要因にはどんな種類がある?
生徒自身の特徴が学力にどう関わるのか
学力には生徒の内面的な特徴が強く関係しています。
とくに知能や感情、性格の傾向が影響を与えます。
これらは勉強の理解度や続ける力に関係します。
また、集中力ややる気も見逃せないポイントです。
さらに、過去の学習の成果も将来の成績に影響します。
主な要因は次のようなものです。
- 知能(考える力)
- 感情コントロール
- 誠実性(コツコツ努力する力)
- 過去の学習経験
こうした要因がそろうと、学力が伸びやすくなります。
学力はただの才能だけでなく、性格や考え方でも変わります。
家庭環境が学力に与える影響とは
家庭の状況も学力に大きく関わっています。
とくに親の存在や家庭内の雰囲気が重要です。
父親がいない家庭では成績が下がりやすい傾向があります。
また、家庭での虐待があると学習への意欲が落ちます。
さらに、お金のあるなしや文化的な影響もあります。
具体的には次のような要因があります。
- 父親がいないこと(例:服役など)
- 親の関与(勉強を見てくれるかどうか)
- 経済的な余裕
- 家庭内の安心感
家庭の安定は、勉強に集中するための土台になります。
学力は家の中の環境とも深くつながっています。
学校の仕組みが成績に与える意外なポイント
学校の環境やルールも成績に関係します。
教室の空気や先生の対応が大きなカギとなります。
特に、落ち着いた教室は集中しやすいです。
逆に、問題行動への厳しすぎる対応は逆効果です。
学校全体の雰囲気も、やる気に影響を与えます。
主な影響要因は以下のとおりです。
- 教室の雰囲気
- 懲戒の方法(停学など)
- クラスの人数
- 友人との関係
- 学校の文化やルール
これらは直接勉強に関係なくても成績を左右します。
学力は学校の雰囲気によっても大きく変化します。
教師の特徴が学力を左右するって本当?
教師の教え方や性格も学力に影響します。
教え方の上手な先生に出会うと成績が伸びやすいです。
また、生徒との関係が良い先生ほど成果が出やすいです。
さらに、先生自身が学び続けていると授業の質が上がります。
リーダーシップをもつ先生はクラスをまとめる力があります。
注目すべき要因は以下のとおりです。
- 教え方の質
- 先生の人柄や態度
- 生徒との信頼関係
- 先生の学びへの姿勢
- リーダーシップ力
先生の関わり方ひとつで、生徒のやる気が大きく変わります。
学力を高めるには先生の存在も欠かせません。
どの要因が一番学力に影響するのか?
一番強い影響を持つのは教師の特徴です。
この研究では、教師の要因が平均でr = 0.23でした。
これは他の要因(生徒:0.08、家庭:0.06、学校:0.06)より大きいです。
とくに授業の質や先生の関係性が効果的でした。
一方で、誠実性や知能などの個人要因も重要です。
要点を整理すると次のとおりです。
- 教師の教え方と関係性が一番影響
- 生徒の知能や誠実性も高い効果
- 家庭の安定が基礎として必要
- 学校環境はサポート的な役割
学力を伸ばすには、先生と生徒、家庭、学校の連携が大切です。
どれか一つではなく、全部のバランスが大事になります。
学力の要因を「生徒の特徴」から見てみよう
学力の要因のなかで知能の高さが重要
知能は学力にもっとも強く関係する個人要因です。
この研究では知能の効果量がr = 0.40でした。
これは中くらいから強い影響を意味します。
知能とは、問題を解いたり考える力のことです。
新しいことを理解するスピードにも関係します。
たとえば、次のような力を含みます。
- 理解力
- 推理力
- 記憶力
- 柔軟な思考
このような知的な力が高いと、勉強も早く身につきます。
知能は学力の土台となる力だといえるでしょう。
過去の成績がその後の学力を左右する
これまでの成績は次の学習の成果に強く関わります。
過去の学習経験が次の勉強の理解を助けるのです。
とくに基礎の知識がしっかりしていると応用が効きます。
研究ではこの要因の効果量はr = 0.34とされています。
主な理由は次のようなものです。
- 基礎ができていると理解が速い
- 成功体験が自信をつくる
- 習慣化された勉強法が使える
つまり、積み重ねた学びは大きな財産となります。
これまでの成果は、未来の成績にしっかりつながります。
集中力ややる気が勉強の成果に直結する
集中して取り組む力や意欲は学力に関係します。
たとえば、すぐにあきらめない姿勢が成果を生みます。
この研究では、集中力や粘り強さの効果量はr = 0.22でした。
これはやや高い影響といえます。
次のような行動が学力と結びついています。
- 勉強中に他のことに気を取られない
- 失敗してもすぐ立ち直る
- 自分で考えて続けようとする姿勢
これらの行動はすぐにでも意識できる要素です。
意識と習慣が、学びの深さを大きく変えていきます。
感情知能や感情コントロールが成績に影響
感情の安定や気持ちの調整力は学力に影響する大切な要素です。
この感情知能とは、自分や他人の感情を理解し、うまく対応する力のことです。
この力があると、落ち着いて学習に取り組むことができます。
研究でも、感情知能の効果量はr = 0.20と、学力との関係が示されています。
具体的には次のような力が関係します。
- 落ち着いているとミスが減る
- 不安が少ないと勉強に集中できる
- 自信があると難しい問題に挑戦できる
感情知能が高いと、勉強のストレスにも上手に対応できます。
心の状態が安定することが、学びの土台となるのです。
誠実性や努力の継続が学力の要因で重要
誠実性は学力に強く関わる性格の特徴です。
この特性は、まじめでコツコツ取り組む力のことです。
この性格傾向が高い人は勉強も続けやすいです。
研究では、誠実性が高いと成績が良い傾向がありました。
次のような行動が誠実性に関係しています。
- 毎日少しずつ勉強する
- 宿題をきちんとやる
- 時間を守って行動する
こうした行動の積み重ねが大きな成果を生みます。
努力を続ける力が、学力アップの土台となります。
学力の要因を「家庭の環境」から考える
親がいない家庭は成績に影響が出やすい
父親がいない家庭は学力に悪い影響を与えます。
研究では、父親が服役中などで不在だと成績が下がる傾向がありました。
その効果量はr = -0.36で、かなり大きな影響です。
家族の安定が学習に集中するための土台となります。
影響の理由には次のようなことがあります。
- 家庭内のサポートが少なくなる
- 精神的な不安が強くなる
- 学習への関心が薄れやすい
家庭に安心できる環境があるかどうかが大切です。
親の存在は、成績にも心にも深く関わっています。
家庭内での虐待が学習に悪影響を与える
虐待を受けた子どもは学力が下がりやすいです。
研究では、家庭内の虐待と学力に負の関係がありました。
効果量はr = -0.15で、中くらいの影響があります。
暴言や身体的な暴力は、学びへの意欲を弱めてしまいます。
悪影響の例としては以下のようなことがあります。
- 学校に行きたくなくなる
- 勉強に集中できない
- 自信がなくなる
安全な家庭環境があってこそ、学力は育ちます。
子どもは安心の中でこそ力を発揮できるのです。
親の学習サポートが成績にどう関係するか
親が勉強を手伝うことは成績向上に役立ちます。
ただし、そのサポートの内容によって効果は変わります。
効果量の平均はr = 0.09と小さいですが、差が大きいです。
よい関わり方をすると、学力がしっかり伸びます。
よいサポートには次のような特徴があります。
- 子どもと一緒に考える
- 励ましたり褒めたりする
- 勉強時間をつくる手伝いをする
反対に、怒ったり押しつけたりすると逆効果です。
親のかかわり方しだいで、学力は良くも悪くもなります。
お金のゆとりが学力に与える影響とは
経済的な安定は学力にじわじわと効いてきます。
研究では、経済状況と成績の関係はr = 0.15でした。
これは小さめですが、確かな関係です。
教材の購入や塾などの機会に差が出ます。
影響を受ける場面としては以下があります。
- 教材や本を買えるかどうか
- 静かな勉強スペースがあるか
- 習い事や塾に通えるかどうか
お金がすべてではありませんが、選べる環境が広がります。
ゆとりのある生活は、学びやすい環境を支えてくれます。
親の文化的な背景も見逃せないポイント
家庭の文化的な雰囲気も学力に関わります。
文化的背景とは、本を読む習慣や教育への考え方のことです。
研究では文化的資本との関係はr = 0.13でした。
これは経済力とは少しちがう影響です。
具体的な文化的な支えには次があります。
- 家に本がたくさんある
- 親が教育を大事にしている
- 子どもとよく会話をしている
こうした文化があると、学ぶことが当たり前になります。
家庭の考え方や雰囲気が、知らないうちに学力を支えています。
学力の要因を「学校の環境」から読み解く
教室の雰囲気が勉強に集中できるかを左右
教室の雰囲気は学力に影響する大きな要因です。
落ち着いた空気の教室では集中しやすくなります。
研究では、教室の管理の効果量がr = 0.24でした。
これは中程度の正の影響で、しっかりした関係があります。
具体的には次のような雰囲気が大切です。
- 授業中に静かである
- ルールが守られている
- みんなが集中している
先生の声かけやクラスの文化も関係しています。
教室の空気は、毎日の学びの質を左右します。
学校でのルール違反への対応が逆効果に?
問題行動への対応はやり方によっては逆効果になります。
とくに停学などの強い対応は学力を下げることがあります。
この研究では、停学の効果量はr = -0.21でした。
つまり、強い処分が逆に成績を悪くする可能性があるのです。
注意したい点は以下のようなことです。
- 停学で学習の機会が減る
- 学校からの疎外感が強くなる
- 生徒がやる気をなくしてしまう
ルールを守らせることは大切ですが、方法も重要です。
思いやりのある対応が、学力にもつながります。
クラスの人数が少ないと学びやすい?
人数の多さよりも教え方や雰囲気のほうが大切です。
クラスの人数が少ないほどよいと思われがちですが、
研究では、人数の影響はとても小さいものでした。
効果量はr = 0.10程度とされています。
人数が関係しにくい理由は次のとおりです。
- 少人数でも教え方が悪ければ効果は小さい
- 多人数でも教室管理がよければ集中できる
- 生徒の性格や意欲も影響する
つまり、人数だけで成績が決まるわけではありません。
教室の質が学びやすさのカギになります。
友達との関係が勉強にどう影響するのか
友人関係はときに学力に悪い影響を与えることがあります。
とくに、いじめや仲間外れがあると成績が下がります。
研究では、いじめの影響はr = -0.13と報告されています。
これは小さくても確かなマイナスの影響です。
悪い影響を与える例は次のとおりです。
- 勉強に集中できなくなる
- 自信を失いやすくなる
- 学校に行きたくなくなる
友人関係が安心できるものかどうかが大切です。
よい人間関係が、学びを前向きにしてくれます。
学校の文化や組織が学力に影響する理由
学校全体の考え方や仕組みも学力を左右します。
これは「学校文化」や「学校の組織」と呼ばれる要素です。
研究では、この要因の効果量はr = 0.23でした。
教員どうしの協力や、学校の目標などが関係しています。
影響するポイントには次のようなものがあります。
- 学校の雰囲気が前向きかどうか
- 教師どうしの連携があるか
- 学校としての一貫した方針があるか
こうした仕組みが整っている学校では、生徒の成績も伸びやすいです。
学びやすい学校づくりが、生徒の力を引き出します。
学力の要因を「先生の影響」から考える
教え方のうまさが学力を伸ばす大きな力に
先生の教え方の質は学力に最も強い影響を与えます。
研究では、教え方の質の効果量がr = 0.29と高く出ています。
これは中〜大の影響で、とても重要な要素です。
教え方がわかりやすいと、生徒の理解も深まります。
良い教え方の特徴には次のようなものがあります。
- 例を使って説明する
- 生徒の反応を見ながら進める
- つまずいたときにフォローがある
こうした丁寧な指導は、学びを楽しいものに変えてくれます。
教え方ひとつで、学力はぐんと伸びるのです。
先生の性格や態度が成績を左右することも
先生自身の人柄や態度も学力に関係します。
研究によると、先生の性格的特徴も効果がありました。
効果量はr = 0.21で、決して小さな影響ではありません。
やさしさや誠実さが、生徒のやる気を引き出します。
影響を与える先生の特徴には次があります。
- 話しやすい雰囲気がある
- 生徒に対して公平である
- 失敗しても励ましてくれる
信頼できる先生の存在は、生徒の安心感につながります。
だからこそ、先生の人柄も学力にとって重要です。
生徒との関係が成績に深く関わる
先生と生徒の関係の良さも成績に大きく影響します。
この要因の効果量はr = 0.16とされており、しっかりした関係があります。
関係がよいと、生徒は質問しやすくなります。
また、学ぶことに対して前向きになります。
よい関係をつくるポイントは次のとおりです。
- 生徒の話をよく聞く
- 困ったときにすぐ助ける
- 努力をきちんと認める
信頼関係があると、勉強への意欲がぐんと高まります。
教科の内容だけでなく、心のつながりも大切なのです。
先生自身の学びが生徒の成長にもつながる
先生が学び続ける姿勢は、生徒の学力にも影響します。
研究では、先生の研修や学び直しも効果があると示されています。
効果量はr = 0.12で、やや小さいですが確かな影響があります。
新しい教え方や知識を身につけた先生は授業がより良くなります。
具体的な学びの内容は次のようなものです。
- 教え方の改善
- 生徒理解のための知識
- 最新の教材や情報の活用
先生が成長すると、それが授業に反映されます。
結果として、生徒の理解も深まっていくのです。
リーダーシップのある先生は効果が高い
リーダーシップのある先生は学力を引き出す力があります。
このリーダーシップとは、クラスをよい方向へ導く力のことです。
この要因の効果量はr = 0.29で、授業の質と同じくらい高い数値です。
指示が的確で、安心して学べる環境をつくります。
リーダーシップのある先生の特徴は以下のとおりです。
- クラスの目標を明確にする
- 一人ひとりの役割を大切にする
- 全員が参加できるように工夫する
まとめ役としての力が、クラス全体の力を底上げします。
学びのリズムをつくる力がある先生は、成績にも影響を与えるのです。
どの要因が一番学力に影響するのか?
教師の教え方と関係性が一番影響
学力に最も強い影響を与えるのは教師の要因です。
この研究では、教師に関する効果量がr = 0.23でした。
これは生徒・家庭・学校のどの要因よりも高い数値です。
とくに教え方のうまさや、生徒との関係が重要でした。
教師要因で特に強かったのは次のとおりです。
- 教え方の質(r = 0.29)
- リーダーシップ(r = 0.29)
- 関係性の良さ(r = 0.16)
これらの要素がそろうと、学力がしっかり伸びやすくなります。
やはり、よい先生との出会いが学びの大きな力になります。
生徒の知能や誠実性も高い効果
生徒自身の力も、学力に大きな影響を与えます。
とくに知能(r = 0.40)と過去の成績(r = 0.34)は効果が高いです。
これは中〜強い影響とされ、学力と直結します。
さらに、誠実性や感情の安定も見逃せません。
生徒要因で目立ったものは以下のとおりです。
- 知能の高さ(考える力)
- 集中力とやる気(r = 0.22)
- 感情の安定(健康・情動性)
- 誠実性(努力を続ける力)
本人の持つ力と、どれだけ努力できるかが大きな鍵になります。
学力は「もって生まれた力」と「育てた力」の両方で決まります。
家庭の安定が学力の土台を支える
家庭の影響は小さくても、学力の土台になります。
まず家庭の要因全体の効果量はr = 0.06と小さいです。
しかし、これは見過ごしていい数字ではありません。
安全で落ち着いた家庭は、学習に集中する助けになります。
家庭要因で重要だったのは次のとおりです。
- 父親の不在(r = -0.36)
- 虐待などの被害(r = -0.15)
- 経済的なゆとり(r = 0.15)
- 親の関わり(r = 0.09)
小さな積み重ねでも、子どもの学びには大きく響きます。
安心して勉強できる環境が、学力を長く支えていきます。
学校全体の雰囲気が学力を支える
学校の環境も学力に影響を与えるサポート的な力です。
研究によると、学校全体の効果量はr = 0.06でした。
一つひとつの要因は小さいですが、組み合わせが大切です。
とくに教室の管理や学校文化は影響がありました。
影響を持つ学校要因は以下のようなものです。
- 教室の雰囲気(r = 0.24)
- 学校の文化や組織(r = 0.23)
- 友人関係(r = -0.13)
- 停学などの処分(r = -0.21)
勉強に集中できるかどうかは、学校の空気にも関係します。
学校全体で「学びを大切にする文化」を育てることが大切です。
バランスのとれた支援が学力をのばすカギ
最も大切なのは、全体のバランスです。
教師・生徒・家庭・学校のすべてが関係して学力は育ちます。
どれか一つだけが良くても、それだけでは足りません。
とくに弱い部分があると、全体の力が発揮されにくくなります。
学力向上のために必要なのは次のようなことです。
- 生徒本人のやる気や努力
- 教師の指導力と関係性
- 家庭の安定と支援
- 学校の安心できる雰囲気
この4つがうまくかみ合うことで、学びの力は最大になります。
学力は「ひとりの力」ではなく、「みんなの力」で育ちます。
最後に学力の要因まとめ
学力は、ただの「頭のよさ」だけで決まるものではありません。
この記事で紹介したように、自分の性格や努力のしかた、家庭の環境、学校の雰囲気、そして先生との関係など、いろいろな「学力の要因」が影響しています。
とくに大きな力を持っていたのは、先生の教え方や関係性でした。
また、知能や誠実性、感情の安定など、自分の内面も大きく関係しています。
「自分のせいだけじゃなかったんだ」と思った人もいるかもしれません。
でも逆にいえば、自分のまわりの環境や関係を見直すことで、学力はきっと変えていけるということです。
今日からできることを少しずつやってみましょう。
努力する自分を信じて、一歩ずつ進めば、未来はきっと変わります。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。








