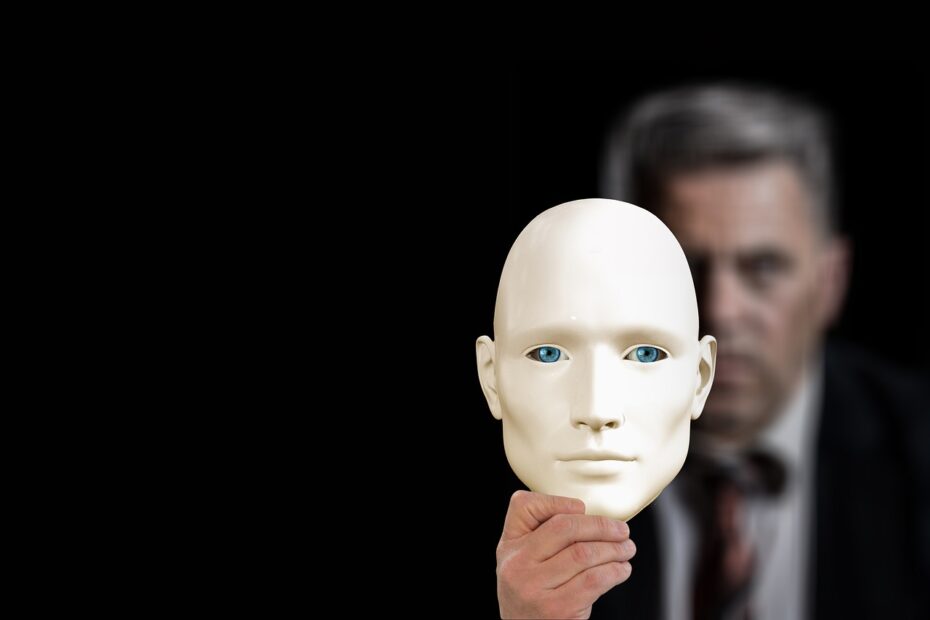「悪者のEQ」って聞いたことありますか?
これは、他人の気持ちを感じたり理解したりする「共感力(EQ)」が、ちょっとズレていたり、うまく働かない人のことを指す言葉です。
最近では、「感じないのに読める」人が増えていると言われています。つまり、人の気持ちはわかるのに、寄り添ったり共感したりしないのです。
そういうタイプの性格について、心理学の研究では「ダークトライアド」と呼ばれる3つの性格特性が注目されています。
このテーマについて詳しく調べたのが、『The affective and cognitive empathic nature of the dark triad of personality』という論文です。
この記事では、そんな悪者タイプの人たちが持つEQの特徴や、共感力との関係について、わかりやすく紹介していきます。「ちょっと冷たいかも?」と感じる人の心の中、のぞいてみませんか?
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

悪者のEQとは何か?その意味と背景
悪者って誰のこと?
悪者とは、人をだましたり利用したりする性格の人のことです。
もちろん法律を破るわけではありませんが、周りの人に冷たい態度をとったり、自己中心的な行動をとったりします。
このような人たちには、共通する性格の特徴があります。
それが心理学で「ダークトライアド」と呼ばれる3つの性格です。
- マキャベリズム:ずる賢く人を操作する
- ナルシシズム:自分が一番すごいと思っている
- サイコパシー:他人の気持ちに鈍く、冷たい
これらの性格の人は、感情をあまり気にせず、他人を自分のために使おうとする傾向があります。
そのため、日常の中で「この人ちょっと怖いな」と感じる人が該当することもあります。
見た目や話し方ではわかりにくいですが、行動や言葉に表れることがあります。
つまり、悪者とは、人間関係でトラブルを起こしやすい性格の人を指すことが多いのです。
悪者とは、周囲の気持ちを考えず、自分の利益を優先する人のことをいいます。
EQ(共感力)ってどんな能力?
EQとは、他人の気持ちを理解してうまく関わる力のことです。
「共感力」とも呼ばれ、人間関係をよくするために欠かせない能力です。
たとえば友達が落ち込んでいるとき、「つらいんだね」と寄り添う力がEQです。
EQには2つの種類があります。
- 認知的共感:相手の気持ちを読み取る力
- 情動的共感:相手と同じような気持ちになる力
この2つがうまく働くことで、他人と良い関係を築けるのです。
逆にEQが低いと、空気が読めなかったり、人の話を聞かずに傷つけたりしてしまいます。
EQは生まれつきだけでなく、成長や経験で伸ばすこともできます。
EQは、人の気持ちを考えて行動するための、心の知能といえる力です。
なぜ「悪者のEQ」が注目されるの?
「悪者のEQ」は、他人との関係を左右するからです。
どれだけ頭がよくても、人の気持ちがわからなければ、信頼は得られません。
近年の研究では、悪者タイプの人でも、感情を読み取る力はあることがわかっています。
ですが、その感情に共感する力がとても低いのです。
つまり、
- 相手の気持ちはわかっている
- でも、その気持ちに寄り添わない
という状態です。
このような性格は、人間関係でトラブルを起こしやすくなります。
また、他人を利用するために、あえて感情を読み取る力を使うこともあります。
このようにして、悪者のEQは「ずる賢い共感力」とも言われるのです。
人の気持ちを読むのに、それを優しさに使わない人のEQが注目されています。
ダークトライアドとは何か?
ダークトライアドとは、3つの「悪い」性格特性のことです。
この言葉は心理学で使われており、次のような性格のことをいいます。
- マキャベリズム:人を操作するのがうまい
- ナルシシズム:自分が特別だと思っている
- サイコパシー:冷たく感情に無関心
これらの性格は、誰にでも少しはあるかもしれません。
でも、これが強く出る人は、他人とのトラブルが多くなります。
たとえば、
- 嘘をついて人をだます
- 自分だけ得をしようとする
- 人が困っていても無関心
などの行動が見られます。
見た目ではわからなくても、言動に出ることがあります。
ダークトライアドとは、人の気持ちより自分の利益を大事にする性格です。
心理学で使われる共感の2つの種類
共感には「読み取る力」と「感じる力」の2つがあります。
まず、相手の気持ちを「考えて理解する力」があります。
これは「認知的共感」と呼ばれます。
次に、相手と同じような気持ちになる力があります。
これを「情動的共感」といいます。
つまり、
- 認知的共感:気持ちを頭で理解する
- 情動的共感:気持ちを心で感じる
どちらも大切な力ですが、ダークトライアドの人は「感じる力」が弱いとされています。
相手の悲しみを理解しても、自分は何も感じないのです。
だから冷たく見えるのです。
共感には、頭で理解する力と心で感じる力の両方があるのです。
悪者のEQと性格特性の関係
マキャベリズムの特徴と共感力の低さ
マキャベリズムとは、人を利用して自分の利益を得ようとする性格です。
このタイプの人は、他人の感情にあまり関心がありません。
むしろ、感情を利用して相手をうまく動かそうとします。
特徴的な行動は以下の通りです。
- 嘘をついても平気
- 自分の損にならないかだけを考える
- 感情を表に出さない
共感力でいうと、相手の気持ちは理解できても、それに心を動かされることは少ないです。
だから、冷たく感じたり、思いやりがないと思われたりします。
感情を持たないのではなく、感情に左右されないのが特徴です。
マキャベリズムの人は、共感しても行動には出さない傾向があります。
ナルシシズムの意外な一面とは?
ナルシシズムとは、自分が特別だと思いこむ性格です。
このタイプの人は、自己中心的に見えますが、意外にも相手の感情には気づいています。
なぜなら、周囲からどう見られているかをとても気にしているからです。
つまり、
- 自分をよく見せるために相手を観察する
- 相手の反応に敏感
- 認知的共感は高いが、行動に結びつかない
このように、他人の気持ちを「読む力」はあります。認知的共感です。
ただし、それは相手に寄り添うためではなく、自分のイメージを守るためです。
情動的共感は弱く、相手のつらさを一緒に感じることは少ないです。
ナルシシズムの人は、自分を守るために共感を使うことがあります。
サイコパシーはどれくらい共感できない?
サイコパシーの特徴は、感情の薄さと衝動的な行動です。
このタイプの人は、他人の気持ちにほとんど関心を持ちません。
また、良心の痛みや罪悪感も感じにくいのが特徴です。
具体的には、
- 人を傷つけても平気
- 怒りや悲しみの表情を見ても無反応
- 共感がほとんどない
共感力のうち、認知的な理解も弱い傾向があります。
特に一次的サイコパシーと呼ばれるタイプは、冷静に見えるけれど他人の感情を感じません。
感情のない判断をするため、冷酷な印象を与えます。
サイコパシーの人は、共感そのものをほとんど持たない傾向があります。
誠実性が低いとどうなる?
誠実性が低い人は、ルールや約束を軽く考える傾向があります。
この特性は、まじめで責任感のある性格を指します。
これが低いと、行動がいい加減になったり、思いやりに欠けたりします。
たとえば、
- 約束を守らない
- 嘘をついても気にしない
- 自分の行動を正当化する
このような人は、他人の信頼を失いやすく、人間関係がうまくいかなくなります。
また、共感力も育ちにくいため、冷たいと感じられることがあります。
悪者タイプの人は、誠実性が全体的に低い傾向にあります。
誠実性の低さは、人間関係のトラブルを引き起こす原因になります。
情動性が低い人の行動パターン
情動性が低い人は、感情を表に出しにくく、人に共感しにくいです。
この特性は、感情を感じる力や、それに反応する力のことです。
情動性が低いと、感情に鈍く、他人の感情にも無関心になりがちです。
特徴的な行動は以下のようなものがあります。
- 冷静すぎて距離を感じる
- 人の気持ちを読み取るのが苦手
- 感情的な話を聞いても反応が薄い
このような人は、誤解されやすく、無関心に見られてしまうこともあります。
悪者のEQが低い理由のひとつに、この情動性の低さがあります。
情動性が低いと、人の気持ちを感じとることが難しくなります。
悪者のEQを測る心理テストとは?
自分の性格特性を測る方法
性格特性を知るには、質問に答えるテストが使われます。
心理学では、性格をいくつかの視点から評価します。
その中でも「ダークトライアド」に注目した質問があります。
このようなテストでは、日常の行動や考え方をたずねる質問が並びます。
たとえば、
- 自分の利益のために嘘をついたことがあるか
- 他人をだまして得をしたことがあるか
- 人の失敗を気にしないか
といった内容です。
点数が高いほど、ダークな性格の傾向が強いと考えられます。
これは「マキャベリズムテスト」「ナルシシズム診断」など名前もさまざまです。
自分の性格の傾向を知ることで、行動のクセを見直すきっかけになります。
共感力のチェック方法とは?
共感力を調べるテストでは、気持ちへの反応を見る質問が使われます。
このテストは、相手の感情をどれだけ理解できるかを見るものです。
たとえば以下のような質問があります。
- 人が悲しんでいると、自分も悲しくなるか
- 相手の気持ちをすぐに察知できるか
- 人の気持ちに振り回されることがあるか
このような問いに対し、自分の感じ方に近い選択肢を選びます。
点数が高いほど、共感力が高いとされます。
情動的共感と認知的共感に分かれて結果が出るものもあります。
自分の強みや弱みを知るのに役立ちます。
共感力のテストは、自分の心の動きを知る大切な手がかりになります。
顔写真を見て何がわかる?
人の表情を見ることで、共感の感じ方が測れます。
ある研究では、いろいろな表情の顔写真を見て感情を答える方法が使われました。
参加者は、怒り・悲しみ・喜び・恐れなどの写真を見て、
- どう感じたか(快か不快か)
- その表情はどんな感情か
を判断します。
この方法で、相手の表情に対する「反応」と「理解」が両方チェックできます。
たとえば、
- 悲しい顔を見て楽しいと感じたら、共感のズレがある
- 怒った顔を見てすぐに怒りと答えられる人は理解力が高い
という具合です。
顔の表情に対する反応は、共感力を客観的に見る手がかりになります。
感情を読み取る力とEQの関係
感情を読み取る力は、EQの中でも大事な要素です。
これは「認知的共感」と呼ばれ、相手の気持ちを頭で理解する力です。
この力があると、相手が何を考えているかを読み取りやすくなります。
たとえば、
- 相手の声のトーンや表情から気持ちを感じ取る
- 相手が言葉にしなくても状況から読み取る
といった行動ができます。
しかし、感情を読み取れても「寄り添う気持ち」がなければ意味がありません。
ダークな性格の人は、読み取る力はあっても、行動が伴わないことが多いのです。
感情を読む力と感じる力の両方がそろってこそ、本当のEQといえます。
テストで見えてくる心のクセ
心理テストを通じて、自分の心のクセが明らかになります。
人は、自分では気づいていない反応や思い込みを持っていることがあります。
テストの質問に答えることで、
- どんなときに感情的になるか
- どういう場面で冷たくなりやすいか
- 相手を無意識にコントロールしていないか
といった心の傾向が見えてきます。
また、テストの結果は変化することもあります。
環境や経験によって、感じ方や行動は少しずつ変わるからです。
だから、1回の結果で決めつけるのではなく、自分を知る材料として使うのが大切です。
心理テストは、自分の心の動きを客観的に見るための「鏡」のような存在です。
悪者のEQが低いとどうなる?
悪者のEQ:他人の気持ちが気にならない人の心理
他人の気持ちが気にならない人は、感情より自分の利益を優先します。
そのような人は、冷たく見えることがあります。
なぜなら、感情に流されず、損得を重視するからです。
たとえば、
- 人が困っていても助けようとしない
- 相手の感情に気づいても何もしない
- 自分の思い通りにしたがる
このような人は、他人と深く関わるのが苦手です。
また、相手の立場に立って考えることが少なくなります。
結果として、人間関係のトラブルが増えることがあります。
他人の気持ちを無視することは、信頼やつながりを壊す原因になります。
悪者のEQ:冷たい態度の裏側にあるもの
冷たい態度の背後には、共感の不足が隠れていることがあります。
一見すると、強くてしっかりした人に見えるかもしれません。
しかし実際は、感情に関心がないか、関心を持てないことがあります。
主な理由は以下の通りです。
- 感情を表すのが苦手
- 感情に興味がない
- 相手の感情に価値を感じない
このような態度が続くと、周囲との心の距離がどんどん広がります。
「どうしてわかってくれないの?」と誤解されやすくなります。
特に情動的共感が低い人に多く見られる特徴です。
冷たい態度の奥には、感情に鈍い心のしくみがある場合があります。
悪者のEQ:操作的な人が人間関係でやりがちなこと
操作的な人は、人をコントロールすることで関係を築こうとします。
その行動は一見すると親切に見えることもあります。
しかし、本当の目的は自分の利益です。
たとえば、
- わざと同情をひくようなことを言う
- 相手の弱点を見つけて利用する
- ほめたり怒ったりして相手を動かす
こうした行動の背後には、相手の感情への無関心があります。
共感せずにただ結果を求めるため、相手を疲れさせることがあります。
人間関係が一時的にはうまくいっても、信頼は長続きしません。
人を動かすために感情を使うと、関係が不安定になります。
悪者のEQ:感情のズレが引き起こすトラブル
共感のずれがあると、人間関係に誤解が生まれやすくなります。
相手が悲しんでいるのに笑ってしまう。
怒っているのに気づかずに話を続ける。
こうした行動は、感情をうまく読み取れないことが原因です。
とくに以下の場面で問題が起こりやすくなります。
- グループでのやりとり
- 家族との会話
- 恋人や友達との関係
感情のズレが積み重なると、「この人には何を言っても伝わらない」と思われてしまいます。
それが孤立やケンカにつながることもあります。
共感のズレは、小さなすれ違いから大きな問題へ発展することがあります。
恋愛や友達関係に与える影響
EQが低いと、恋愛や友情にも悪い影響を与えます。
感情を理解できなかったり、気づいても無視してしまうと、相手は傷つきます。
以下のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 相手の気持ちを軽く見てしまう
- すれ違いが多くなる
- ケンカが増える
また、「どうして気づいてくれないの?」と不満を持たれがちです。
EQが低い人は、悪気がなくても無関心に見えることがあります。
それが相手にとっては冷たく感じるのです。
だからこそ、少しでも気持ちに寄り添う努力が大切です。
恋愛や友情では、思いやりが心のつながりを強くします。
悪者のEQは高くなるのか?
共感力は後から身につけられる?
共感力は生まれつきだけでなく、あとから伸ばすこともできます。
最初は苦手でも、少しずつ練習すれば変わることがあります。
共感力は筋肉と同じで、使えば育つのです。
主な方法は以下のとおりです。
- 他人の気持ちを想像する練習をする
- 感情を言葉にしてみる
- 困っている人に声をかけてみる
最初はうまくできなくても大丈夫です。
大切なのは、少しでも他人に関心をもつことです。
関係が深まるほど、共感の力は自然と育ちます。
共感力は、努力と経験によって育てることができる力です。
まずは相手の気持ちに気づくことから
共感力を高めるには、まず「気づく力」が大切です。
多くの人は、相手の気持ちに「気づかない」だけで、冷たいわけではありません。
気づくためには、次のことを意識しましょう。
- 相手の表情や声のトーンに注意する
- 「今、どんな気持ちかな?」と考える
- 会話の中で感情の言葉を拾う
小さな変化にも目を向けることで、感情への理解が深まります。
気づくことができれば、行動にもつながります。
その一歩が、共感への第一歩です。
共感は、相手の感情に気づくところから始まります。
自分の感情に気づくトレーニング
自分の感情を知ることで、他人への共感力も高まります。
まず自分の気持ちに鈍いと、他人の気持ちもわかりにくくなります。
感情に気づく練習として、次の方法があります。
- 毎日「今日はどんな気持ちだったか」書き出す
- 嬉しかったことや、イライラした理由を振り返る
- 感情に名前をつけてみる
このトレーニングを続けると、心の動きに敏感になります。
その結果、人の感情にも自然と目が向くようになります。
自分の心に目を向けることが、共感力アップの近道です。
日常生活でできるEQアップの習慣
EQは、毎日の小さな行動で高めることができます。
特別な勉強や訓練がなくても、心がけ次第で育てられます。
次のような習慣を取り入れてみましょう。
- あいさつを丁寧にする
- 話を最後まで聞く
- 相手の立場になって考える
- 「ありがとう」や「ごめんね」を言葉にする
このような行動を続けると、自然と相手を思いやる気持ちが育ちます。
EQは特別な人だけのものではありません。
日々の積み重ねで、誰でも身につけられる力です。
共感力は、日常の中で育つ「こころの筋トレ」です。
心のクセを変えるために大事なこと
共感力を高めるには、自分の「心のクセ」に気づくことが必要です。
人は無意識に、同じ考え方や反応をくり返してしまいます。
たとえば、
- すぐに相手を責めてしまう
- 自分の考えが正しいと思いがち
- 他人の感情を軽く見てしまう
こうしたクセに気づけば、少しずつ変えることができます。
大切なのは、自分を責めるのではなく、見つめ直すことです。
気づいたら「次はこうしてみよう」と思うことが成長につながります。
心のクセに気づき、自分を見つめることが共感力を育てる第一歩です。
最後に
今回の記事では、「悪者のEQ」と呼ばれる人たちの共感力について紹介しました。ダークトライアドといわれるマキャベリズム、ナルシシズム、サイコパシーという性格の持ち主たちは、他人の感情を理解する力はあるけれど、それに心を動かされにくいという特徴があることがわかりました。
つまり、「気持ちは読めるけど、寄り添わない」人たちです。でも、共感力は生まれつきだけでなく、あとから伸ばすこともできます。
大切なのは、自分の心のクセに気づいて、少しずつ相手の気持ちを考えること。友達や家族との関係を大切にしたいなら、共感する力を育てていくことがとても大事です。
EQは特別な人だけのものではなく、毎日の行動の中で育っていくものです。あなたの中の共感力、今日から少しずつ育てていきましょう。
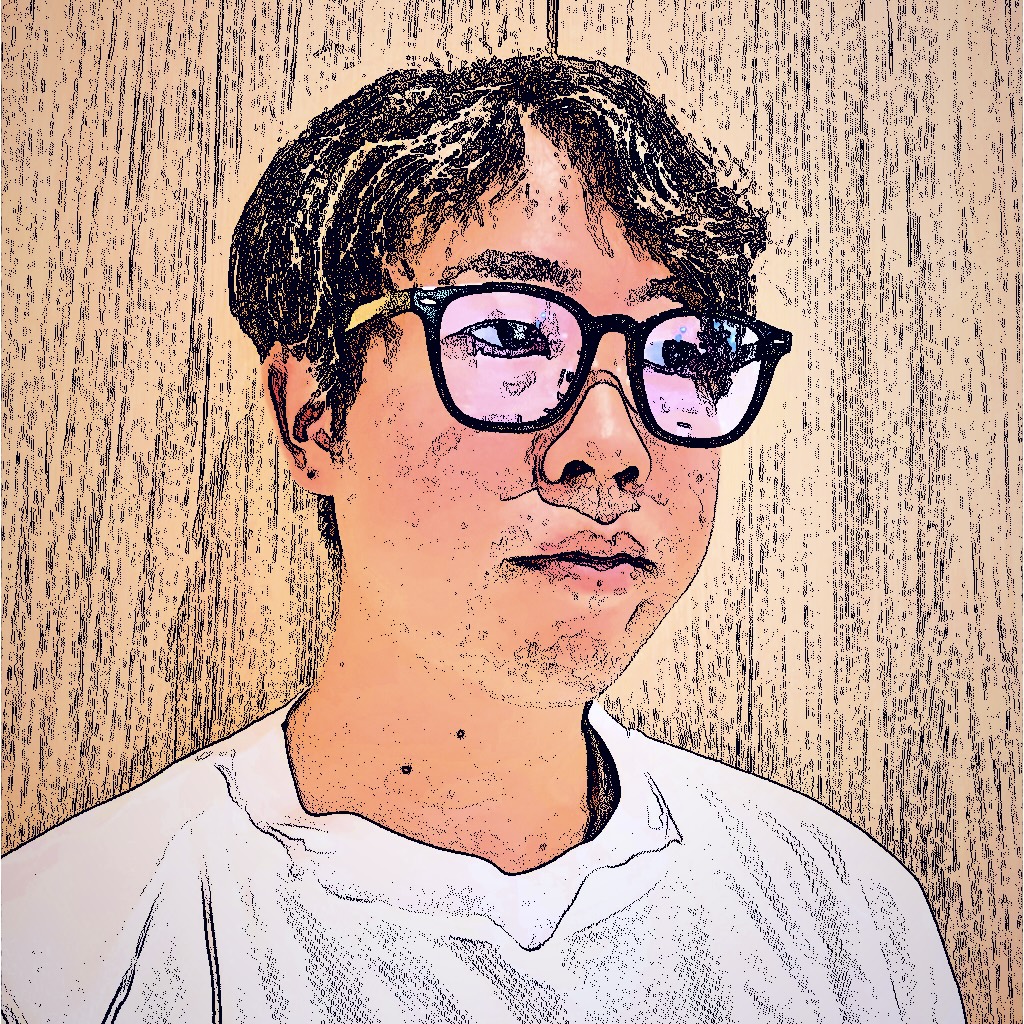
ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。