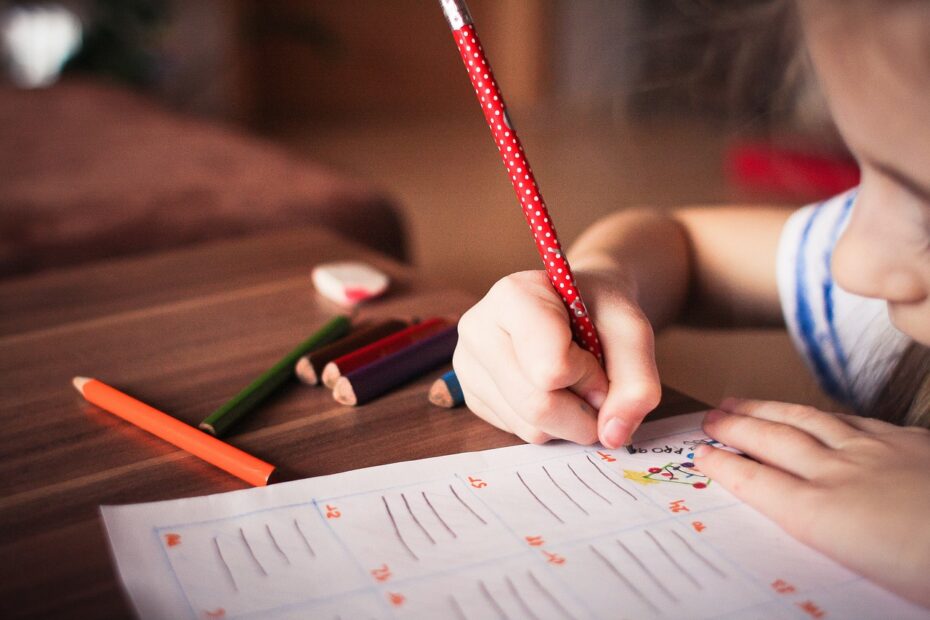学力と性格は関係があるのでしょうか?
私たちは、誰しも自分の性格を知っていますし、学力についても気になるところです。
もし性格が学力に影響するのなら、性格を知ることで、自分の学力を高められるヒントが得られるかもしれません。
実は、心理学者たちはこの問題に長い間取り組んできました。
しかし、一つ一つの研究では、結果にばらつきがあり、なかなか明確な答えが得られませんでした。そこで、最近ある研究者たちが、今までの研究を総合的に分析する「メタ分析」という方法を使って、この問題に取り組みました。
その研究のタイトルは「A Meta-Analysis of the Five-Factor Model of Personality and Academic Performance」です。
この研究は、性格と学力の関係について、重要な発見をしたのです。
では、具体的にはどのようなことがわかったのでしょうか?もう少し詳しく見ていきましょう。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
学力と性格の関係:大規模メタ分析が明らかにしたこと
メタ分析とは?
メタ分析とは、複数の研究結果を統合し、全体としての傾向を明らかにする手法です。
個々の研究では、サンプルの特性や調査方法の違いから、結果にばらつきがあることがあります。
そこで、メタ分析では、以下のような手順で研究結果を統合します。
- 研究テーマに関連する先行研究を網羅的に収集
- 各研究の結果を定量的に評価(効果量の算出)
- 効果量を統計的に統合し、全体としての傾向を推定
- 研究間の結果の違いを生む要因を探索
このように、メタ分析は個別の研究結果を統合することで、より信頼性の高い知見を得ることができます。
今回のメタ分析では、学力と性格の関係について、大規模なデータを用いて包括的に検討しました。
その結果、全体としての傾向が明らかになり、教育現場に役立つ示唆が得られました。
分析の対象:7万人以上の学生の学力と性格のデータ
この研究では、就学前から大学までの学生、合計7万人以上のデータを分析しました。
具体的な内訳は以下の通りです。
- 就学前児童
- 小学生
- 中学生
- 高校生
- 大学生
このように幅広い年齢層を対象とすることで、学力と性格の関係が、発達段階によってどのように変化するのかを検討することができました。
また、サンプルサイズが非常に大きいことから、得られた結果の信頼性は高いと言えます。
一般的に、サンプルサイズが大きいほど、結果がより安定し、母集団の特性を正確に反映すると考えられているためです。
今回のメタ分析では、これまでの研究の中でも最大規模のデータを用いており、結果の信頼性は非常に高いと評価できるでしょう。
学力と性格:関連があった性格特性とは?
分析の結果、ビッグファイブの誠実性、協調性、開放性が学力と有意な正の相関を示しました。
つまり、これらの特性が高い学生ほど、学力も高い傾向があったということです。
それぞれの特性の意味は以下の通りです。
- 誠実性:規律正しく、責任感が強い
- 協調性:他者と良好な関係を築き、協力的である
- 開放性:知的好奇心が高く、新しいアイデアに寛容である
一方で、外向性と情緒安定性は学力とあまり関連がありませんでした。
外向性の高さや、情緒の安定度合いは、学力にはあまり影響しないようです。
これらの結果から、学力向上のためには、特に誠実性、協調性、開放性を育むことが重要だと示唆されました。
ただし、学力と性格の関係は、年齢や教育段階によって変化することも明らかになりました。
誠実性が学力に与える影響
誠実性は、学力に最も強い影響を与える性格特性であることが明らかになりました。
この特性が高い学生は、以下のような特徴があります。
- 計画的で、粘り強く物事に取り組む
- 時間を有効に使い、効率的に学習する
- 規則正しい生活習慣を維持する
このような特徴が、学力の向上につながっていると考えられます。
実際、誠実性の高い学生は、そうでない学生に比べて、宿題や課題に熱心に取り組み、良い成績を収める傾向があることが報告されています。
さらに興味深いのは、誠実性と学力の関連の強さは、知能の影響を考慮しても変わらなかったという点です。
つまり、誠実性の高さは、知能とは独立して学力に影響を与えているのです。
誠実性を育むことは、学力向上のための重要な鍵となるでしょう。
協調性と学力の関係
協調性も、学力と正の相関を示す性格特性の一つです。
この特性が高い学生は、以下のような特徴があります。
- 他者と良好な関係を築き、協力的である
- 先生の指示に従い、授業に積極的に参加する
- グループ学習などでは、他者と協力して課題に取り組む
このような特徴が、学習に良い影響を与えていると考えられます。
協調性の高い学生は、学校生活に適応しやすく、学習に集中しやすい環境を作ることができるのです。
また、協調性は社会的スキルとも関連が深いため、将来の社会生活でも重要な役割を果たすでしょう。
ただし、協調性と学力の関連の強さは、誠実性ほど大きくはありませんでした。
協調性は学力に影響を与えるものの、その影響力は誠実性に比べると限定的であると言えます。
それでも、協調性を育むことは、学力向上と社会性の発達の両面で意味があるでしょう。
開放性が学力に及ぼす影響
開放性は、学力と正の相関を示す3つ目の性格特性です。
この特性が高い学生は、以下のような特徴があります。
- 知的好奇心が高く、新しいことを学ぶことに積極的である
- 創造的で、独自のアイデアを生み出すことができる
- 様々な視点から物事を捉えることができる
このような特徴が、学習への動機づけを高め、学力向上につながっていると考えられます。
開放性の高い学生は、新しい知識を吸収することに喜びを感じ、自ら進んで学習に取り組むことができるのです。
また、複雑な問題に対しても、柔軟な思考で対応することができるでしょう。
ただし、開放性と学力の関連は、知能の影響を受けることが明らかになりました。
つまり、開放性の高さは、知能の高さとある程度関連しており、学力に対する独自の影響力は限定的であると言えます。
とはいえ、開放性を育むことは、知的好奇心を刺激し、生涯学び続ける姿勢を培うことにつながるでしょう。
外向性と情緒安定性は学力とあまり関係がない?
外向性と情緒安定性は、学力とはあまり関連がないことが示されました。
この特性の特徴は以下の通りです。
- 社交的で、積極的に他者と関わる
- 活発で、エネルギッシュである
- 自己主張が強い
一方、情緒安定性の特徴は以下の通りです。
- ストレスに強く、情緒的に安定している
- 落ち着いていて、冷静に物事に対処できる
- 不安やネガティブな感情に左右されにくい
これらの特性は、学習場面では重要な役割を果たさないようです。
外向的であるか内向的であるか、情緒的に安定しているかどうかは、学力にはあまり影響しないということです。
ただし、外向性や情緒安定性が高いことは、学校生活を円滑に送る上では有利に働くかもしれません。
例えば、外向的な学生は、グループ学習などでリーダーシップを発揮しやすいでしょう。
また、情緒安定性の高い学生は、試験のストレスにも動じずに対処できるかもしれません。
性格と知能、どちらが学力により強く影響する?
性格と知能は、どちらも学力に影響を与える重要な要因です。
ただし、その影響力の大きさは、性格特性によって異なることが明らかになりました。
特に注目すべきは、以下の点です。
- 誠実性は、知能と同程度の影響力を持つ
- 開放性の影響力は、知能の影響を受ける
- 協調性、外向性、情緒安定性の影響力は限定的である
つまり、学力を予測する上では、知能と並んで、特に誠実性が重要な役割を果たすと言えるでしょう。
誠実性の高さは、知能の高さと同じくらい、学業成績の向上に寄与するのです。
一方、開放性の影響は、知能の影響を考慮すると、それほど大きくないことが示唆されました。
また、協調性、外向性、情緒安定性は、学力に対する直接的な影響力は小さいようです。
ただし、これらの特性は、学習態度や学校生活の適応などを通じて、間接的に学力に影響を与えている可能性があります。
誠実性の影響は知能を考慮しても変わらない
誠実性と学力の関連の強さは、知能の影響を統制しても変わらないことが明らかになりました。
つまり、誠実性の高さは、知能とは独立して学力に影響を与えているのです。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 誠実性は、学力を予測する上で、知能と並ぶ重要な要因である
- 誠実性を高めることは、知能の高低に関わらず、学力向上に役立つ
- 学力向上のためには、知能だけでなく、誠実性も重視する必要がある
誠実性の高い学生は、知能の高低に関わらず、以下のような行動特性を示すと考えられます。
- 計画的で、粘り強く学習に取り組む
- 宿題や課題に真面目に取り組む
- 時間を有効に活用し、効率的に学習する
これらの行動特性が、学力の向上につながっているのでしょう。
つまり、誠実性を高めることは、知能の高低に関わらず、全ての学生の学力向上に役立つと期待できます。
学力向上のためには、知能の育成と並行して、誠実性を育むための教育的介入が重要だと言えるでしょう。
開放性と学力の関係は知能の影響を受ける
開放性と学力の関連は、知能の影響を受けることが明らかになりました。
つまり、開放性の高い学生は知能も高い傾向があり、学力に対する開放性の独自の影響力は限定的だということです。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 開放性の高さは、知能の高さと関連している
- 開放性が学力に与える影響の一部は、知能の影響によるものである
- 開放性を高めることは、知能の発達を促す可能性がある
開放性の高い学生は、以下のような特徴を示すと考えられます。
- 知的好奇心が高く、新しいアイデアに興味を持つ
- 創造的で、独自の視点を持っている
- 美的感性が高く、芸術的な活動を好む
これらの特徴は、知的な活動への関与を促し、知能の発達を助ける可能性があります。
ただし、開放性の高さが直接的に学力を向上させるわけではないようです。
むしろ、開放性を高めることで、知的好奇心を刺激し、知能の発達を促すことが期待できるでしょう。
そうすることで、間接的に学力の向上につながる可能性があります。
高校の成績を考慮しても、大学の成績に誠実性は影響する
高校時代の成績を統制しても、誠実性は大学の成績に影響を与えることが明らかになりました。
つまり、高校時代の成績が同じ学生を比べた場合、誠実性の高い学生の方が、大学でも良い成績を収める傾向があるということです。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 誠実性は、高校から大学へと継続して学業成績に影響を与える
- 高校時代の成績だけでなく、誠実性も大学の成績を予測する重要な要因である
- 大学入学後も、誠実性を高めることが学業成績の向上につながる
高校時代の成績は、大学入学時点での学力を反映していると考えられます。
しかし、大学での学びは高校とは異なり、より自律的で主体的な学習が求められます。
そのような環境では、誠実性の高さが学業成績に与える影響が大きくなるのかもしれません。
誠実性の高い学生は、以下のような行動特性を示すと考えられます。
- 自ら進んで学習に取り組み、学習時間を確保する
- 課題や宿題に真面目に取り組み、提出期限を守る
- 講義に出席し、積極的に質問やディスカッションに参加する
このような行動特性が、大学での学業成績の向上につながっているのでしょう。
大学入学後も、誠実性を高め、主体的な学習態度を維持することが、学業成功の鍵となるはずです。
学力と性格の関係:教育段階や年齢で変化する
小学校から大学にかけて、学力と性格の関係が変わる
学力と性格の関係は、小学校から大学にかけて変化することが明らかになりました。
特に、以下のような変化が見られました。
- 誠実性と学力の関連は、一貫して強い
- 協調性、開放性、外向性、情緒安定性と学力の関連は、教育段階が上がるにつれて弱まる
これらの変化は、以下のような要因によって説明できるかもしれません。
- 教育段階が上がるにつれて、学習内容が高度になり、個人の自律性がより重要になる
- 高校や大学では、学習スタイルや興味・関心に基づいて科目を選択できるようになる
- 社会性やコミュニケーション能力の重要性は、年齢とともに変化する
つまり、教育段階が上がるにつれて、学習に対する個人の主体性や自律性がより重要になるのです。
そのような環境では、誠実性の重要性が相対的に高まり、他の特性の影響力が低下するのかもしれません。
ただし、これらの変化は連続的なものであり、一つの教育段階だけに当てはまるわけではありません。
学力と性格の関係を理解するためには、発達の連続性を考慮することが重要です。
学力と性格:誠実性以外は教育段階が上がると弱まる
教育段階が上がるにつれて、誠実性以外は弱まる傾向があることが明らかになりました。
具体的には、以下のような変化が見られました。
- 協調性と学力の関連は、小学校から中学・高校にかけて弱まる
- 開放性と学力の関連は、小学校から中学・高校、大学にかけて弱まる
- 外向性と学力の関連は、小学校から中学・高校にかけて弱まる
- 情緒安定性と学力の関連は、小学校から中学・高校にかけて弱まる
これらの変化は、以下のような要因によって説明できるかもしれません。
- 教育段階が上がるにつれて、学習内容が高度になり、個人の努力や能力がより重要になる
- 高校や大学では、個人の興味・関心に基づいて科目を選択できるようになる
- 社会性やコミュニケーション能力の重要性は、年齢とともに変化する
教育段階が上がるにつれて、学習に対する個人の主体性や自律性がより重要になります。
そのような環境では、誠実性の重要性が相対的に高まり、他の特性の影響力が低下するのかもしれません。
ただし、これらの特性が学力に与える影響が弱まるからといって、それらの特性が重要でないというわけではありません。
むしろ、学力以外の側面、例えば社会性や精神的健康などに対して、重要な役割を果たしている可能性があります。
年齢とともに、協調性、情緒安定性、開放性と学力の関係は弱まる
協調性、情緒安定性、開放性と学力の関連は、年齢とともに弱まる傾向があることが明らかになりました。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 協調性、情緒安定性、開放性が学力に与える影響は、年齢によって異なる
- 年齢が上がるにつれて、これらの特性の学力に対する影響力は低下する
- 年齢に応じて、学力に影響を与える要因が変化する可能性がある
ただし、年齢による変化の背景には、以下のような要因があるかもしれません。
- 教育段階の変化(小学校から中学・高校、大学へ)
- 認知能力や社会性の発達
- 学習内容や学習環境の変化
例えば、小学校では協調性が高いことが学習に良い影響を与えるかもしれません。
しかし、大学では個人の自律性がより重要になるため、協調性の影響力が低下するのかもしれません。
同様に、情緒安定性や開放性の影響力も、年齢とともに変化する可能性があります。
ただし、これらの特性が重要でなくなるわけではありません。
学力以外の側面、例えば精神的健康や創造性などに対して、重要な役割を果たしている可能性があります。
小学生では、年齢とともに誠実性、情緒安定性、外向性の影響が強まる
小学生を対象とした分析では、年齢とともに誠実性、情緒安定性、外向性と学力の関連が強まることが明らかになりました。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 小学生では、誠実性、情緒安定性、外向性が学力に与える影響が、年齢とともに大きくなる
- これらの特性を高めることが、小学生の学力向上に役立つ可能性がある
- 小学校教育では、これらの特性の育成にも注目する必要がある
年齢による変化の背景には、以下のような要因があるかもしれません。
- 自己制御能力や自己調整学習能力の発達
- 社会性やコミュニケーション能力の発達
- 学習内容や学習環境の変化
例えば、誠実性の高さは、宿題への取り組みや時間管理능力と関連しています。
年齢とともにこれらの能力が発達することで、誠実性と学力の関連が強まるのかもしれません。
同様に、情緒安定性の高さは、ストレス対処能力と関連しており、年齢とともにその重要性が高まるのかもしれません。
外向性については、コミュニケーション能力や社会性の発達と関連している可能性があります。
小学校教育では、これらの特性を育成することが、学力向上につながる可能性があります。
小学生では、年齢とともに開放性の影響は弱まる
小学生を対象とした分析では、年齢とともに開放性と学力の関連が弱まることが明らかになりました。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 小学生では、開放性が学力に与える影響が、年齢とともに小さくなる
- 年齢が上がるにつれて、開放性以外の要因が学力により強く影響するようになる
- 小学校教育では、開放性の育成よりも、他の要因により注目する必要がある
年齢による変化の背景には、以下のような要因があるかもしれません。
- 学習内容や学習環境の変化
- 興味・関心の多様化
- 認知能力の発達
例えば、低学年では、新しいことに興味を持つ開放性の高さが、学習への動機づけにつながるかもしれません。
しかし、高学年になるにつれて、学習内容が高度になり、個人の努力や能力がより重要になります。
そのため、開放性の影響力が相対的に低下するのかもしれません。
また、年齢とともに興味・関心が多様化することで、開放性の影響力が分散する可能性もあります。
ただし、開放性が重要でなくなるわけではありません。
知的好奇心や創造性の育成には、開放性が重要な役割を果たすと考えられます。
中学生・高校生では、年齢とともに協調性、情緒安定性、開放性の影響が弱まる
中学生・高校生を対象とした分析では、年齢とともに協調性、情緒安定性、開放性と学力の関連が弱まることが明らかになりました。
この結果は、以下のような示唆を与えてくれます。
- 中学生・高校生では、協調性、情緒安定性、開放性が学力に与える影響が、年齢とともに小さくなる
- 年齢が上がるにつれて、これらの特性以外の要因が学力により強く影響するようになる
- 中学・高校教育では、これらの特性の育成よりも、他の要因により注目する必要がある
年齢による変化の背景には、以下のような要因があるかもしれません。
- 学習内容や学習環境の変化
- 個人の自律性や主体性の重要性の高まり
- 進路選択や将来設計の重要性の高まり
例えば、中学・高校では、学習内容が高度になり、個人の努力や能力がより重要になります。
そのため、協調性や情緒安定性、開放性の影響力が相対的に低下するのかもしれません。
また、進路選択や将来設計が重要になるため、個人の興味・関心や能力に基づいた選択が行われるようになります。
そのような状況では、これらの特性の影響力が低下する可能性があります。
ただし、これらの特性が重要でなくなるわけではありません。
社会性やコミュニケーション能力、ストレス対処能力、創造性などには、これらの特性が重要な役割を果たすと考えられます。
学力と性格の関係:職場での成績との類似点
学力と職務パフォーマンスに対する性格の影響の類似性
学力と性格の関連は、職務パフォーマンスと性格の関連と類似していることが明らかになりました。
特に、以下のような類似点が見られました。
- 誠実性が、学力と職務パフォーマンスの両方に最も強い影響を与える
- 協調性、情緒安定性、開放性、外向性の影響力は、学力と職務パフォーマンスで同程度である
- 性格の影響力は、状況や環境によって異なる
これらの類似点は、以下のような要因によって説明できるかもしれません。
- 学力と職務パフォーマンスに共通する要素(例:目標達成、自己管理、対人関係)の存在
- 性格が行動パターンに与える影響の一般性
- 状況や環境が性格の発現に与える影響の共通性
例えば、誠実性の高さは、目標達成や自己管理に役立つと考えられます。
これらの要素は、学業場面でも職務場面でも重要であるため、誠実性の影響力が両方で高くなるのかもしれません。
また、性格は行動パターンに影響を与えますが、その影響は状況や環境によって異なります。
学業場面と職務場面では、求められる行動や役割が異なるため、性格の影響力も状況によって変化すると考えられます。
ただし、学力と職務パフォーマンスは同一ではありません。
両者の関連を理解するためには、状況や環境の違いを考慮することが重要です。
教育段階が上がるほど、学力と職務パフォーマンスへの性格の影響が似てくる
教育段階が上がるにつれて、学力と性格の関連が、職務パフォーマンスと性格の関連に近づくことが明らかになりました。
特に、以下のような変化が見られました。
- 小学校から中学・高校、大学へと進むにつれて、学力と職務パフォーマンスへの性格の影響の類似性が高まる
- 高校や大学では、学力と職務パフォーマンスに対する誠実性の影響力が同程度に強い
- 高校や大学では、学力と職務パフォーマンスに対する他の特性の影響力が同程度に弱い
これらの変化は、以下のような要因によって説明できるかもしれません。
- 教育段階が上がるにつれて、学習内容や学習環境が職務環境に近づく
- 高校や大学では、個人の自律性や主体性がより重要になる
- 高校や大学では、将来のキャリアを見据えた学習が行われる
例えば、小学校では学習内容が基礎的であり、教師の指導に従うことが重要です。
一方、大学では専門的な知識やスキルを自ら学ぶことが求められ、自律性や主体性が重要になります。
このような学習環境の変化が、性格の影響力の変化につながっているのかもしれません。
また、高校や大学では、将来のキャリアを見据えた学習が行われます。
このため、職務場面で重要となる要素(例:目標達成、自己管理、対人関係)がより重視されるようになります。
その結果、学力と職務パフォーマンスに対する性格の影響が似てくるのかもしれません。
今後の研究の方向性:より詳細な性格特性の検討と交互作用効果の探索
今回のメタ分析では、性格と学力の関係について、重要な知見が得られました。
しかし、今後のさらなる研究が必要な点も明らかになりました。
特に、以下のような研究の方向性が考えられます。
- より詳細な性格特性と学力の関連の検討
- 性格特性間の交互作用効果の探索
- 状況や環境と性格の交互作用効果の検討
まず、今回の分析では、性格をビッグファイブでとらえました。
しかし、各特性にはさらに詳細な下位特性が存在します。
例えば、誠実性には、慎重さなどの下位特性が含まれます。
次に、性格特性間の交互作用効果も重要な研究テーマです。
例えば、誠実性と知性の高さが組み合わさることで、学力に相乗効果が生じる可能性があります。
このような交互作用効果を検討することで、状況に応じた性格の影響力の変化を理解できるでしょう。
学力と性格の関係は複雑であり、さらなる研究が必要です。
しかし、今回のメタ分析で得られた知見は、今後の研究の方向性を示す重要な基盤となるはずです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。