結婚の遺伝って本当にあるのでしょうか?「生まれつき結婚しやすい人がいる」と聞くと、ちょっと不思議に感じるかもしれません。
けれど、実際に科学の世界では、こうしたテーマが真面目に研究されています。
今回は、海外の研究「Marriage and Divorce: A Genetic Perspective」をもとに、結婚や離婚がどれくらい遺伝に関係しているのかを、やさしく解説していきます。
「性格の違いが結婚に影響する?」「育った家庭よりも自分の気質が大事?」など、イメージしやすい話題をたくさん紹介します。
この記事を読めば、自分自身のことや周りの人の関係にも、新しい見方が生まれるかもしれません。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

結婚の遺伝は本当にあるのか?
双子研究からわかったこととは?
結婚するかどうかに遺伝が関係していることが明らかになりました。
この研究では、ベトナム戦争に参加した男性双子を対象にしました。
約6300組の双子を調べることで、遺伝と環境の影響を見ました。
その結果、結婚するかどうかは遺伝の力が強いとわかりました。
主なポイントは次のとおりです。
- 一卵性双子の結婚傾向がよく似ていた
- 二卵性双子よりも一卵性双子の方が一致率が高かった
- 環境よりも遺伝の影響が大きかった
つまり、家庭の育ちよりも、生まれつきの気質が影響していたのです。
このような研究方法を「行動遺伝学」といいます。
これは性格や行動が遺伝か環境かを調べる学問です。
双子研究はその代表的な方法として使われます。
この研究から、結婚は「個人の持つ特性」によって左右されることがわかりました。
つまり、結婚は偶然ではなく、ある程度生まれつき決まっているともいえます。
結婚する可能性に遺伝はどのくらい影響する?
結婚に対する遺伝の影響はおよそ58パーセントです。
これは「遺伝率」と呼ばれる数字で表されます。
研究では、双子の似ている割合からこの値を計算しました。
この数字は思ったよりも高く、多くの人にとって意外かもしれません。
一方で、残りの42パーセントは環境の影響です。
ここでいう環境とは、
- 育った家庭
- 学校や友人関係
- 社会的な経験
などが含まれます。
ただし、家族で共有する環境の影響は少なかったです。
つまり、兄弟で同じ家に育っても、結婚に影響はあまりありません。
このように、結婚においては生まれつきの力が大きく働いています。
性格や行動のクセが関係していると考えられます。
この結果から、結婚しやすいかどうかは、かなり個人差があるといえます。
遺伝と環境はどちらが強く働いている?
結婚のきっかけには遺伝が強く関係しています。
研究では、複数のモデルを使って分析されました。
その中で最も合っていたのが「遺伝と個人環境」のモデルです。
つまり、家族や兄弟と共有する環境よりも、自分だけの体験が影響していたのです。
この結果から、次のことがいえます。
- 結婚は兄弟でも違いが出る
- たとえ同じ家で育っても結婚傾向は同じにならない
- 自分らしさや考え方が大きく関係している
もちろん、すべてが遺伝で決まるわけではありません。
環境も約4割は影響しているため、無視はできません。
しかし、今回の研究では遺伝の力がより強いという結果でした。
人との出会いや恋愛の仕方も、生まれつきの特性に左右されるのかもしれません。
このように、結婚は「育ち」より「生まれ」が大きいことが示されました。
結婚のしやすさに関わる個人の違い
結婚しやすい人には特定の特徴がある可能性があります。
この研究では性格検査をしていませんが、他の研究からヒントが得られます。
たとえば、誠実性や社交性が高い人は結婚しやすいといわれています。
また、人と信頼関係を築くのが得意な人も有利です。
反対に、人づきあいが苦手な人は結婚のチャンスが減ることがあります。
このような特徴は、もともとの性格や行動パターンに関係しています。
そして、性格はある程度遺伝によって決まっていることが多いです。
つまり、恋愛や結婚も生まれ持った傾向が影響するということです。
ただし、すべてが決まっているわけではなく、努力や経験で変わる部分もあります。
この研究では性格の話は深く扱っていませんが、個人差の存在を示しています。
そのため、結婚の遺伝には個人の特性が大きく関係するといえるでしょう。
家庭環境よりも重要な要因とは?
兄弟で同じ家庭に育っても結婚傾向は似ませんでした。
これは少し意外に思えるかもしれません。
けれども、双子研究ではそれがはっきりと示されています。
たとえば、次のような点が明らかになりました。
- 兄弟の教育水準が似ていても結婚率は違う
- 家族の価値観が同じでも結婚年齢は異なる
- 親の影響よりも個人の考えが強く働く
このように、同じ家に育ったとしても結婚には違いが出ます。
つまり、家庭環境よりも「その人自身の特性」が重要なのです。
人との関係をどう築くか、何を大切にするかなどが関係します。
これはすべて、生まれつきの傾向やその後の経験に基づいています。
この研究では、共通環境よりも個人の要因が大きいことがわかりました。
結婚に関する意思や行動は、自分の中にある力によって動いているのです。
結婚の遺伝と離婚の関係はあるのか?
離婚にも遺伝が影響しているの?
離婚するかどうかにも遺伝の力があるとわかっています。
双子を使った研究では、離婚のしやすさにも個人差が見られました。
そしてその差は、生まれつきの影響が大きいことが示されています。
具体的には、離婚に対する遺伝の影響は約32パーセントでした。
残りは主にその人だけの経験や環境によるものです。
この研究でわかったのは次のようなことです。
- 離婚する人は、似た性格の双子も離婚しやすい
- 家族全体の環境よりも、本人の性格や行動が影響する
- 感情の起伏が強い人は離婚リスクが高くなる傾向がある
また、離婚後には気分の落ち込みや問題行動が増えることもあります。
これらも遺伝の影響を受けることが知られています。
このように、離婚という行動にも、生まれ持った性質が関係しているのです。
まとめると、離婚には個人の性格や特性が強く関わっており、それには遺伝の力があると考えられます。
結婚と離婚は同じ理由で起こるのか?
結婚と離婚には、まったく別の影響が働いています。
この研究では、結婚したかどうかと、離婚したかどうかを同時に調べました。
すると、2つの行動は、同じ原因では説明できないことがわかりました。
研究では、結婚と離婚がどのくらい同じ要因で説明できるかを計算しました。
結果、たったの0.7パーセントしか共通していませんでした。
つまり次のようなことが言えます。
- 結婚しやすい人が離婚しやすいとは限らない
- 結婚と離婚は別々の遺伝や環境の影響を受けている
- 同じ人でも結婚の時と離婚の時では、理由がまったく異なる
これまで、結婚と離婚はつながっていると考えられがちでした。
しかし、この研究ではそれをはっきりと否定する結果となりました。
まとめると、結婚と離婚は似ているようで実は別々の問題であり、それぞれに異なる影響があるといえます。
結婚してから離婚までに働く別の力
離婚には、結婚とは違う新しい影響が加わります。
結婚したあとの生活では、さまざまな出来事が起こります。
それらが原因で、関係が悪くなってしまうこともあります。
研究では、離婚につながる要因として以下のようなものが示されています。
- 感情のコントロールが難しい
- 相手とのすれちがいが多い
- 不安や怒りの気持ちをうまく伝えられない
- よく知られている問題行動(酒やギャンブル)も関係する
これらはすべて、性格や習慣、生活環境に関係しています。
そして、それぞれが遺伝の影響を一部受けています。
結婚するまでと、結婚してからでは、必要な力や対応が変わるのです。
まとめると、離婚は結婚の延長ではなく、新しい状況で起こる別の問題と考える必要があります。
結婚していない人には離婚のデータがない理由
離婚の研究には、結婚した人のデータしか使えません。
これは当たり前のようですが、分析にとっては大きな問題です。
なぜなら、離婚のしやすさを測るには、そもそも結婚している必要があるからです。
たとえば、次のような人の情報は離婚の分析には使えません。
- 一度も結婚したことがない人
- 結婚を望まなかった人
- 同棲はしたが結婚しなかった人
そのため、離婚に関する分析は「結婚した人の中だけ」で行われます。
研究者たちはその条件をふまえて、特殊な分析方法を使っています。
結婚していない人の中にも、離婚しやすい性格の人はいるかもしれません。
しかし、それはデータに現れないため、分析では無視されてしまうのです。
まとめると、離婚の研究は限られた人の情報に基づいており、それが研究の限界にもなっています。
離婚のしやすさに関わる個人の違い
ある人が離婚しやすいかどうかには、個人の性格が関係しています。
この研究では、離婚しやすい人に見られる性格の例が紹介されています。
その中で大きな影響があったのが、次のような特性です。
- 情動性が高い(感情の波が大きい)
- 外向性が高すぎる(刺激を求めやすい)
- 伝統的な考えを持たない(型にはまらない)
また、配偶者とのやりとりも影響しています。
人との関係の作り方がうまくいかないと、すれちがいが生まれやすくなります。
一方で、誠実性が高い人は離婚のリスクが低いという傾向も見られました。
ただし、この研究では性格検査を直接行っていません。
過去の研究とあわせて考えると、性格の違いが離婚の起こりやすさを左右すると考えられます。
まとめると、離婚には本人の持つ特性や考え方が大きく関係しており、それには生まれつきの傾向も含まれています。
結婚の遺伝と性格・行動のつながり
離婚しやすい人に見られる性格とは?
離婚しやすい人には、共通する性格の傾向があります。
研究では、配偶者の性格が離婚に大きく関係することが示されました。
特に、一方の性格が強く出ると関係が不安定になりやすいのです。
次のような性格が、離婚リスクを高めるとされています。
- 情動性が高い(すぐにイライラしたり落ち込む)
- 外向性が高すぎる(刺激を求める行動が多い)
- 自分の意見を曲げない(柔軟に対応できない)
また、相手との協力や理解がうまくいかないと、関係がこじれやすくなります。
性格の違いが会話や価値観のズレを生みやすくするからです。
このような傾向は、遺伝によってある程度決まっていることもわかっています。
まとめると、離婚に関係する性格にはパターンがあり、そこには遺伝の影響が関係しています。
情動性が高い人は離婚リスクが高い?
感情の変化が激しい人は、離婚しやすい傾向があります。
情動性とは、感情の動きが激しかったり、不安や怒りを感じやすい性格のことです。
この性格が高い人は、夫婦関係において衝突が起きやすくなります。
たとえば、こんな行動が見られます。
- 小さなことでイライラしてしまう
- 相手の言葉に過敏に反応する
- 気分が不安定で長く続かない
研究では、このような傾向が離婚につながることが報告されています。
また、この性格の高さは、生まれつきの部分が多く、遺伝的に受け継がれることもあるのです。
もちろん、全ての感情的な人が離婚するわけではありません。
ただし、感情の扱い方が関係を左右することは間違いありません。
まとめると、情動性が高い人は夫婦関係が不安定になりやすく、離婚リスクも高まることがあります。
外向的な人はうまくいかないことが多い?
外向性が高い人は離婚のリスクがやや高くなります。
外向性とは、人との関わりが好きで、行動的で活発な性格のことです。
一見すると良い性格に思えますが、過度な外向性は問題になることもあります。
具体的には、以下のような傾向があります。
- 新しい刺激を求めて落ち着かない
- 配偶者以外の人と関わる機会が多い
- 自由を大切にしすぎて衝突が起きやすい
研究では、外向性が高い人は離婚の可能性がやや上がることが示されています。
特に、行動が極端だったり、自分の欲求を優先しがちな人は注意が必要です。
この性格もまた、遺伝の影響を受けやすいとされています。
まとめると、外向性が強いことは一長一短であり、結婚生活にはバランスが必要です。
夫婦のやりとりと性格の関係
性格の違いが夫婦の関係に大きな影響を与えます。
研究では、夫婦のやりとりがうまくいかない理由のひとつに、性格の相性があると指摘されています。
たとえば、以下のようなケースが見られます。
- 一方が感情的で、もう一方が冷静すぎる
- 誠実性の高い人とそうでない人がすれちがう
- 人付き合いのスタイルが極端に違う
このような性格の組み合わせは、関係にストレスを生みやすくなります。
特に、感情をうまく表現できない人は、誤解を生みやすくなる傾向があります。
また、夫婦関係の質が悪いと、精神的な問題や行動の乱れも引き起こすことがあります。
このような性格の違いは、少なからず遺伝によっても決まっている可能性があります。
まとめると、夫婦のやりとりのうまさは、性格の相性と深く関わっており、その根本には生まれつきの特性があります。
離婚後に見られる問題行動の背景
離婚した後に問題行動が増えることがあります。
研究では、離婚した人に次のような行動が見られると報告されています。
- 気分が落ち込む(うつ状態)
- お酒やたばこの使用が増える
- ギャンブルなどに走る傾向がある
これらは一時的な感情の変化だけではありません。
実は、こうした行動には、もともとの性格や遺伝的な要因が関係していることがあります。
たとえば、もともと情動性が高い人は、離婚後に気持ちのコントロールが難しくなりやすいです。
また、ストレスへの耐性が低い人も、問題行動に向かいやすい傾向があります。
このような傾向は、もともとその人が持っている特徴に基づいていると考えられています。
まとめると、離婚後の行動には個人の性格や生まれつきの傾向が影響しており、それが行動の変化につながっています。
研究から見えた結婚の遺伝の本質
結婚と離婚はまったく別のものだった
結婚と離婚は、同じものの表と裏ではありませんでした。
研究では、結婚と離婚の関係について詳しく調べられました。
多くの人は、結婚した人が離婚するという流れを想像します。
しかし実際には、結婚と離婚は別々の影響を受けているとわかったのです。
その理由は、次の通りです。
- 結婚に影響する遺伝子と離婚に影響する遺伝子が違う
- 環境の影響も、それぞれで異なる働きをする
- 結婚した人すべてが離婚の対象になるわけではない
たとえば、結婚する性格と、離婚する性格は一致しないことが多いです。
外向的で社交的な人は結婚しやすいですが、同時に離婚もしやすい傾向があります。
つまり、結婚のしやすさと離婚のしやすさは別の問題なのです。
まとめると、結婚と離婚は似ているように見えて、実はまったく異なる仕組みで成り立っているといえます。
結婚と離婚に共通する要因はたった0.7%
結婚と離婚に共通する要因は、わずか0.7%でした。
研究では、「CCCモデル」と呼ばれる分析方法が使われました。
この方法で、結婚と離婚の遺伝や環境の重なりが調べられました。
その結果、以下のことがわかりました。
- 結婚と離婚の間には、ほとんど関係がない
- 共通する要因は、全体のたった0.7%だけ
- ほぼすべての影響は、独立して働いている
つまり、結婚に至った理由が、離婚の理由とはまったく別ということです。
この数値は驚くほど低く、想像以上に両者は関係がないといえます。
人は「結婚と離婚はセット」だと思いがちですが、それは実際のデータとは異なります。
結婚しても、離婚の仕方は人それぞれというのが本当のところです。
まとめると、結婚と離婚を同じものとして考えるのは間違いであり、それぞれの背景は大きく違っています。
年齢や世代によって遺伝の影響は変わる?
遺伝の影響は、年齢によって変わることがあります。
過去の研究では、年齢や人生の時期によって遺伝の強さが変化することが報告されています。
今回の研究の対象者は、平均年齢38歳の男性でした。
そのため、以下の点に注意が必要です。
- 若い人と年配の人で結果が違うかもしれない
- 結婚や離婚の時期によって、影響の出方が変わる可能性がある
- 高齢になると、離婚を避ける傾向もある
たとえば、若い時は衝動的な行動が多く、遺伝の影響が強く出ることがあります。
一方で、年齢を重ねると、考え方が変わり、行動も落ち着いてきます。
そのような変化は、環境によるものかもしれません。
このように、遺伝と環境のバランスは年齢とともに変わるのです。
まとめると、結婚や離婚に対する遺伝の影響は、年齢や時代によって違いがある可能性が高いです。
男性だけのデータで見えた限界
今回の研究は、男性だけを対象にしていました。
対象者は、ベトナム戦争時代に兵役に就いた双子の男性たちです。
そのため、結果をすべての人に当てはめることはできません。
たとえば、次のような限界があります。
- 女性のデータが入っていない
- 結婚観や価値観が今と違う可能性がある
- 軍人という特殊な環境で育った影響がある
また、男性と女性では、結婚や離婚に対する考え方や行動のしかたが違うことも知られています。
性格の影響も、男女で異なるパターンを示すことがあります。
したがって、この研究結果はあくまで一部の条件での話と考える必要があります。
まとめると、今回の研究は重要な示唆を与えるものですが、男女や世代の違いを考慮した追加研究が必要です。
今後の研究で明らかにすべきこと
結婚と離婚に影響する要因には、まだ多くの未知が残っています。
今回の研究では、遺伝と環境の影響を中心に分析されました。
しかし、性格や精神状態など、他の要因も関係していると考えられます。
今後の研究で注目すべき点は、以下のようなものです。
- 性格のタイプと結婚・離婚の関係
- 心の病気やストレスとのつながり
- 配偶者同士の性格の相性
- 文化や社会的背景の違い
さらに、夫婦の両方の情報を集めることで、関係のバランスがより正確に見えてくるでしょう。
また、男女それぞれの視点からも分析する必要があります。
研究が進めば、「なぜこの人は結婚しやすいのか」「なぜ離婚しやすいのか」がもっと詳しく理解できるようになります。
まとめると、今後の研究によって、結婚と離婚に関する新しい知見が広がることが期待されます。
最後に
この記事では、「結婚の遺伝」が本当にあるのか、そして離婚との関係まで、研究にもとづいて見てきました。結果からわかったのは、結婚や離婚には生まれつきの性格や気質が関係しているということです。
つまり、結婚しやすい人や離婚しやすい人には、ある程度の共通点があり、それは遺伝からきている場合もあるのです。
また、結婚と離婚は別々の影響を受けていて、同じ理由では説明できないこともわかりました。もちろん、すべてが遺伝で決まるわけではありません。
自分の経験や環境、考え方も大きな力になります。だからこそ、自分の性格や行動を知ることは、これからの人間関係にとって大切なヒントになるかもしれません。
恋愛や結婚について考えるときに、少しだけ「自分の特性」についても意識してみてください。
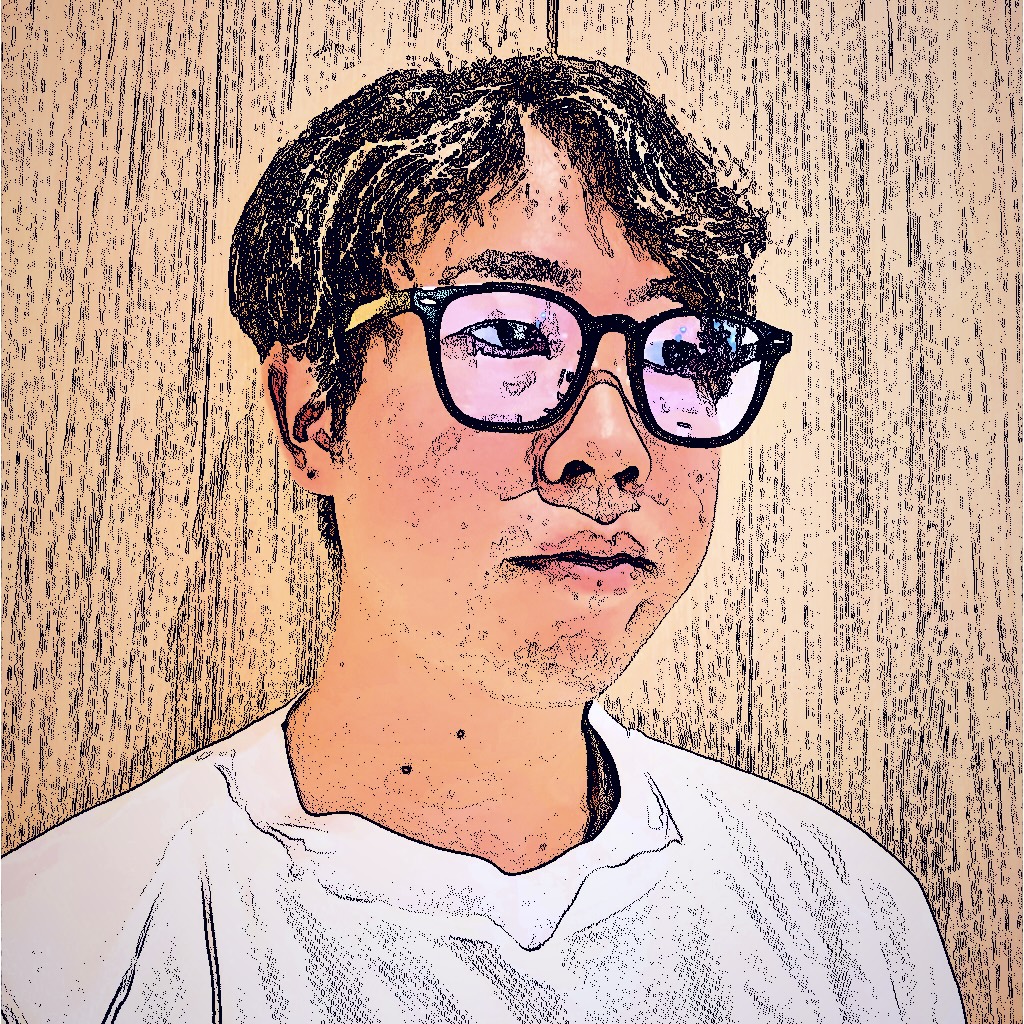
ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。








