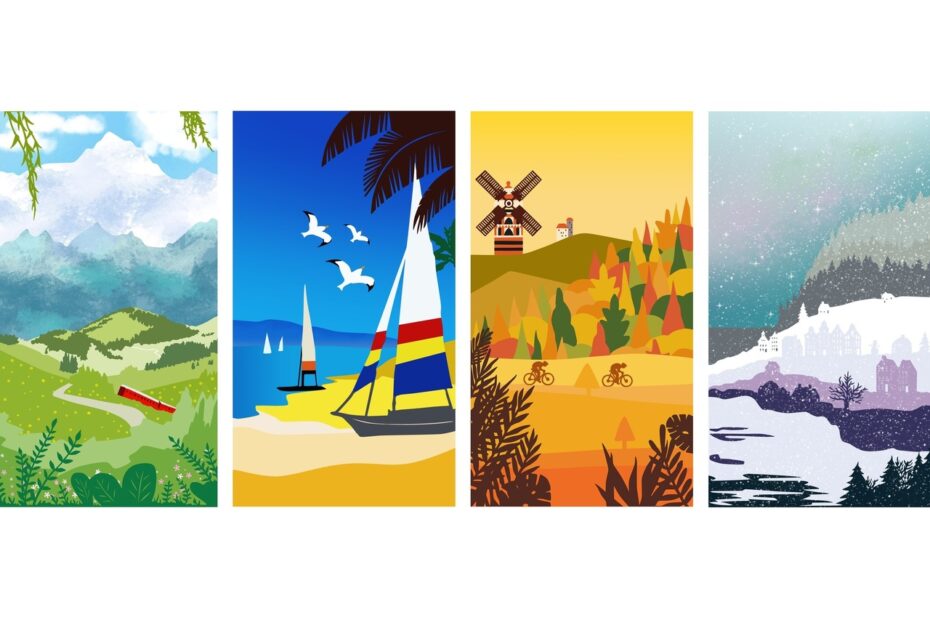季節によって気分が変わる経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。春になると元気になり、冬は少し憂うつ…。
このような気分の変化には、実は私たちの性格が関係しているかもしれません。
最近の研究「Seasonality and personality: a prospective investigation of Five Factor Model correlates of mood seasonality」では、季節による気分の変化と性格の関係が調べられました。
この研究結果から、私たちの性格によって季節の影響の受け方が違う可能性がわかってきたのです。
この記事では、研究結果をわかりやすく解説しながら、季節と上手に付き合うためのヒントをお伝えします。自分の気分と季節の関係について、一緒に考えてみましょう。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
季節と気分の関係:あなたの性格が影響しているかも
研究の目的:季節による気分変化と性格の関連を探る
この研究の目的は、季節によって変わる気分と性格の関係を調べることです。
研究者たちは、人の気分が季節によって変化するのは、性格が関係しているのではないかと考えました。
そこで、性格と季節による気分の変化の関連を探ることにしたのです。
季節による気分の変化は、多くの人が経験します。
例えば、以下のような変化がよく見られます:
- 冬に憂うつになる
- 春に元気になる
- 夏に活動的になる
- 秋に落ち着く
このような変化が、どのような性格の人に起こりやすいのかを
明らかにすることが、この研究の狙いでした。
また、性格によって気分の変化の仕方が違うのかも調べることにしました。
これらのことがわかれば、自分の気分の変化を理解し、上手く付き合っていく方法が見つかるかもしれません。
つまり、この研究は私たちの日常生活に役立つ情報を得ることを目指していたのです。
調査方法:2年間で304人の気分と性格を測定
この研究では、304人を対象に2年間にわたって調査を行いました。
調査は、オーストラリアのメルボルンで実施されました。
参加者は、一般の人々から無作為に選ばれました。
調査は、次のような方法で行われました:
- 冬と夏の年2回、2年間で計4回実施
- 気分と性格の両方を測定
- 質問票を使って回答を集める
気分の測定では、その時点での気分の状態を答えてもらいました。
性格の測定には、「NEO Five Factor Inventory」というテストが使われました。
このテストは、5つの要素で性格を分析します。
測定は慎重に行われ、信頼性の高いデータを集めることができました。
2年間という長期間の調査により、季節による気分の変化を正確に捉えることができました。
また、多くの人を対象にしたことで、さまざまな性格の人のデータを集めることができました。
このような方法で、季節と気分の関係を詳しく調べることができたのです。
季節性スコアとは:夏と冬の気分の差を数値化
季節性スコアは、夏と冬の気分の差を数字で表したものです。
このスコアは、次のように計算されました:
- 夏の気分の点数を測定
- 冬の気分の点数を測定
- 夏の点数から冬の点数を引く
例えば、夏の気分が80点、冬の気分が60点だった場合、季節性スコアは20点になります。
この数字が大きいほど、夏と冬の気分の差が大きいことを意味します。
逆に、この数字が小さいほど、季節による気分の変化が小さいことを示します。
また、マイナスの数字になることもあります。
これは、冬の方が夏よりも気分が良いことを表します。
研究者たちは、この季節性スコアを使って、性格との関連を調べました。
このスコアを使うことで、季節による気分の変化を客観的に比較できます。
そのため、性格との関係を科学的に分析することができたのです。
季節性スコアは、私たちの気分の変化を数字で表現する重要な道具となりました。
性格特性の測定:5つの要素で性格を分析
性格特性の測定には、5つの要素を使う方法が用いられました。
この方法は「ビッグファイブ」と呼ばれています。
5つの要素は以下の通りです:
- 開放性:新しい経験への態度
- 誠実性:計画性や責任感
- 外向性:社交性や活動性
- 協調性:他人への思いやり
- 神経症傾向:不安や心配のしやすさ
それぞれの要素について、質問に答えることで点数が付けられます。
例えば、開放性が高い人は、新しいことに挑戦するのが好きです。
一方、誠実性が高い人は、計画を立てて行動するのが得意です。
外向性が高い人は、人と話すのが好きで、活発な傾向があります。
協調性が高い人は、他人の気持ちを考えて行動します。
神経症傾向が高い人は、ストレスを感じやすい傾向があります。
この5つの要素を測ることで、その人の性格を総合的に理解できます。
研究では、この方法を使って参加者の性格を分析しました。
そして、季節性スコアとの関連を調べたのです。
季節による気分変化と関係する2つの性格特性
開放性:新しい経験を好む性格
開放性は、新しい経験や考え方を受け入れる性格のことです。
この特性が高い人には、次のような特徴があります:
- 好奇心が強い
- 想像力が豊か
- 芸術や文化に興味がある
- 冒険を楽しむ
- 変化を恐れない
一方、開放性が低い人は、慣れたものや伝統的なものを好む傾向があります。
研究では、開放性と季節による気分の変化に関連があることがわかりました。
開放性が高い人ほど、季節の変化に敏感である可能性があります。
これは、環境の変化に対して敏感に反応する性質があるためかもしれません。
例えば、冬の暗さや寒さをより強く感じ取るかもしれません。
また、春の訪れをより喜びをもって迎えるかもしれません。
このような性格の人は、季節の移り変わりを楽しむ一方で、気分の変動も大きくなる可能性があります。
開放性は、季節と気分の関係を理解する上で重要な性格特性の一つです。
神経症傾向:不安や心配が多い性格
神経症傾向は、不安や心配が多い性格のことを指します。
この特性が高い人には、以下のような特徴があります:
- ストレスを感じやすい
- 気分の変動が大きい
- 自信が持ちにくい
- 心配性である
- 感情的になりやすい
一方、神経症傾向が低い人は、比較的落ち着いていて、安定しています。
研究の結果、神経症傾向は季節による気分の変化の大きさと関係していました。
神経症傾向が高い人ほど、季節に関わらず気分の変動が大きい傾向がありました。
これは、環境の変化に対して敏感に反応するためかもしれません。
例えば、天候の変化や日照時間の変化に強く影響を受ける可能性があります。
ただし、神経症傾向は冬に気分が下がるといった特定の方向性とは関係がないことがわかりました。
つまり、夏に気分が下がる人もいれば、冬に気分が下がる人もいるということです。
神経症傾向は、季節による気分の変化の強さを予測する重要な要因と言えます。
開放性が高い人は冬に気分が下がりやすい?
研究の結果、開放性が高い人は冬に気分が下がりやすい傾向がわかりました。
これには、いくつかの理由が考えられます:
- 環境の変化に敏感
- 活動の制限を強く感じる
- 光の減少に影響を受けやすい
- 新しい経験の機会が減ることへの不満
開放性が高い人は、周りの環境の変化に敏感です。
そのため、冬の暗さや寒さをより強く感じ取るかもしれません。
また、冬は外出の機会が減り、新しい経験をする機会も少なくなります。
これは、新しいことを好む開放性の高い人にとって、ストレスになる可能性があります。
さらに、冬は日照時間が短くなります。
光の減少は、多くの人の気分に影響しますが、開放性の高い人はより強く影響を受けるかもしれません。
ただし、これは必ずしも悪いことではありません。
季節の変化を敏感に感じ取ることで、春の訪れをより喜びをもって迎えられるかもしれません。
開放性の高い人は、冬の気分の落ち込みに注意が必要です。
神経症傾向が高い人は季節による気分の変化が大きい?
神経症傾向が高い人は、季節による気分の変化が大きい傾向があります。
この傾向には、次のような特徴があります:
- 気分の波が激しい
- 環境の変化に敏感に反応する
- ストレスを感じやすい
- 気分の調整が難しい
神経症傾向が高い人は、もともと感情の変動が大きい傾向があります。
季節の変化は、この傾向をさらに強める可能性があります。
例えば、冬の長い夜に不安を感じやすくなったり、夏の暑さにイライラしやすくなったりします。
また、天候の変化にも敏感に反応します。
雨の日が続くと憂うつになりやすく、晴れの日が続くと気分が高揚しやすいかもしれません。
ただし、気分の変化の方向性は人それぞれです。
冬に気分が落ち込む人もいれば、夏に落ち込む人もいます。
神経症傾向が高い人は、自分の気分の変化のパターンを知ることが大切です。
そうすることで、季節の変化に備えることができます。
気分の変化が大きいことを知っておくことで、適切な対処法を見つけやすくなります。
その他の性格特性:外向性、協調性、誠実性との関係
外向性、協調性、誠実性と季節による気分の変化の関係は、あまり強くありませんでした。
これらの性格特性について、簡単に説明します:
- 外向性:社交的で活動的な性格
- 協調性:思いやりがあり、協力的な性格
- 誠実性:責任感があり、計画的な性格
研究の結果、これらの性格特性は季節による気分の変化とはっきりとした関連がありませんでした。
例えば、外向性の高い人は人と交流することで気分を保つかもしれません。
しかし、季節による気分の変化の大きさとは直接的な関係はなさそうです。
協調性の高い人は、他人への思いやりが強いですが、これも季節による気分の変化とはあまり関係がないようです。
誠実性の高い人は、計画的に物事を進める傾向がありますが、これも季節による気分の変化とははっきりとした関連がありませんでした。
ただし、これらの性格特性も間接的には影響している可能性があります。
例えば、外向性の高い人は冬でも積極的に外出するかもしれません。
これが結果的に、気分の落ち込みを防ぐ効果があるかもしれません。
このように、直接的な関連はなくても、間接的に季節と気分の関係に影響を与える可能性はあります。
季節と気分の関係:年齢による違いも
若い人ほど季節の影響を受けやすい?
研究結果によると、若い人ほど季節による気分の変化が大きい傾向があります。
この傾向には、いくつかの理由が考えられます:
- ホルモンバランスの変化
- 生活リズムの不安定さ
- 経験の少なさ
- ストレス対処能力の発達途上
若い人は、身体的にも精神的にも
まだ成長の途中にあります。
そのため、環境の変化に敏感に反応しやすいのです。
例えば、冬の日照時間の減少は、若い人の気分により強く影響を与えるかもしれません。
また、若い人は生活リズムが不安定になりやすいです。
季節の変化によって睡眠パターンが乱れると、気分にも大きな影響が出る可能性があります。
さらに、季節の変化への対処経験が少ないことも影響しているかもしれません。
年齢を重ねるにつれて、季節の変化への対処法を学んでいきます。
しかし、若い人はまだその段階にありません。
年齢を重ねると季節による気分の変化が小さくなる理由
年齢を重ねると、季節による気分の変化が小さくなる傾向があります。
これには、いくつかの理由が考えられます:
- 経験の蓄積
- ホルモンバランスの安定
- ストレス対処能力の向上
- 生活リズムの確立
年齢を重ねると、季節の変化を何度も経験することになります。
そのため、季節ごとの対処法を自然と身につけていきます。
例えば、冬に気分が落ちやすいことを知っていれば、前もって対策を立てることができます。
また、年齢とともにホルモンバランスが安定してきます。
これにより、環境の変化に対する身体の反応が穏やかになります。
ストレス対処能力も、年齢とともに向上していきます。
季節の変化によるストレスも、上手く管理できるようになります。
さらに、生活リズムが確立されていくことも大きな要因です。
規則正しい生活は、季節の変化による影響を軽減します。
ただし、これは一般的な傾向であり、個人差があることを忘れてはいけません。
年齢に関わらず、自分の気分の変化に注意を払うことが大切です。
季節による気分変化のメカニズム:2つの可能性
環境の変化に敏感:開放性との関連
開放性が高い人は、環境の変化に敏感に反応する傾向があります。
これが季節による気分変化と関連している可能性があります。
開放性が高い人の特徴は以下の通りです:
- 新しい経験を好む
- 想像力が豊か
- 好奇心が強い
- 変化に対して柔軟
このような特徴から、季節の変化をより強く感じ取るのかもしれません。
例えば、春の訪れを喜び、秋の美しさに感動しやすいでしょう。
一方で、冬の暗さや寒さもより強く感じ取ってしまうかもしれません。
これは、環境の微妙な変化に気づきやすいためだと考えられます。
光の変化、気温の変化、自然の移り変わりなどを敏感に感じ取ります。
そのため、季節の変化が気分により大きな影響を与える可能性があります。
ただし、これは必ずしも悪いことではありません。
季節の変化を楽しむ能力にもつながるからです。
開放性の高い人は、季節の変化を意識的に楽しむことで、気分の変動をポジティブに活用できるかもしれません。
気分の波が大きい:神経症傾向との関連
神経症傾向が高い人は、気分の波が大きい傾向があります。
これが季節による気分変化と関連している可能性があります。
神経症傾向が高い人の特徴は以下の通りです:
- 不安になりやすい
- ストレスを感じやすい
- 感情の起伏が激しい
- 心配性である
このような特徴から、季節の変化に対しても敏感に反応するのかもしれません。
例えば、冬の長い夜に不安を感じやすくなったり、夏の暑さにイライラしやすくなったりします。
また、天候の変化にも敏感に反応します。
雨の日が続くと憂うつになりやすく、晴れの日が続くと気分が高揚しやすいかもしれません。
これは、環境の変化に対して感情的に反応しやすいためだと考えられます。
ホルモンバランスの変化やストレスへの脆弱性も関係しているかもしれません。
ただし、気分の変化の方向性は人それぞれです。
冬に気分が落ち込む人もいれば、夏に落ち込む人もいます。
神経症傾向が高い人は、自分の気分の変化のパターンを知ることが大切です。
そうすることで、季節の変化に備えることができます。
季節性気分障害(SAD)との関係
季節性気分障害(SAD)は、季節の変化によって引き起こされる気分障害です。
SADと性格特性には、いくつかの関連が考えられます:
- 開放性との関係
- 神経症傾向との関係
- その他の性格特性との関係
開放性が高い人は、季節の変化に敏感であるため、SADになりやすい可能性があります。
特に、冬型のSADとの関連が指摘されています。
神経症傾向が高い人も、SADのリスクが高い可能性があります。
気分の変動が大きいため、季節の変化による影響を受けやすいからです。
ただし、SADは単に性格だけで決まるものではありません。
その他の要因も大きく関わっています。
例えば、以下のような要因が挙げられます:
- 遺伝的要因
- 地理的要因(緯度など)
- 生活習慣
SADの症状がある場合は、専門家に相談することが大切です。
性格特性を知ることは、SADの理解や対処に役立つかもしれません。
しかし、適切な診断と治療が最も重要です。
冬型と夏型:気分が下がりやすい季節の違い
季節による気分の変化には、冬型と夏型があります。
それぞれの特徴は以下の通りです:
冬型:
- 冬に気分が落ち込む
- 日照時間の減少が影響
- エネルギー低下や過眠が見られる
夏型:
- 夏に気分が落ち込む
- 暑さや長い日照時間が影響
- 不眠や食欲不振が見られる
冬型は比較的よく知られていますが、夏型も存在します。
冬型の人は、日照時間の減少や寒さによってエネルギーが低下します。
一方、夏型の人は、暑さや長い日照時間によってストレスを感じます。
性格特性との関連では、開放性が高い人は冬型になりやすい可能性があります。
しかし、夏型との明確な関連はまだわかっていません。
神経症傾向は、冬型にも夏型にも関連している可能性があります。
自分がどちらのタイプか知ることは、気分の管理に役立ちます。
例えば、冬型の人は冬に向けて対策を立てることができます。
夏型の人は、夏を乗り切るための準備をすることができます。
どちらのタイプでも、専門家に相談することが大切です。
自分の季節による気分の変化を知ることの重要性
自分の季節による気分の変化を知ることは、とても大切です。
その理由は以下の通りです:
- 自己理解が深まる
- 対策を立てやすくなる
- ストレス管理に役立つ
- 周囲の理解を得やすくなる
自分の気分の変化パターンを知ることで、自己理解が深まります。
例えば、冬に気分が落ち込みやすいことがわかれば、それに備えることができます。
対策を立てやすくなるのも大きなメリットです。
夏に気分が高まりやすい人は、その時期に新しいことに挑戦するのもいいでしょう。
ストレス管理にも役立ちます。気分の変化を予測できれば、ストレスへの対処法も準備できます。
周囲の理解を得やすくなるのも重要です。
家族や友人、職場の人に伝えることで、サポートを得やすくなります。
気分の変化を記録することから始めるのがおすすめです。
日記やアプリを使って、毎日の気分を記録してみましょう。
数ヶ月続けると、パターンが見えてくるかもしれません。
自分の気分の変化を知ることで、より良い生活を送ることができます。
専門家に相談するのも良い方法です。
季節と上手に付き合うためのヒント
自分の性格タイプを知ろう
自分の性格タイプを知ることは、季節との付き合い方を考える上で重要です。
性格タイプを知るには、以下の方法があります:
- 性格テストを受ける
- 自己観察を行う
- 周囲の意見を聞く
- 専門家に相談する
性格テストは、自分の傾向を客観的に知るのに役立ちます。
ただし、結果を絶対視せず、参考程度に考えるのが良いでしょう。
自己観察も大切です。日々の行動や感情を振り返ることで、自分の特徴が見えてきます。
周囲の意見を聞くのも効果的です。他人から見た自分の印象を知ることで、新たな気づきがあるかもしれません。
専門家に相談するのも一つの方法です。カウンセラーや心理士は、あなたの性格を客観的に分析してくれるでしょう。
性格タイプを知ることで、季節による影響の受けやすさがわかります。
例えば、開放性が高い場合は冬の気分の落ち込みに注意が必要かもしれません。
神経症傾向が高い場合は、季節を問わず気分の変動に気をつける必要があるでしょう。
自分の性格タイプを知ることで、より効果的な対策を立てることができます。
季節の変化に備えるための工夫
季節の変化に備えるための工夫は、気分の安定に役立ちます。
以下のような方法があります:
- 規則正しい生活リズムを保つ
- 運動を習慣化する
- 食事に気をつける
- 光療法を試す
- ストレス解消法を見つける
規則正しい生活リズムは、体内時計の調整に役立ちます。
特に、起床時間と就寝時間を一定にすることが大切です。
運動は、気分を向上させる効果があります。
季節を問わず、適度な運動を心がけましょう。
食事も重要です。季節に合った食材を取り入れ、バランスの良い食事を心がけましょう。
光療法は、特に冬の気分の落ち込みに効果があります。
朝の光を浴びることで、体内時計が整います。
ストレス解消法を見つけることも大切です。
趣味や瞑想など、自分に合った方法を探しましょう。
これらの工夫を日常的に行うことで、季節の変化に対する耐性が高まります。
ただし、効果には個人差があります。自分に合った方法を見つけることが大切です。
気分が落ち込みやすい季節の過ごし方
気分が落ち込みやすい季節には、特別な配慮が必要です。
以下のような対策が効果的です:
- 屋外で過ごす時間を増やす
- 社会的つながりを大切にする
- 新しい趣味や活動を始める
- マインドフルネスを実践する
- 環境を明るく保つ
屋外で過ごす時間を増やすことで、自然光を浴びる機会が増えます。
これは、特に冬の気分の落ち込みに効果があります。
社会的つながりも重要です。
友人や家族との交流は、気分を向上させる効果があります。
新しい趣味や活動を始めるのも良いでしょう。
新しいことへの挑戦は、脳を活性化させ、気分を前向きにします。
マインドフルネスの実践も効果的です。
瞑想やヨガなどを通じて、現在の瞬間に集中することで、ネガティブな思考から距離を置けます。
環境を明るく保つことも大切です。
部屋の照明を工夫したり、明るい色の服を着たりするのも良いでしょう。
これらの対策を組み合わせることで、気分の落ち込みを和らげることができます。
ただし、症状が重い場合は、専門家の助けを求めることが大切です。
自分に合った方法を見つけ、季節を上手に乗り越えましょう。
最後に
この記事では、季節による気分の変化と性格の関係について見てきました。
新しいことが好きな人は冬に気分が落ち込みやすく、心配性の人は季節を問わず気分の変化が大きい傾向があることがわかりました。
でも、これは単なる「運命」ではありません。自分の性格と季節の関係を知ることで、より上手に対処できるんです。
例えば、冬に気分が落ちやすい人は、その時期に楽しみを見つけたり、光を多く浴びるよう心がけたりすることができます。
大切なのは、自分自身をよく知ること。日々の気分を記録したり、友達や家族と話したりして、自分の傾向を探ってみましょう。
そして、自分に合った対策を見つけていくのです。
季節の変化は、私たちの人生に彩りを与えてくれます。その変化を前向きに受け止め、上手に付き合っていけば、より豊かな毎日を送ることができるはずです。
みなさんも、自分なりの「季節との付き合い方」を見つけてみてください。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。