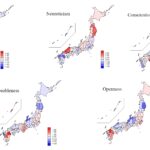スポーツ選手に必要な性格的資質とは何でしょうか。
部活動などでスポーツに打ち込む中で、時に悩むことがあるかもしれません。
「もっと上手くなりたい」「もっと活躍したい」と願っても、なかなか思うようにいかない。
そんな時、自分の性格を見つめ直してみるのも1つの方法かもしれません。
実は、ある研究で、世界で活躍するトップアスリートに共通する性格特性が明らかになったのです。
その研究とは、「Personality profile of individual sports champions」という論文に詳しく書かれています。
この研究では、600人ものスポーツ選手の性格を詳しく分析。
そこから見えてきたのは、チャンピオンクラスの選手に特有の性格傾向でした。
彼らに備わっていたのは、ある4つの性格特性だったのです。
この記事では、そうした性格特性について、順を追って詳しく解説していきます。
スポーツに真剣に取り組む人とそこに関わる人にとってはきっと参考になるはずです。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

スポーツ選手に求められる性格特性とは
性格特性を表す「ビッグファイブ」という尺度
性格心理学では、性格特性を5つの次元で表す「ビッグファイブ」という尺度がよく使われています。
この5つの次元とは、以下のようなものです。
- 神経症傾向:不安や怒りなどのネガティブな感情を感じやすいか
- 外向性:社交的で活発か、内向的で控えめか
- 経験への開放性:新しいことへの興味や知的好奇心の強さ
- 協調性:他人に対して親切で協力的か、敵対的で利己的か
- 誠実性:責任感が強く、計画的で勤勉か、衝動的で怠惰か
ビッグファイブは性格を多面的に捉える枠組みとして、スポーツ選手の性格研究にも活用されています。
スポーツ選手の性格を調べた大規模な研究
ポーランドの研究者が、600人ものスポーツ選手を対象に、ビッグファイブの性格検査を実施しました。
この大規模な調査によって、スポーツ選手に共通する性格特性や、競技による性格の違いが明らかになりました。
調査には「NEO-FFI」という質問紙が使われ、各性格次元の傾向が数値化されました。
研究の目的は、個人競技で世界レベルの成績を収めるチャンピオンに、どのような性格の特徴があるのかを探ることでした。
個人競技のトップアスリートに焦点を絞った研究は珍しく、スポーツ心理学の発展に寄与する貴重なデータと言えます。
調査の対象となったスポーツ選手の内訳
調査に参加したのは、20歳から29歳のポーランド人アスリート600人です。
彼らは全員、個人競技の選手でした。
具体的な内訳は以下の通りです。
- 20の競技から、各30人ずつ選出
- 登山、オリエンテーリング、バイアスロン、フィットネスなど
- 乗馬、カヌー、自転車、ボディビル、陸上長距離、陸上短距離など
- アーチェリー、アルペンスキー、水泳、リュージュ、スノーボードなど
- スポーツシューティング、ブレイクダンス、社交ダンス、テニス、スポーツクライミングなど
これらの選手の中から、さらに世界大会や欧州大会でメダルを獲得したことのある56人が「チャンピオン」として抽出されました。
こうして、一流選手とそれ以外の選手の性格特性を比較することができたのです。
スポーツ選手の個人競技の種目によって違いがある
調査の結果、個人競技であっても、種目によって選手の性格特性に違いがあることが分かりました。
統計的に見ると、ビッグファイブのすべての次元で、競技間の有意差が認められたのです。
つまり、それぞれのスポーツが求める心理的資質が異なっており、それが選手の性格に反映されているのでしょう。
特に顕著だったのは、神経症傾向と経験への開放性の2つの次元でした。
神経症傾向は分散の29%、経験への開放性は16%を説明していました。
競技の特性によって、必要とされる性格のタイプが大きく異なることが示唆されたと言えます。
神経症傾向が低いのはどの競技のスポーツ選手?
神経症傾向が最も低かったのは、スポーツクライミング、登山、リュージュの選手たちでした。
これらの競技者は、不安やストレスに負けない強靭な精神力を持っていると考えられます。
一方、乗馬、スポーツシューティング、社交ダンスの選手は、相対的に神経症傾向が高い傾向にありました。
ただし、同じ個人競技でも、要求される精神的タフさには差があるようです。
例えば、アルペンスキーや水泳の選手は、乗馬やダンスの選手よりも有意に神経症傾向が低かったのです。
このように、神経質になりにくい精神の安定性は、多くの個人競技で重視されていると言えるでしょう。
世界で活躍するスポーツ選手の性格の特徴
神経症傾向の低さが際立つチャンピオン級のスポーツ選手
チャンピオンクラスの選手は、他の選手と比べて、神経症傾向が極めて低いことが明らかになりました。
神経症傾向の得点差は非常に大きく、統計的な効果量は最も高い部類に入ります。
世界で活躍する一流選手は、ネガティブな感情に惑わされない、驚異的な精神力を持っているのでしょう。
トップアスリートにとって、不安やプレッシャーに負けない強靭なメンタルは不可欠な要素と言えます。
神経症傾向の低さは、チャンピオンと他の選手を分ける最も重要な性格特性だと考えられます。
実際、多くの研究で、神経症傾向の低いアスリートほど高いパフォーマンスを発揮することが報告されています。
チャンピオンは外向的な性格である
世界トップレベルの選手は、内向的というよりも外向的な性格の持ち主であることが分かりました。
統計的には、チャンピオンの外向性は、他の選手よりも有意に高いスコアを示しています。
外向的な人は、社交的で活動的、積極的といった特徴を持ちます。
スポーツの世界でも、外向的な選手は、以下のような利点を持つと考えられます。
- コーチや仲間とのコミュニケーションが良好
- 積極的に練習に取り組み、技術を磨ける
- 試合本番でも臆することなく力を発揮できる
内向的な選手が活躍する例もありますが、総じて、外向的な性格はアスリートの強みになるのかもしれません。
チャンピオンは協調性が高い
協調性も、チャンピオン選手に特徴的な性格特性であることが判明しました。
世界で活躍する選手は、他の選手よりも有意に協調性が高いのです。
協調性の高い人は、他者への思いやりや協力的な態度を示します。
スポーツにおいても、協調性の重要性は以下の点で指摘できるでしょう。
- チームメイトと良好な関係を築ける
- コーチの指導に素直に従い、上達しやすい
- ライバルとも敬意を持って接することができる
協調性の高さは、特に団体競技で求められる資質ですが、個人競技でもメリットになり得ます。
周囲との円滑な関係は、良好な練習環境を作り、選手のパフォーマンス向上に役立つのです。
誠実性もチャンピオンの重要な特徴
チャンピオンクラスの選手は、誠実性の点でも他の選手を上回っていました。
統計的に見ると、誠実性の得点差は中程度の効果量を示しています。
誠実性は、勤勉さ、計画性、自制心などを表す性格特性です。
スポーツ選手にとって、誠実性の高さは以下のような強みにつながります。
- コツコツと練習を積み、着実に力をつける
- 計画的に調整し、ベストコンディションで試合に臨める
- 誘惑に負けず、規則正しい生活を送れる
一流選手は、日々の地道な努力を続けることで、高いパフォーマンスを維持しているのでしょう。
誠実性は、才能を開花させるための土台となる大切な性格特性と言えます。
経験への開放性はスポーツの種類による
経験への開放性については、チャンピオンと他の選手の間に有意差は見られませんでした。
ただし、この性格特性は、スポーツの種類によって重要度が異なるようです。
例えば、新しい技術の習得が求められる競技では、経験への開放性の高さがアドバンテージになるかもしれません。
逆に、決まった型を正確に演じる競技では、開放性よりも几帳面さが求められるでしょう。
経験への開放性は、スポーツのタイプによって、必要とされる度合いが変わる性格特性だと考えられます。
一概にチャンピオンに不可欠な資質とは言えませんが、状況に応じて開放性を発揮できることが理想的なのかもしれません。
スポーツが性格形成に与える影響
スポーツ活動によって性格は形作られる
今回の研究から、スポーツ活動が選手の性格形成に影響を及ぼしていることが示唆されました。
各競技で求められる心理的資質が異なるように、スポーツ体験によって特定の性格特性が育まれるのでしょう。
例えば、以下のような効果が考えられます。
- 困難な練習に耐えることで、精神的なタフさが身につく
- チームメイトとの交流を通じて、社交性や協調性が高まる
- 規則正しい生活を送ることで、誠実性や自制心が養われる
スポーツは、単に体を鍛えるだけでなく、人格形成にも大きな影響力を持っているのかもしれません。
特に、ジュニア期からスポーツに打ち込むことで、性格の基盤が作られていくのでしょう。
アスリートの性格特性は、競技との相互作用の中で形作られていくと考えられます。
性格特性が競技場面での行動に影響する
一方で、性格特性そのものが、競技場面での選手の行動に影響を与えている可能性も指摘できます。
例えば、神経症傾向の低い選手は、以下のような利点を持つかもしれません。
- 試合の緊張場面でも冷静さを保ち、実力を発揮しやすい
- ミスをしても動揺せず、切り替えが早い
- コンディションの波に左右されにくい
一方、誠実性の高い選手は、練習に対する真摯な姿勢や、コーチへの素直さなどで、有利になるでしょう。
外向性や協調性の高さも、チームワークの向上や士気の高揚につながるかもしれません。
このように、性格特性は、スポーツでの行動や成績に直接的な影響力を持つと考えられるのです。
アスリートの性格を知ることは、強みを生かしたサポートをする上で重要な手がかりになるはずです。
神経症傾向の低さが成績に関係している可能性
特に、神経症傾向の低さは、スポーツでの成功と密接に関係している可能性が高いと言えるでしょう。
今回の研究では、チャンピオン選手の神経症傾向の低さが際立っていました。
その理由として、以下のようなことが考えられます。
- 不安に負けず、実力を十分に発揮できる
- 高いプレッシャーの中で冷静な判断力を保てる
- 感情的なブレが少なく、安定したパフォーマンスを維持できる
神経症傾向の高い選手は、大一番になるほど実力を出し切れない傾向があるのかもしれません。
逆に、神経質にならない選手は、試合本番での活躍が期待できるでしょう。
スポーツ心理学の分野でも、神経症傾向とパフォーマンスの関係性は重要なテーマとなっています。
神経症傾向のコントロールは、競技力向上のカギを握る要素の1つだと考えられます。
外向性の高さもパフォーマンスに好影響か
外向性の高さも、スポーツパフォーマンスにプラスの影響を与えている可能性があります。
今回の調査で、チャンピオン選手は外向的である傾向が示されました。
外向的な選手は、以下のような点で有利になるのかもしれません。
- 積極的なコミュニケーションでチームを活性化できる
- 練習やトレーニングに対する高いモチベーションを維持できる
- 試合での声掛けやボディランゲージで存在感を発揮できる
内向的な選手でも、集中力の高さなどの長所はあるでしょう。
しかし、総じて外向性の高い選手は、周囲を巻き込む力でチームを盛り上げ、パフォーマンス向上に貢献しているのかもしれません。
スポーツ心理学の研究でも、外向性とスポーツでの成功の関連性が指摘されています。 外向的な性格を生かしたメンタルトレーニングは、競技力アップに役立つ可能性が期待できます。
協調性の高さはチームワークに不可欠
協調性の高さは、特に団体競技において重要な意味を持つでしょう。 チャンピオンクラスの選手は、協調性においても高いレベルにあることが示されました。 協調性の高い選手は、以下のような利点を発揮すると考えられます。
- チームメイトとの人間関係を円滑に保てる
- 個人の利害よりもチームの目標を優先できる
- 周囲と協力し合い、チームとしてのパフォーマンスを高められる
団体競技では、選手間の連携や結束力が勝敗を左右する大きな要素となります。 協調性の高い選手は、チームをまとめ、全体のレベルアップに貢献できるのです。 個人競技でも、コーチや関係者との良好な関係は、選手の成長を支える土台になるでしょう。 協調性の高さは、スポーツにおける人間関係の円滑化に欠かせない性格特性だと言えます。
誠実性は努力を続ける原動力になる
誠実性の高さは、アスリートが努力を継続する上で重要な役割を果たすと考えられます。 今回の研究で、世界トップレベルの選手は、誠実性においても高い傾向が見られました。 誠実な選手は、以下のような資質を備えているのでしょう。
- 練習に対する真摯な姿勢と高い自己管理能力
- 目標に向けて着実に歩を進める計画性と忍耐力
- 規則を守り、フェアプレーを尊重するスポーツマンシップ
一流アスリートは、日々の地道な取り組みの積み重ねによって、高いパフォーマンスを実現しています。
誠実性は、そうした長期的な努力を支える重要な性格特性だと言えるでしょう。 また、ルールを守る誠実さは、アスリートに求められる倫理観の基盤にもなります。
誠実性の高さは、スポーツに打ち込む選手の姿勢や持続力に直結しているのかもしれません。
以上のように、本研究から、スポーツ選手の性格特性と競技パフォーマンスの関係性が浮き彫りになりました。
特に、神経症傾向の低さと、外向性・協調性・誠実性の高さが、チャンピオンクラスの選手に共通する特徴であることが示唆されました。
こうした知見は、アスリートの心理的側面に着目するスポーツ指導や、選手の育成・強化に役立てることができるでしょう。
今後は、性格特性を測定・分析し、個々の選手に合ったメンタルトレーニングを実践していくことが期待されます。
まとめ:スポーツ選手に必要な性格特性
神経質にならない精神の強さ
本研究から、スポーツ選手に求められる最も重要な性格特性は、神経症傾向の低さだと考えられます。
神経質にならない精神の強さは、以下のような点で競技力の向上に寄与するでしょう。
- 高いプレッシャーの中でも実力を発揮できる
- 試合中のアクシデントにも動じない冷静さを保てる
- コンディションの波に左右されない安定感がある
チャンピオンクラスの選手に共通していたのは、まさにこの神経症傾向の低さでした。
不安やストレスにも負けない強靭な精神力が、世界で活躍する選手の条件だと言えるでしょう。
社交的でポジティブな態度
外向性の高さも、スポーツ選手に望ましい性格の1つだと考えられます。
社交的でポジティブな態度は、以下のような形で選手の活躍を支えるのかもしれません。
- チームメイトとのコミュニケーションを活発にする
- 練習やトレーニングへの意欲を高く保つ
- 試合での積極的なプレーにつなげる
世界で活躍する選手の多くが、外向的な性格であることが示されました。
内向的な選手でも活躍する例はありますが、外向性を伸ばすことは、競技力アップの一助になるでしょう。
仲間と協力する協調性の高さ
協調性の高さは、特に団体競技で重要視される性格特性です。 仲間と協力する姿勢は、以下のような効果をもたらすと考えられます。
- チームの結束力を高める
- 全体のパフォーマンスを引き上げる
- 選手間の人間関係を円滑にする
調査の結果、トップレベルの選手は協調性においても高い傾向が見られました。
個人競技であっても、コーチや関係者との良好な関係は欠かせません。
協調性の高さは、スポーツ選手に必要不可欠な資質の1つだと言えるでしょう。
コツコツ努力を続ける誠実さ
誠実性も、スポーツ選手に求められる重要な性格特性です。 コツコツと努力を続ける誠実さは、以下のような形で選手の成長を支えます。
- 練習に真剣に取り組む姿勢を作る
- 目標達成に向けた計画的な行動を可能にする
- フェアプレーの精神を培う
世界で活躍する選手は、誠実性の点でも高い水準にあることが分かりました。
地道な努力を積み重ねる誠実な姿勢が、一流の競技力を支えているのです。
スポーツ選手には、真摯な取り組みを続ける誠実さが欠かせないでしょう。
最後に
本研究の知見は、スポーツ選手に求められる性格特性を明確に示すものでした。
神経質にならない精神力、社交的な態度、協調性の高さ、コツコツ努力を続ける誠実さ。 こうした特性を備えた選手を育成することが、競技力の向上につながると考えられます。
性格の分析とそれに基づくサポートは、スポーツ指導における重要な柱の1つになるかもしれません。
今後のスポーツ心理学の発展が期待されます。
※この記事は以下の本に掲載された論文を参考に執筆しています。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。