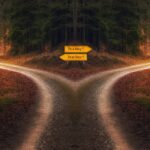心理療法は、心の問題を抱える人を助ける上で重要な役割を果たしています。
でも、心理療法にはもう一つの可能性があることをご存知でしょうか?実は、心理療法は性格特性を変化させる力を持っているのです。
性格は変わらないもの、と思っている人も多いかもしれません。
しかし、最近の研究では、心理療法によって性格特性が変化する可能性が示唆されているのです。
「A Systematic Review of Personality Trait Change Through Intervention」というタイトルの論文では、心理療法が性格特性に与える影響について、大規模なメタ分析(複数の研究を統合して分析する手法)が行われました。
この記事では、心理療法が性格特性にどのような影響を与えるのか、どのくらいの期間で変化が起こるのか、どんな種類の心理療法が効果的なのかなど、様々な角度から解説していきます。
また、心理療法による性格特性の変化が、自己理解や成長の機会につながる可能性についても探ります。
心理療法が性格を変えるって本当?そんな疑問を持ったあなた、ぜひこの記事を読んでみてください。
心理療法の新たな可能性に気づくきっかけになるかもしれません。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
心理療法とは?性格を変える可能性を秘めた治療法
心理療法の定義と目的
心の問題を抱える人に対して行われる治療法のことを心理療法と呼びます。
心理的な援助を通じて、以下のような目的を達成することを目指します。
- 症状の改善や軽減
- 適応力の向上
- 自己理解の促進
- 対人関係の改善
心理療法は、クライエントと治療者の協力的な関係性の中で行われます。
クライエントの思考、感情、行動のパターンを探索し、洞察を得ることで、
より適応的で柔軟な生き方を見つけていくことが目標となります。
心理療法は、心の問題の解決だけでなく、自己成長や人格的な発達も促すことができる、包括的なアプローチだと言えるでしょう。
心理療法にはどんな種類があるの?
様々な種類の心理療法がありますが、代表的なものを以下に紹介します。
- 精神分析療法
- 認知行動療法(CBT)
- クライエント中心療法
- ゲシュタルト療法
- 家族療法
- グループ療法
それぞれの療法は、独自の理論的背景と技法を持っています。
しかし、いずれの療法も、クライエントの主体性を尊重し、自己理解と成長を促進することを目的としている点では共通しています。
個々のクライエントのニーズや特性に応じて、適切な療法が選択され、柔軟に適用されることが重要です。
心理療法は多様なアプローチを包含する、幅広い治療法だと言えるでしょう。
性格特性とは何か
性格特性とは、個人の行動や思考、感情の一貫したパターンのことを指します。
以下のような特徴があります。
- 比較的安定している
- 状況を超えて一貫している
- 個人を特徴づける
性格特性は、以下の5つの次元で捉えられることが多いです。ビッグファイブと呼ばれます。
- 開放性
- 誠実性
- 外向性
- 協調性
- 神経症傾向
これらの特性は、遺伝と環境の相互作用によって形成されると考えられています。
性格特性は、個人の行動を予測し、理解するための重要な手がかりとなります。
ただし、性格特性は絶対的なものではなく、状況や発達段階によって変化する可能性もあることを忘れてはいけません。
心理療法は性格特性にどのような影響を与えるの?
情動安定性(神経症傾向)への影響
心理療法は、情動安定性の向上に最も大きな影響を与えることが示されています。
情動安定性は、ストレスへの耐性や情動調整能力を表す性格特性です。
以下のような変化が報告されています。
- ネガティブな感情の減少
- ストレス対処能力の向上
- 情動調整能力の改善
特に、認知行動療法(CBT)や精神力動的療法が、
情動安定性の向上に効果的であることが示唆されています。
これらの療法では、以下のようなアプローチがとられます。
- ネガティブな思考パターンの修正
- 感情の探索と洞察
- 適応的な対処スキルの習得
情動安定性の向上は、心理的健康や適応力の改善につながると考えられます。
心理療法は、情動安定性の向上を通して、クライエントのレジリエンスを高める可能性があるでしょう。
外向性への影響
心理療法は、外向性にも一定の影響を与えることが報告されています。
外向性は、社交性や積極性、活動性などを表す性格特性です。
以下のような変化が見られることがあります。
- 社交的な行動の増加
- 自己表現の向上
- 積極的な活動への参加
ただし、外向性への影響は、情動安定性ほど大きくはないようです。
外向性は、環境との相互作用から影響を受けやすい特性だと考えられています。
心理療法では、以下のような要因が外向性の変化に寄与する可能性があります。
- 自己理解の深まり
- 対人関係スキルの向上
- 自信の向上
外向性の適度な向上は、社会適応や人生満足度の向上につながるかもしれません。
ただし、個人差が大きいため、一概に心理療法が外向性を変化させるとは言えません。
クライエントの特性や目標に応じて、柔軟にアプローチすることが大切です。
誠実性への影響
心理療法は、誠実性にもある程度の影響を与える可能性があります。
誠実性は、目標指向性や自制心、責任感などを表す性格特性です。
以下のような変化が報告されています。
- 目標への取り組みの向上
- 自己規律の強化
- 責任感の向上
ただし、誠実性への影響は、情動安定性や外向性ほど顕著ではないようです。
誠実性は、遺伝的要因の影響が比較的大きい特性だと考えられています。
心理療法では、以下のような要因が誠実性の変化に寄与する可能性があります。
- 自己効力感の向上
- 目標設定スキルの習得
- 自己コントロール能力の強化
誠実性の向上は、目標達成や社会適応、人生満足度の向上につながるかもしれません。
ただし、心理療法が誠実性に与える影響については、さらなる研究が必要とされています。
クライエントの特性や目標に応じて、誠実性の向上を促すアプローチを検討することが大切です。
開放性への影響
心理療法が開放性に与える影響については、一定の見解が得られていません。
開放性は、新奇性の追求や知的好奇心、想像力などを表す性格特性です。
一部の研究では、以下のような変化が報告されています。
- 新しい経験への積極性の向上
- 創造性の向上
- 柔軟性の向上
ただし、開放性への影響は、他の性格特性ほど一貫した結果が得られていません。
開放性は、遺伝的要因の影響が比較的大きい特性だと考えられています。
心理療法では、以下のような要因が開放性の変化に寄与する可能性があります。
- 自己探索の促進
- 新しい視点の獲得
- 創造的な表現の奨励
開放性の向上は、適応力や人生満足度の向上につながるかもしれません。
ただし、心理療法が開放性に与える影響については、さらなる研究が必要とされています。
クライエントの特性や目標に応じて、開放性の向上を促すアプローチを検討することが大切です。
協調性への影響
心理療法は、協調性にもある程度の影響を与える可能性があります。
協調性は、共感性や利他性、調和性などを表す性格特性です。
以下のような変化が報告されています。
- 他者への理解の深まり
- 協力的な行動の増加
- 対人関係の調和性の向上
ただし、協調性への影響は、情動安定性や外向性ほど顕著ではないようです。
協調性は、環境との相互作用から影響を受けやすい特性だと考えられています。
心理療法では、以下のような要因が協調性の変化に寄与する可能性があります。
- 共感性の向上
- コミュニケーションスキルの習得
- 対人関係の洞察の深まり
協調性の向上は、対人関係の質の向上や社会適応、人生満足度の向上につながるかもしれません。
ただし、心理療法が協調性に与える影響については、さらなる研究が必要とされています。
クライエントの特性や目標に応じて、協調性の向上を促すアプローチを検討することが大切です。
心理療法による性格特性の変化の程度
情動安定性の変化の大きさ
心理療法による情動安定性の変化は、他の性格特性と比べて最も大きいことが示されています。
メタ分析の結果では、以下のような効果量が報告されています。
- プレポスト変化スコア:d = .57
- 真の実験での効果量:d = .69
これらの効果量は、中程度から大きい変化を示しています。
情動安定性の変化は、以下のような要因によって影響を受ける可能性があります。
- 治療法の種類
- 治療期間
- クライエントの特性
特に、認知行動療法(CBT)や精神力動的療法が、情動安定性の向上に効果的であることが示唆されています。
また、治療期間が長いほど、変化が大きくなる傾向があります。
情動安定性の変化は、心理的健康や適応力の改善につながると考えられます。
心理療法は、情動安定性の向上を通して、クライエントのレジリエンスを高める可能性があるでしょう。
外向性の変化の大きさ
心理療法による外向性の変化は、情動安定性ほどではありませんが、一定の効果が報告されています。
メタ分析の結果では、以下のような効果量が報告されています。
- プレポスト変化スコア:d = .23
- 真の実験での効果量:d = .38
これらの効果量は、小から中程度の変化を示しています。
外向性の変化は、以下のような要因によって影響を受ける可能性があります。
- 治療法の種類
- クライエントの特性
- 環境要因
外向性は、環境との相互作用から影響を受けやすい特性だと考えられています。
心理療法では、自己理解の深まりや対人関係スキルの向上が、外向性の変化に寄与する可能性があります。
ただし、個人差が大きいため、一概に心理療法が外向性を変化させるとは言えません。
外向性の適度な向上は、社会適応や人生満足度の向上につながるかもしれません。
クライエントの特性や目標に応じて、柔軟にアプローチすることが大切です。
誠実性、開放性、協調性の変化の大きさ
心理療法による誠実性、開放性、協調性の変化は、情動安定性や外向性ほど顕著ではありません。
メタ分析の結果では、以下のような効果量が報告されています。
- 誠実性のプレポスト変化スコア:d = .19
- 開放性のプレポスト変化スコア:d = .13
- 協調性のプレポスト変化スコア:d = .15
これらの効果量は、小さな変化を示しています。
ただし、真の実験での効果量は報告されていないため、
因果関係を断定することは難しいでしょう。
これらの性格特性の変化は、以下のような要因によって影響を受ける可能性があります。
- 遺伝的要因
- 環境要因
- 治療法の種類
心理療法では、自己理解の深まりや対人関係スキルの向上、目標設定スキルの習得などが、これらの性格特性の変化に寄与する可能性があります。
ただし、心理療法がこれらの性格特性に与える影響については、さらなる研究が必要とされています。
クライエントの特性や目標に応じて、これらの性格特性の向上を促すアプローチを検討することが大切です。
どのくらいの期間で性格特性は変化するの?
短期的な変化と長期的な変化
心理療法による性格特性の変化は、短期的にも長期的にも見られることが報告されています。
メタ分析の結果では、以下のような知見が得られています。
- 治療終了直後の効果量:d = .34
- 6ヶ月後の効果量:d = .48
- 1年以上経過後の効果量:d = .37
これらの結果は、心理療法による性格特性の変化が、
短期的にも長期的にも維持される可能性を示唆しています。
ただし、効果量の大きさは時間経過とともに変動しており、一貫した増加傾向は見られていません。
性格特性の変化には、以下のような要因が影響を与える可能性があります。
- 治療法の種類
- 治療期間
- フォローアップ期間
- クライエントの特性
短期的な変化は、治療中の学習や洞察の影響を受けやすいと考えられます。
一方、長期的な変化は、治療後の環境要因や個人の適応過程の影響を受けやすいでしょう。
心理療法による性格特性の変化は、短期的にも長期的にも見られる可能性がありますが、
時間経過による効果量の変動には注意が必要です。
治療終了後のフォローアップを行うことで、長期的な変化のプロセスを明らかにすることができるかもしれません。
性格特性の変化が持続する期間
心理療法による性格特性の変化は、治療終了後も長期的に持続する可能性があります。
メタ分析の結果では、以下のような知見が得られています。
- 6ヶ月後の効果量:d = .48
- 1年以上経過後の効果量:d = .37
これらの結果は、心理療法による性格特性の変化が、
治療終了後も長期的に維持される可能性を示唆しています。
特に、情動安定性の変化は、1年以上経過後も大きな効果量を示しています。
性格特性の変化が持続する期間は、以下のような要因によって影響を受ける可能性があります。
- 治療法の種類
- 治療期間
- クライエントの特性
- 環境要因
心理療法で得られた学習や洞察を日常生活に活かし続けることが、変化の持続につながると考えられます。
また、治療後のフォローアップや継続的なサポートが、変化の維持に寄与する可能性があります。
ただし、性格特性の変化が持続する期間については、さらなる長期的な研究が必要とされています。
心理療法による性格特性の変化は、治療終了後も長期的に持続する可能性がありますが、
個人差や環境要因の影響を考慮する必要があります。
どんな心理療法が性格特性の変化に効果的?
認知行動療法(CBT)の効果
認知行動療法(CBT)は、性格特性の変化に効果的であることが示唆されています。
メタ分析の結果では、以下のような知見が得られています。
- CBTによる情動安定性の変化:d = .73
- CBTによる外向性の変化:d = .46
これらの効果量は、中程度から大きい変化を示しています。
CBTは、以下のような特徴を持つ心理療法です。
- 認知(思考)と行動に焦点を当てる
- 現在の問題に取り組む
- 構造化されたアプローチ
- エビデンスに基づく技法の活用
CBTでは、ネガティブな思考パターンの同定と修正、適応的な行動の習得などを通して、性格特性の変化を促すと考えられています。
特に、情動安定性の向上に対するCBTの効果は顕著です。
ストレス対処能力の向上や感情調整能力の改善が、情動安定性の変化に寄与している可能性があります。
また、CBTは比較的短期間で効果が得られやすく、費用対効果の高い治療法だと考えられています。
認知行動療法(CBT)は、エビデンスに基づく効果的な心理療法であり、性格特性、特に情動安定性の変化に寄与する可能性が高いと言えるでしょう。
サポーティブセラピーの効果
サポーティブセラピーは、性格特性の変化に一定の効果を持つことが示唆されています。
メタ分析の結果では、以下のような知見が得られています。
- サポーティブセラピーによる情動安定性の変化:d = .68
この効果量は、中程度から大きい変化を示しています。
サポーティブセラピーは、以下のような特徴を持つ心理療法です。
- 共感的な治療者-クライエント関係の重視
- クライエントの感情表出の促進
- 現実検討力の向上
- 対処能力の向上
サポーティブセラピーでは、治療者との信頼関係を基盤として、クライエントの感情を受け止め、現実適応力を高めることが目指されます。
このような関係性や感情表出の促進が、情動安定性の変化に寄与している可能性があります。
ただし、サポーティブセラピーの効果は、治療者の資質や技法によって影響を受けやすいと考えられています。
また、長期的な効果については、さらなる研究が必要とされています。
サポーティブセラピーは、治療者との関係性を重視する心理療法であり、性格特性、特に情動安定性の変化に一定の効果を持つ可能性があります。
ただし、治療者の資質や技法の影響を考慮する必要があるでしょう。
精神力動的療法の効果
精神力動的療法は、性格特性の変化に一定の効果を持つことが示唆されています。
メタ分析の結果では、以下のような知見が得られています。
- 精神力動的療法による情動安定性の変化:d = .49
この効果量は、中程度の変化を示しています。
精神力動的療法は、以下のような特徴を持つ心理療法です。
- 無意識の葛藤や防衛機制に焦点を当てる
- 過去の経験や対人関係パターンを探る
- 洞察の獲得を重視する
- 長期的なアプローチが多い
精神力動的療法では、無意識の心理的葛藤を意識化し、洞察を得ることで、性格特性の変化を促すと考えられています。
特に、情動安定性の向上に対する効果が示唆されています。
感情の探索や対人関係パターンの理解が、情動調整能力の改善に寄与している可能性があります。
ただし、精神力動的療法は長期的なアプローチが多く、効果の現れ方には個人差が大きいと考えられています。
また、治療者の資質や技法によって効果が左右される可能性があります。
精神力動的療法は、無意識の心理的葛藤に焦点を当てる心理療法であり、性格特性、特に情動安定性の変化に一定の効果を持つ可能性があります。
ただし、長期的なアプローチが必要であり、治療者の資質や技法の影響を考慮する必要があるでしょう。
マインドフルネス療法の効果
マインドフルネス療法は、性格特性の変化に一定の効果を持つ可能性が示唆されています。
ただし、メタ分析では直接的な効果量は報告されていません。
マインドフルネス療法は、以下のような特徴を持つ心理療法です。
- 今ここでの体験への気づきを重視する
- 評価や判断を保留する態度を養う
- セルフコンパッションを育む
- 瞑想やボディスキャンなどの技法を用いる
マインドフルネス療法では、今の瞬間の体験に意図的に注意を向け、評価や判断を保留することで、柔軟で適応的な態度を養うことが目指されます。
このような態度の変化が、性格特性、特に情動安定性や開放性の変化に寄与する可能性があります。
また、セルフコンパッションを育むことで、
自己受容や自己理解が深まり、性格特性の変化が促される可能性もあります。
ただし、マインドフルネス療法の性格特性への効果については、さらなる研究の蓄積が必要とされています。
また、個人の特性や適性によって、効果に差が生じる可能性があります。
マインドフルネス療法は、今ここでの体験への気づきを重視する心理療法であり、性格特性、特に情動安定性や開放性の変化に寄与する可能性があります。
ただし、効果については今後のさらなる研究の蓄積が必要とされています。
対人関係療法(IPT)の効果
対人関係療法(IPT)は、性格特性の変化に一定の効果を持つ可能性が示唆されています。
ただし、メタ分析では直接的な効果量は報告されていません。
IPTは、以下のような特徴を持つ心理療法です。
- 対人関係の問題に焦点を当てる
- 現在の対人関係パターンを探る
- コミュニケーションスキルの向上を目指す
- 比較的短期間で終結する
IPTでは、対人関係の問題が症状の発生や維持に関与していると考え、現在の対人関係パターンを探ることで、適応的な関係性の構築を目指します。
このようなアプローチが、性格特性、特に外向性や協調性の変化に寄与する可能性があります。
また、コミュニケーションスキルの向上や対人関係の改善が、社会適応力や自己効力感の向上につながり、性格特性の変化を促す可能性もあります。
ただし、IPTの性格特性への効果については、さらなる研究の蓄積が必要とされています。
また、個人の特性や対人関係の問題の性質によって、効果に差が生じる可能性があります。
対人関係療法(IPT)は、対人関係の問題に焦点を当てる心理療法であり、
性格特性、特に外向性や協調性の変化に寄与する可能性があります。
ただし、効果については今後のさらなる研究の蓄積が必要とされています。
心理療法は性格特性を本当に変えられるの?
研究デザインと因果関係の問題
心理療法が性格特性を変化させるという因果関係を確実に示すためには、研究デザインの工夫が必要です。
メタ分析では、以下のような研究デザインの問題点が指摘されています。
- 無作為化比較試験(RCT)の不足
- 対照群の設定の困難さ
- プラセボ効果の影響
- 交絡要因の統制の難しさ
心理療法の効果を検証するためには、
RCTによる厳密な比較が理想的ですが、現実には倫理的な問題などから、RCTの実施が困難な場合が多いのが実情です。
また、心理療法の効果は、治療者とクライエントの関係性や、クライエントの期待や動機づけなどの要因によって影響を受けやすく、プラセボ効果の影響を排除することが難しいという問題もあります。
さらに、性格特性の変化には、治療以外の様々な要因が関与している可能性があり、これらの交絡要因を十分に統制することは容易ではありません。
このような研究デザイン上の限界から、心理療法と性格特性の変化の因果関係を確実に示すことは難しいと言えます。
ただし、メタ分析の結果は、心理療法が性格特性に一定の影響を与えている可能性を示唆しており、今後のさらなる研究の蓄積が期待されます。
心理療法が性格特性を変化させるという因果関係を確実に示すためには、研究デザインの工夫が必要であり、現状では限界があると言えます。
ただし、メタ分析の結果は、心理療法の効果の可能性を示唆しています。
性格特性の変化と治療効果の関係性
性格特性の変化と心理療法の治療効果の関係性については、さらなる研究が必要とされています。
メタ分析では、以下のような可能性が示唆されています。
- 性格特性の変化が治療効果を媒介する可能性
- 治療効果が性格特性の変化をもたらす可能性
- 性格特性の変化と治療効果が相互に影響し合う可能性
性格特性の変化が、心理的症状の改善や適応力の向上といった治療効果を媒介している可能性があります。
例えば、情動安定性の向上が、抑うつ症状の改善につながるというプロセスが考えられます。
一方、心理療法によって症状が改善することで、性格特性の変化が促される可能性もあります。
適応的な行動パターンの獲得や自己効力感の向上などが、性格特性の変化に寄与するというプロセスが考えられます。
また、性格特性の変化と治療効果が相互に影響し合う可能性も指摘されています。
例えば、外向性の向上が対人関係の改善につながり、それがさらなる外向性の向上を促すという循環的なプロセスが考えられます。
まとめ:心理療法で性格を変えるために
自分に合った心理療法を見つける重要性
性格特性の変化を目指すためには、自分に合った心理療法を見つけることが重要です。
以下のようなポイントを考慮すると良いでしょう。
- 自分の性格特性や問題の特徴を理解する
- 治療法の特徴やアプローチを知る
- 治療者との相性を重視する
- 自分の目標や期待を明確にする
性格特性の変化を目指す際には、まず自分の性格特性や問題の特徴を理解することが大切です。
その上で、各療法の特徴やアプローチを知り、自分に合ったものを選ぶことが重要になります。
また、心理療法では治療者との関係性が重要な役割を果たすため、治療者との相性を重視することも大切です。
自分の目標や期待を明確にし、治療者と共有することで、より効果的な治療が可能になると考えられます。
心理療法は、個人の特性や問題に応じて柔軟に適用される必要があります。
自分に合った心理療法を見つけるためには、十分な情報収集とコミュニケーションが不可欠だと言えるでしょう。
性格特性の変化を目指すためには、自分に合った心理療法を見つけることが重要であり、そのためには自己理解と治療者とのコミュニケーションが欠かせません。
個人の特性や目標に応じた柔軟な治療の選択が求められます。
性格特性の変化は自己理解と成長の機会
性格特性の変化は、自己理解と成長の機会をもたらす可能性があります。
以下のような観点から、性格特性の変化を捉えることができるでしょう。
- 自分の傾向や特徴を知る機会になる
- 適応的な変化を通して、成長につながる
- 新たな可能性や選択肢に気づくことができる
- 人生の意味や価値観を見つめ直すきっかけになる
心理療法を通して性格特性の変化を経験することは、自分自身の傾向や特徴を知る貴重な機会になります。
客観的なフィードバックを受けることで、自己理解が深まり、新たな気づきが得られるでしょう。
また、適応的な変化を通して、よりよい生き方や人生観の獲得につながる可能性があります。
性格特性の変化は、新たな可能性や選択肢に気づくきっかけにもなります。
今までと異なる行動や考え方を試すことで、自分の可能性を広げることができるかもしれません。
心理療法を通して、自分自身と向き合い、よりよい生き方を探求することが、性格特性の変化の真の意義だと言えるでしょう。
※本記事はこちらの本に記載されていた論文を取り上げました。ぜひ読んでみてください。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。