プロパガンダという言葉を聞いたことはありますか?
それは、人々の考えや行動をある方向に誘導するための情報のことです。
ニュースやSNSでも、気づかないうちに似たような影響を受けているかもしれません。
でも、すべての人が同じように流されるわけではありません。
実は、「どこに住んでいるか」や「もともとの考え方」によって、効果がまったく違うのです。
今回紹介する論文『Radio and the Rise of the Nazis in Prewar Germany』では、ナチスがラジオを使ってプロパガンダを広めたとき、どんな地域で効果が強く出たのかを詳しく調べています。
この記事では、その研究をもとに、プロパガンダの力は本当にどこでも同じように働くのか?という疑問に答えていきます。
歴史の中の本当の出来事から、今の情報社会で生きる私たちが学べることを、わかりやすく解説します。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※以下のHEXACO-JP診断は個人向けになります。サンブレイズテストは法人向けになります。

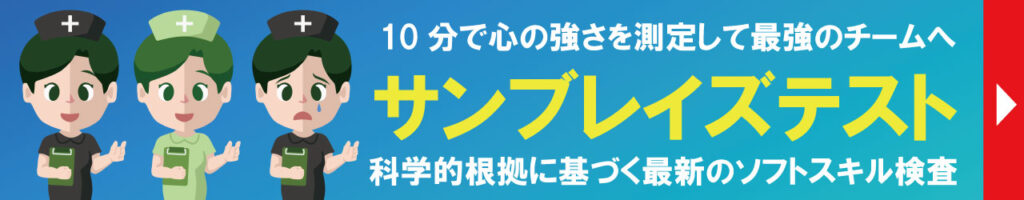
プロパガンダの影響はどこでも同じじゃない
ナチスが信じたプロパガンダの力とは
ナチスはプロパガンダを政治の武器として使いました。
当時の宣伝大臣だった人物は「ラジオがなければ政権は取れなかった」と発言しています。
つまり、国民に向けた情報の出し方が重要だったのです。
特にラジオは家で簡単に聞けるので、多くの人に影響しました。
当時は新聞よりもラジオのほうが早くて広く伝わったのです。
たとえば1933年3月の選挙では、放送が始まってわずか5週間でナチスの得票率が2.9ポイント上がりました。
これはプロパガンダの力の大きさを示しています。
ナチスは敵の考えを否定し、自分たちの正しさを繰り返し伝えました。
その結果、人々の心に自分たちの言葉を染み込ませることができたのです。
まとめると、ラジオという手段を使ったプロパガンダは、人々の考え方や行動に大きな影響を与えました。
民主主義下のプロパガンダは抑止力になった
ラジオは最初、ナチスの支持を減らす働きをしました。
1929年から1932年までは政府がラジオを使って民主的な考えを伝えていました。
この時期、ナチスや共産党などの過激な政党には放送が許されませんでした。
そのかわり、政府寄りの安定した意見がラジオから流れました。
たとえば1930年の選挙では、ラジオが聞ける地域ほどナチスの得票率が下がっています。
逆にラジオが届かない場所では、ナチスが多く票を集めました。
このように、メディアの内容が過激な意見の広がりを防いだのです。
放送の主な内容は以下のようなものでした。
- 政府の政策を分かりやすく説明
- 極端な意見の危険性を伝える
- 選挙での冷静な判断を呼びかける
結果として、民主主義の価値を守るために、プロパガンダは一時的に役立っていました。
ヒトラー就任後にラジオの内容が一変した
1933年1月にヒトラーが首相になった直後、ラジオの内容は大きく変わりました。
これまで登場しなかったナチスの政治家が、放送に出始めました。
特にヒトラー自身が5週間で16回もラジオで話したのです。
その間、他の政党の出演はほとんどありませんでした。
つまり、ナチスの言葉だけが国民の耳に届くようになったのです。
この偏った放送は、国民の意見を一方向に誘導しました。
さらに政府は、次のような動きを取りました。
- すべてのラジオ会社を国の管理下に置く
- 政府に不都合な内容を禁止する
- ナチスの考えだけを繰り返す
こうして、ラジオは自由な情報源から、ナチスの宣伝装置に変わってしまいました。
たった5週間で選挙結果が変わった理由
ヒトラー就任後のラジオ放送は、短期間で選挙結果を動かしました。
1933年3月の選挙では、ナチスが43.9%の得票を記録しました。
前年の選挙から約4か月で約10ポイントの伸びです。
これは、暴力や弾圧だけでなく、プロパガンダの影響が大きかったと考えられています。
ラジオを通じて、政府は次のようなメッセージを繰り返しました。
- 共産主義の脅威を強調する
- 国の未来はナチスにしか任せられない
- 国民の不安に答えるふりをする
こうした言葉は、特に不安を感じていた貧しい人々の心に届きました。
一方で、ラジオを持っていない人も多く、情報が限られていたのも事実です。
それでも、短期間で選挙の流れを変えた背景には、ラジオによるプロパガンダの力がありました。
政治的メッセージの効果に地域差があった
ラジオの影響は、すべての地域で同じではありませんでした。
ある地域ではプロパガンダの効果が強く、別の地域では逆効果になったこともあります。
その違いには、もともとの考え方や歴史が関係していました。
たとえば次のような点が重要でした。
- 昔から反ユダヤ的な事件が起きていたか
- 極右の考え方がすでに支持されていたか
- 貧富の差が大きく、社会の不満が強いか
これらの要素がそろっていると、プロパガンダは強く働きました。
一方、ユダヤ人と共存していた地域では、ナチスの言葉に疑いを持つ人が多かったのです。
つまり、聞き手の考え方次第で、同じ放送でもまったく違う反応が生まれたのです。
そのため、プロパガンダの力は一方的なものではなく、地域や歴史に深く関わっていたといえます。
プロパガンダが効いたのはどんな地域?
歴史的に反ユダヤ感情が強かった場所
もともとユダヤ人への差別が根強かった地域では、プロパガンダが強く効きました。
この研究では、14世紀の黒死病のころにユダヤ人迫害があった地域を調べました。
こうした土地では、ナチスの反ユダヤ放送に人々が反応しやすかったのです。
たとえば、ユダヤ人を警察に通報したり、手紙で悪口を書いたりする人が増えました。
放送はあくまできっかけで、もともとの気持ちが火をつけたのです。
このような地域では、次のような特徴が見られました。
- 長い間ユダヤ人に対する偏見が続いていた
- 地元の文化や学校で反ユダヤ的な考えが広まっていた
- ユダヤ人と関わる機会が少なく、理解が進んでいなかった
その結果、ナチスのプロパガンダは「新しい意見」ではなく、「前からある考え」を強める働きをしたのです。
極右政党への支持が高かった地域
ナチスと似た考えを持つ政党が強かった地域では、プロパガンダの効果が大きくなりました。
1924年にはナチスが一時的に禁止されたため、「国民社会主義自由党」という代わりの政党が活動しました。
この政党に多くの票が集まった地域では、のちにナチスが支持されやすくなりました。
つまり、考え方が近い人が多い場所では、プロパガンダに共感しやすかったのです。
具体的には以下のような内容が響きました。
- 国の力を強くすべきという考え
- 外国や少数派に対する不満
- 指導者に従うことを重んじる空気
これらがすでに広がっていた地域では、ナチスの放送が「正しい」と感じられたのです。
そのため、プロパガンダはただの情報ではなく、もともとの気持ちを後押しする道具になっていました。
経済的不平等が大きい地域ほど影響が強かった
お金持ちと貧しい人の差が激しい地域では、ナチスのプロパガンダがより影響を与えました。
研究では、土地の持ち主の分布を使って不平等を測りました。
結果、不満を抱えた人が多い場所ほど、ラジオの内容に強く反応していました。
とくに仕事がない人や生活が苦しい人は、敵をつくる話に納得しやすかったのです。
ナチスの放送はこのような気持ちを利用しました。
- 社会が悪いのはユダヤ人のせいだ
- 今の政治では生活は変わらない
- ナチスに従えば未来はよくなる
こうしたメッセージは、苦しい状況にある人の心をとらえました。
そのため、不平等の大きな地域では、プロパガンダが特に強く効いたのです。
過去のユダヤ人迫害の記録があった地域
過去にユダヤ人への攻撃があった土地では、再び同じ行動が起こりやすくなりました。
論文では、何百年も前の記録が今の行動に影響することが示されています。
たとえば、黒死病のときにユダヤ人が攻撃された地域では、ナチス時代にも差別が激しくなりました。
これは、家族や地域に伝わる考え方が変わっていなかったためです。
プロパガンダはそうした「伝統的な考え」を目覚めさせる役割を果たしました。
以下のような言葉が繰り返されました。
- 昔からユダヤ人は信用できない
- ドイツの問題は彼らのせいだ
- 昔と同じように行動すべきだ
そのため、過去の歴史が今の行動に結びつくという、怖い現象が起きていたのです。
1933年以降、反ユダヤ行動が増えた背景
ヒトラー政権がラジオを使って反ユダヤ感情を広げると、実際の行動が目に見えて増えました。
ユダヤ人の店を壊したり、警察に通報したりする人が増えたのです。
特に1935年から1938年にかけて、その数は大きく伸びました。
これは、放送が具体的な行動をうながす内容になったからです。
たとえば、ラジオでは次のような話が流されました。
- ユダヤ人を見たら通報しよう
- 彼らを相手に商売してはいけない
- 血を守るために距離を取ろう
また、新聞「シュトゥルマー」に寄せられた反ユダヤの手紙も増加しました。
つまり、プロパガンダが感情だけでなく、行動にも影響を与えたのです。
プロパガンダが逆効果になった地域もある
反ユダヤ感情が低かった場所では反発も
ナチスのプロパガンダが逆に反感を買う地域もありました。
とくに反ユダヤの考えがあまりなかった場所では、その内容に疑問を持つ人が多かったのです。
ユダヤ人と日常的に接していた地域では、極端な話に納得できなかったのです。
たとえば、ユダヤ人の店で買い物をしていた人たちは、急に敵視するようにはなりませんでした。
プロパガンダの内容と生活の実感が合っていなかったのです。
このような地域では、以下のような特徴がありました。
- ユダヤ人との関係が日常にあった
- 地元で信頼されているユダヤ人がいた
- ナチスの言葉に違和感を持つ人が多かった
そのため、プロパガンダが効果を持つどころか、かえって信用を失う原因にもなったのです。
住民の価値観とメッセージが合わなかった場合
放送内容と地域の人々の考えが合わないと、プロパガンダの効果は出ませんでした。
ナチスの放送はとても一方的で、反論や意見の違いを認めませんでした。
しかし、地域によっては多様な価値観がありました。
たとえば、信仰や教育の影響で、差別に反対する考えが強い場所もあったのです。
そのような場所では、ナチスの放送が「押しつけ」に感じられました。
プロパガンダの内容が次のように受け止められました。
- 不自然で無理のある話に聞こえた
- 他人を悪く言うことへの不快感が強かった
- 争いよりも共存を重んじる文化があった
こうした違いが、プロパガンダの成功を妨げる要因になっていました。
ラジオが反感を呼んだケースの紹介
ラジオ放送そのものが嫌われることもありました。
内容が一方的すぎて、不快に感じた人がいたのです。
ある地域では、放送中にラジオの電源を切る人が多かったことも記録されています。
また、特定の民族や宗教を攻撃する話ばかりで、聞いていてつらくなる人もいたのです。
このような状況は次のような要素で起こりました。
- 内容があまりに極端で過激だった
- 日常と合わない話が続いた
- ほかの情報源がなく、自由な選択ができなかった
その結果、ラジオが信用されず、かえってナチスへの疑いが深まった地域もありました。
ナチスに協力しない動きが生まれた背景
一部の地域では、放送に流されずナチスに協力しない人々もいました。
このような地域では、地域全体が一つの価値観でまとまっていたわけではありません。
いろいろな考えが共存しており、すぐには動かされなかったのです。
とくに教育を受けた人や、宗教的な理由から平和を重んじる人は、冷静に状況を見ていました。
また、ユダヤ人の知人や家族を守ろうとした人もいました。
協力しなかった理由としては、以下が考えられます。
- 一方的な話に疑問を感じた
- 昔からの友人や仲間を信じていた
- 自分の意志で行動したかった
そのため、すべての人がプロパガンダに流されたわけではなかったのです。
プロパガンダが信頼を失う危険性
プロパガンダは、使い方を間違えると信頼をなくします。
放送内容が嘘っぽかったり、現実と合わなかったりすると、かえって人々は疑い始めます。
ナチスの放送も、すべての人に効果があったわけではありません。
とくに、生活でユダヤ人と交流があった人は、放送の内容を信じませんでした。
さらに、過激な言葉を繰り返すことで、疲れてしまった人もいたのです。
このような放送は、次のような反応を生みました。
- 「またか」と思って聞かなくなる
- 友人や家族と内容を疑うようになる
- 情報そのものを避けるようになる
結果として、プロパガンダが逆効果になることもありました。
プロパガンダの歴史から学べること
ラジオは思想を広げる「道具」だった
ラジオは情報を広く早く伝える力を持っていました。
ナチスはその力に目をつけ、国民の考え方を変えるために使いました。
ラジオを使えば、読み書きが苦手な人にも情報を届けられます。
また、家にいながら話を聞けるので、影響を受けやすくなります。
そのため、ナチスは特にラジオを重視しました。
1933年にはすでに500万台以上のラジオが家庭にありました。
1934年には、すべてのラジオ局が国に支配されました。
このように、ラジオは「便利な道具」から「思想の武器」へと変わったのです。
放送内容の例としては、以下のようなものがあります。
- ナチスの考え方や政策の紹介
- 敵とされる人々への批判
- ヒトラーの演説を繰り返し流す
こうしてラジオは、ただの家電ではなく、国の考えを広める道具として使われました。
情報の発信者が誰かがカギを握る
情報を誰が発信しているかで、内容の受け止め方は変わります。
ナチスは、放送局を国の支配下に置き、自分たちに都合のよい情報だけを流しました。
それにより、国民は他の意見を聞けなくなったのです。
たとえば、反対の立場の政党や市民団体の声は、まったく紹介されませんでした。
つまり、情報の流れが一方通行になっていたのです。
これは非常に危険な状態です。
以下のような状況が起こりました。
- 国民が「正しい意見はひとつ」と思い込む
- 他の意見がないことで疑う力が弱まる
- 発信者に逆らう空気が強まる
このように、情報の「中身」だけでなく、「誰が言っているか」がとても重要なのです。
メディアの中立性が崩れると何が起きるか
メディアが一つの考えだけを伝えると、社会は偏ります。
本来、メディアはさまざまな意見を公平に紹介するものです。
しかし、ナチス政権下ではその役割が失われました。
政府の考えだけが正しいとされ、他の意見は無視されました。
その結果、反対する人が声を上げにくくなったのです。
さらに、多くの人が知らないうちに影響を受けました。
中立性が失われると、次のような問題が起こります。
- 偏った考えが当たり前になる
- 少数派や異なる意見が排除される
- 国民の判断力が弱くなる
このように、メディアが一方的になると、自由な社会は崩れていくのです。
過去の事例をもとに現在を見直す
歴史をふり返ることで、今の情報の受け止め方を考えることができます。
ナチス時代のように、情報が偏ると社会に危険が生まれます。
今も私たちは、さまざまな情報に囲まれて生きています。
その中には、事実と違うものや、意図的に作られた話もあります。
だからこそ、情報にふれるときには「本当かな?」と考えることが大切です。
たとえば、こんなことを意識するとよいでしょう。
- その情報はどこから来たのか?
- 他の意見もあるか調べてみる
- 自分の考えに合っているか確認する
歴史を学ぶことで、今の行動をよりよいものに変えることができます。
私たちはどのように情報と向き合うべきか
プロパガンダの歴史は、情報の受け取り方の大切さを教えてくれます。
一方的な意見を信じすぎないようにすることが重要です。
また、まわりが同じ意見でも、自分で考える力を持ちましょう。
特に不安なときほど、偏った話に流されやすくなります。
情報に対して疑う心を持つことは、悪いことではありません。
むしろ、自分を守るために必要な力です。
以下のような行動が役立ちます。
- 一度立ち止まって考えてみる
- 友達や家族と話し合ってみる
- 違う立場の人の話も聞いてみる
こうして、自分の判断で行動できる人が増えれば、社会全体もより自由で安全になります。
最後に
この記事では、ナチス時代のドイツで使われたプロパガンダが、すべての地域で同じように効いたわけではないことを紹介しました。
実際には、もともと反ユダヤ的な考えが強かった場所や、極右に親しみのある地域、経済的な不満がたまっていた地域で、特に大きな影響が見られました。
一方で、そうではない地域では逆に反発されたこともあります。
つまり、情報の力は強いけれど、それを受け取る人の気持ちや背景によって、効果が大きく変わるのです。
これは現代にも当てはまる話です。
スマートフォンやSNSを通して、私たちは毎日たくさんの情報にふれています。
その中には、知らないうちに気持ちを動かされるようなものもあります。
だからこそ、「これって本当?」「自分で考えているかな?」と立ち止まることが大切です。
過去の出来事から学び、情報と上手につきあっていく力を身につけましょう。
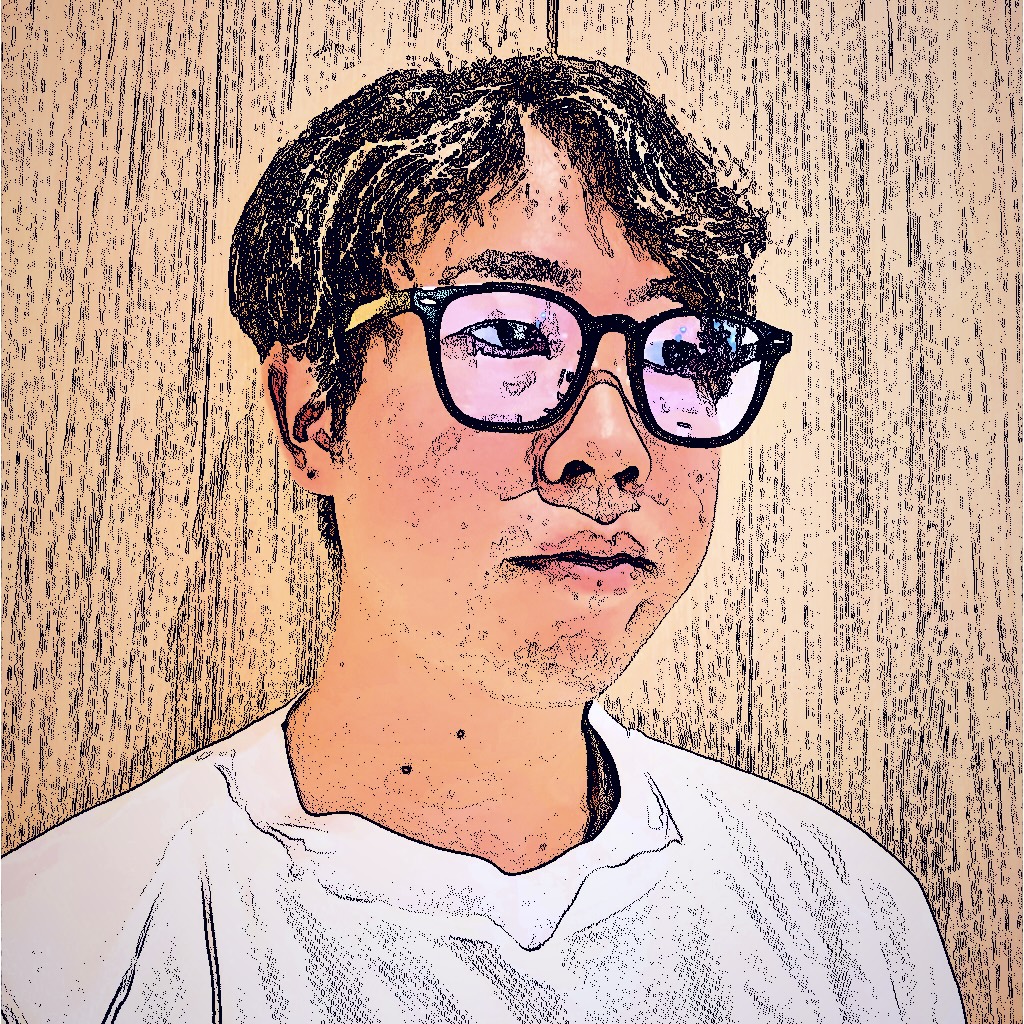
ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。








