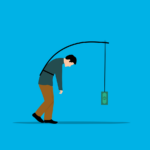「IQと健康行動」の関係について、長年の謎が科学的に解明されつつあります。
あなたは「頭の良い人ほど健康的な生活を送っている」と感じたことはありませんか?
実はこれ、単なる印象ではなく科学的な根拠があるんです。
「Intelligence in youth and health behaviours in middle age」という研究によると、若い頃のIQ(知能指数)は、中年になってからの生活習慣と深く関わっていることが分かりました。
例えば、若い頃にIQが高かった人は、中年になると運動習慣があり、食品ラベルをよく読み、歯のケアもしっかりする傾向があります。
また喫煙率も低いんです。
でも意外なことに、高IQの人が必ずしもすべての面で健康的な選択をしているわけではありません。
お酒を飲む確率は高いですし、食事を抜いたり間食したりする傾向もあるんです。
この記事では、若年期のIQが私たちの健康習慣にどう影響するのか、最新の研究結果をもとに分かりやすく解説します。
自分の健康について考えるきっかけになるかもしれませんよ!
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
IQと健康行動:若年期の知能が中年の生活習慣に与える影響
研究が示す若年期IQと中年期健康行動の関係性
私たちの若い頃の知能は、将来の健康習慣に大きく影響します。
研究によると、若年期のIQ(知能指数)は中年期の健康行動と密接に関連しています。
IQが高い人ほど、健康的な習慣を持つ傾向があるのです。
この関係性は単なる偶然ではありません。
科学的な調査結果から、明確なパターンが見えてきました。
例えば、若い頃のIQが高い人は以下の傾向があります:
- 定期的に運動する習慣がある
- 健康的な食事選択をする
- 喫煙率が低い
- 過度の飲酒をしない
しかしながら、すべての関係性が単純ではありません。
一部の健康行動では予想外の結果も見られました。
特に飲酒パターンや食事習慣では複雑な関連性があります。
このような研究結果は、健康教育や予防医学に役立ちます。
若年期の知能レベルと中年期の健康行動の関連を理解することで、より効果的な健康促進策を考えることができるのです。
調査対象となった5,347人の特徴
この研究では5,347人という大規模な調査が行われました。
対象者は男性と女性の両方が含まれています。
全員がアメリカの国民を代表するグループです。
調査開始時は14歳から21歳の若者でした。
そして約30年後、中年期になった同じ人々を追跡調査しました。
参加者の特徴は以下のとおりです:
- 平均年齢51.7歳(中年期)
- 男性48%、女性52%
- 多様な民族背景(白人、黒人、ヒスパニック系など)
- 様々な社会経済的背景を持つ人々
このような多様な参加者を含むことで、研究結果の信頼性が高まります。
また長期間にわたる追跡調査の形式をとっています。
同じ人を若年期から中年期まで観察することで、より正確な関連性が分かります。
このデータは「全国青年縦断調査1979」と呼ばれるものです。
このような大規模で長期的な調査は、IQと健康の関係を理解する上で貴重な情報源となっています。
AFQT(軍隊資格テスト)で測定されたIQの意味
この研究では「軍隊資格テスト」でIQを測定しています。
この試験は若者の知的能力を客観的に評価するものです。
単なる暗記力ではなく、思考力や問題解決能力を測ります。
テストは主に4つの分野で構成されています。
正確な判断力や理解力が試されるのです。
具体的な測定分野は次のとおりです:
- 計算推理(30問)
- 数学的知識(25問)
- 言葉の知識(35問)
- 文章理解(15問)
テストの制限時間は84分間です。
このテストは学業成績や仕事の成果を予測する力があります。
つまり、社会生活での成功と関連するIQを測定しているのです。
研究ではこのスコアを百分位で記録し、標準化しました。
これにより、異なる年齢や背景を持つ人々の間で公平な比較ができます。
このようなIQ測定は、将来の健康行動との関連を調べる上で信頼性の高い指標となっています。
平均51.7歳の中年期に見られた健康行動とは
中年期には様々な健康習慣が形成されています。
この研究では51歳前後の人々の健康行動を調査しました。
この年齢は健康習慣が定着する重要な時期です。
生活習慣病のリスクも高まってくる頃です。
調査された健康行動は多岐にわたります。
主な調査項目は以下の通りです:
- 運動習慣(頻度や種類)
- 食事選択(間食、食事の抜き方など)
- 喫煙と飲酒の習慣
- 口腔衛生習慣(歯磨きやフロスの使用)
- 栄養ラベルを読む習慣
これらの行動は慢性疾患と深く関連しています。
例えば運動不足は心臓病のリスクを高めます。
また不健康な食習慣は糖尿病と関連します。
中年期の健康行動は将来の健康状態を予測する重要な指標です。
この時期の習慣を理解することで、高齢期の健康問題予防に役立てることができます。
研究結果を読み解く統計用語「オッズ比」について
「オッズ比」は研究結果を理解する重要な指標です。
オッズ比とは、ある出来事が起こる確率の比較を表します。
この数値が1より大きいと、関連性が強いことを示します。
逆に1より小さければ、関連性が弱いことを意味します。
例えば、IQと運動習慣の関連を見てみましょう。
研究では次のようなオッズ比が報告されています:
- 1.72:適度な運動ができる可能性
- 1.61:筋力トレーニングができる可能性
- 0.75:甘い飲み物を摂取する可能性
- 0.60:喫煙する可能性
これらの数字は何を意味するのでしょうか。
1.72というのは、IQが高いほど運動する可能性が1.72倍になるということです。
反対に0.60は、IQが高いほど喫煙率が40%低いことを表します。
また「95%信頼区間」という表現も重要です。
この区間が1を含まなければ、結果は統計的に信頼できると判断します。
オッズ比を理解することで、IQと健康行動の関係をより明確に把握できるのです。
IQと健康行動の関係:意外な発見とは
高IQと運動習慣の意外な関係性
高いIQを持つ人は「適度な」運動を好む傾向があります。
意外なことに、最も知能が高い人々は必ずしも最も激しい運動をするわけではありません。
研究では、IQと運動量の間に逆U字型の関係が見られました。
つまり、中程度の運動をする人が最も高いIQを持つ傾向があるのです。
知能が高い人は極端な行動を避ける特徴があります。
具体的には以下のような関係が見られました:
- 週に150〜509分の中程度の運動をする人がIQが高い
- 運動しない人も、過度に運動する人もIQが比較的低い
- 激しい運動では同様のパターンが見られる
なぜこのような関係があるのでしょうか。
おそらく高IQの人は健康情報をより理解しているからでしょう。
適度な運動が最も健康に良いという科学的事実を知っているのです。
また極端な行動の健康リスクも認識している可能性があります。
このように、高IQの人は情報に基づいた合理的な運動習慣を持つ傾向があります。
筋力トレーニングと知能の関係
筋力トレーニングにも知能との関連が見られます。
高IQの人ほど筋力トレーニングをする可能性が高いのです。
研究によると、そのオッズ比は1.61と高い数値でした。
つまりIQが標準より高い人は、筋トレをする可能性が61%も高いのです。
ただし量については中庸を保つ傾向があります。
筋力トレーニングの頻度とIQの関係は次のとおりです:
- 週に1〜3回のトレーニングをする人が最もIQが高い
- まったくしない人はIQが比較的低い
- 週4回以上の高頻度トレーニングをする人もIQがやや低い
この結果は運動全般に見られるパターンと一致しています。
高IQの人は筋力の重要性を理解しています。
しかし過度なトレーニングのリスクも認識しているようです。
バランスの取れた健康習慣が知的能力と関連しているのです。
筋力トレーニングは認知機能の維持にも役立つという研究もあります。
このような相互関係が、IQと筋トレの関連を説明しているのかもしれません。
食品ラベルを読む習慣とIQの関連性
高IQの人ほど食品ラベルをよく読む傾向があります。
研究によると、知能が高い人は栄養成分表示に注目します。
食品の内容を理解し、意識的な選択をするのです。
特に原材料リストや栄養情報に関心を持ちます。
このような情報収集行動は健康意識の表れでもあります。
具体的な調査結果は以下のとおりです:
- 高IQの人は「しばしば」食品ラベルを読む傾向がある
- 低IQの人は「決して読まない」と答える確率が高い
- 栄養情報を読む習慣のオッズ比は1.20
- 成分表示を読む習慣のオッズ比は1.24
興味深いことに、最もIQが高い人は「常に」ではなく「しばしば」読むと回答しています。
これは極端な行動を避ける傾向の現れかもしれません。
食品ラベルを読むには一定の理解力が必要です。
数値や専門用語を理解し、自分の健康と関連付ける能力が求められるのです。
高いIQを持つ人はこのような複雑な情報を処理するのが得意なため、食品選択においてもより意識的な判断ができるのでしょう。
高IQと甘い飲み物の摂取の少なさ
高IQの人は甘い飲み物を避ける傾向があります。
研究結果によると、知能指数が高い人ほど糖分の多い飲料を控えています。
オッズ比は0.75で、IQが高いほど甘い飲み物を飲む確率が25%も低いのです。
この関連性は統計的にも非常に強いものでした。
健康情報への理解度の違いが影響していると考えられます。
甘い飲み物を避ける理由としては:
- 糖分過多による健康リスクの認識
- カロリー摂取量への意識
- 虫歯や肥満などの長期的影響の理解
- 添加物や人工甘味料への懸念
高IQの人は栄養素と健康の関係をより理解しています。
そのため、より意識的な飲料選択をするのでしょう。
水や無糖の飲み物を好む傾向も見られます。
さらに、子どもの頃の食育も影響している可能性があります。
知的能力が高い家庭では、健康的な飲料習慣が教えられることが多いのかもしれません。
このように、甘い飲み物の摂取量は知能と関連し、将来の健康状態にも影響を与える重要な習慣なのです。
口腔衛生習慣(歯のフロス使用)とIQの関係
高IQの人ほど歯のフロスを使う傾向があります。
研究によると、知能指数が高い人は口腔衛生に気を配ります。
フロスを使用するオッズ比は1.47と高い数値でした。
つまりIQが標準より高い人は、フロスを使う可能性が47%も高いのです。
これは単なる偶然ではなく、明確な関連性があります。
フロス使用とIQの関係は次のようになっています:
- 高IQの人は週に5〜7回フロスを使う傾向がある
- 低IQの人はフロスを全く使わない確率が高い
- 過度な使用(1日複数回)はどのIQレベルでも少ない
さらに、歯磨きの頻度についても同様の傾向が見られました。
高IQの人ほど1日2回以上歯を磨く習慣があります。
口腔衛生は全身の健康にも関連することを理解しているようです。
歯周病と心臓病や糖尿病の関連性などの知識がある可能性があります。
また予防的な健康行動全般への意識が高いことの表れでもあるでしょう。
このように、フロスの使用という単純な習慣も、知的能力と健康意識を反映する重要な指標となっています。
IQと健康行動:リスクを高める行動
高IQと飲酒行動のU字型関係
IQと飲酒の関係は複雑なU字型を示します。
高IQの人は全く飲まない人よりも飲酒する傾向があります。
調査では、IQが高いほど過去30日間に飲酒した確率が58%も高かったのです。
しかし、大量飲酒については逆の関係が見られました。
高IQの人ほど一度に6杯以上飲む確率は33%も低かったのです。
飲酒量とIQの関係は以下のようになっています:
- 中程度のIQの人は最も飲酒量が少ない
- 最も低いIQと最も高いIQの人は比較的飲酒量が多い
- しかし飲酒パターンが異なる(高IQは頻繁に少量、低IQはたまに大量)
この複雑な関係には社会的要因も影響しています。
高学歴の職場環境では飲酒の機会が多いかもしれません。
また高IQの人は飲酒のリスクと利点をより理解しているでしょう。
少量の飲酒には社交的なメリットもあります。
このように、IQと飲酒行動の関係は単純ではなく、量や頻度、状況によって異なるパターンを示すのです。
喫煙習慣とIQの逆U字型関係
喫煙とIQの関係も意外な形を示しています。
全体として、高IQの人ほど喫煙率は低いのです。
オッズ比は0.60で、IQが高いほど喫煙率が40%も低いことを示しています。
しかし喫煙者に限ると、別のパターンが見えてきます。
一日の喫煙本数とIQの間には逆U字型の関係があるのです。
具体的には以下のようなパターンが見られました:
- IQが低い〜中程度の範囲では、IQが高いほど喫煙本数が増える
- IQが中程度〜高い範囲では、IQが高いほど喫煙本数が減る
- 最も多く喫煙するのは中程度のIQを持つ喫煙者たち
この複雑なパターンはなぜ生じるのでしょうか。
低IQの人は喫煙の害をあまり理解していないかもしれません。
一方、高IQの人は喫煙者であっても健康リスクを意識して本数を減らすのでしょう。
中程度のIQの人は、ストレス解消や社会的理由で多く喫煙する可能性があります。
このように、喫煙行動は単にIQだけでなく、社会的要因や心理的要因も絡み合って形成されるのです。
食事を抜く習慣と知能指数の関連性
高IQの人ほど食事を抜く傾向があるという意外な結果が出ています。
研究によると、IQが高い人は前の週に食事を抜いた確率が10%も高いのです。
この関連性は統計的にも有意です。
しかし抜く回数については、また違うパターンが見られました。
IQと抜く食事の回数には逆U字型の関係があります。
食事を抜く習慣とIQの関係は以下のとおりです:
- 低〜中程度のIQでは、IQが高いほど抜く回数が増える
- 中〜高IQでは、IQが高いほど抜く回数が減る
- 最も多く食事を抜くのは中程度のIQ保持者
この結果は一見矛盾しているように見えます。
高IQの人が健康的な習慣を持つなら、なぜ食事を抜くのでしょうか。
可能性としては、仕事の忙しさや時間管理の違いがあります。
また計画的に食事を抜く断続的断食を取り入れている可能性もあります。
食事を抜くことが必ずしも不健康とは限らないという研究も増えています。
このように、食事を抜く習慣は複雑で、単純に健康・不健康と判断できない行動なのです。
間食行動と知能レベルの予想外の結果
知能が高い人ほど間食をする傾向があります。
研究結果によると、高IQの人は前の週に間食した確率が37%も高いのです。
これは予想外の発見でした。
一般的に間食は不健康な習慣と考えられています。
なぜ知的能力の高い人がこのような行動をとるのでしょうか。
考えられる理由としては:
- 計画的な少量多食を実践している
- 栄養バランスを考えた間食を選んでいる
- 長時間の知的作業でエネルギー補給が必要
- 空腹を我慢するよりも少量摂取を好む合理的判断
ただし、間食の内容までは調査されていません。
高IQの人はより健康的なスナックを選んでいる可能性もあります。
また間食の頻度と健康への影響は個人差があります。
このような複雑な関係から、間食習慣だけで健康状態を判断することはできません。
知能と間食行動の予想外の関連は、食習慣の多面的な性質を示すものであり、今後さらなる研究が必要な分野といえるでしょう。
高IQが必ずしも健康的な選択につながらない理由
高いIQがあっても、必ずしも健康的な選択をするとは限りません。
知能と健康行動の関係は複雑です。
知識があっても実行に移せないことはよくあります。
特に嗜好品や快楽を伴う習慣は、理性だけでは変えられないのです。
高IQの人も、様々な要因の影響を受けています。
健康的選択の障壁となる要因は:
- ストレスや感情による判断の曇り
- 社会的環境や周囲の圧力
- 時間的制約や便利さの追求
- 短期的な快楽を優先する心理的傾向
- 職業環境による制約(長時間労働など)
また知的能力が高い人は、リスクを計算し、「適度な不健康」を選ぶこともあります。
例えば、運動不足でも知的活動に時間を使う選択をするケースです。
さらに高IQの人は自己正当化能力も高い傾向があります。
不健康な習慣を持っていても、それを論理的に正当化してしまうのです。
このように、知能は健康行動の一要素ではありますが、健康的な生活習慣の形成には他の多くの要因も影響しているのです。
IQと健康行動と社会経済要因の三角関係
幼少期の社会経済状況がIQと健康行動に与える影響
子ども時代の環境はIQと健康行動の両方に影響します。
幼少期の社会経済状況(SES)は重要な要素です。
SESとは家庭の収入や親の教育、職業などを指します。
この幼少期の環境が、その後の人生に長く影響するのです。
研究ではこの影響を数値で確認しています。
幼少期のSESの影響は以下のような形で現れます:
- 栄養状態や健康サービスへのアクセス
- 教育の質や知的刺激の量
- 健康的な習慣についての家庭教育
- ストレスや安定した環境の有無
- 将来の見通しや自己価値観の形成
興味深いことに、幼少期のSESを考慮しても、IQと健康行動の関連性はあまり変わりませんでした。
これはIQが独自の影響力を持つことを示しています。
つまり、育った環境にかかわらず、知的能力は健康選択に影響するのです。
このことから、幼少期の環境とIQは健康行動に対して、それぞれ独立した影響力を持っていることが分かります。
成人期の社会経済状況が結果を変える理由
大人になってからの社会的立場も健康行動に大きく影響します。
研究では、成人のSESを考慮すると結果が大きく変わりました。
つまり、IQの影響の多くは成人期の社会経済状況を通じて現れるのです。
高IQの人は良い仕事に就きやすく、収入も高い傾向があります。
そして、そのような環境が健康的な選択を促進するのです。
成人期のSESが健康行動に影響する理由は:
- 健康的な食品や運動施設へのアクセスのしやすさ
- 医療情報や健康サービスへのアクセス
- 時間的・金銭的余裕の違い
- 職場環境や社会的ネットワークの影響
- ストレスレベルの違い
例えば、甘い飲み物の摂取とIQの関連は、成人SESを考慮するとほぼ消えました。
これは、飲料選択が知能よりも社会経済的要因に強く影響されることを示しています。
一方で、喫煙や飲酒などいくつかの行動は、成人SESを考慮しても関連性が残りました。
このことから、IQは社会経済的地位を通じて間接的に、そして一部は直接的に健康行動に影響していることが分かります。
教育レベルとIQの密接な関連性
教育とIQは強く関連し、健康行動にも影響します。
高いIQを持つ人は、より高い教育を受ける傾向があります。
研究によると、IQと教育達成度の相関は約0.56と非常に高いのです。
つまり、IQの違いが教育レベルの違いの約30%を説明できます。
そして教育レベルが健康知識や行動に影響するのです。
教育がIQと健康を結ぶ理由は以下のとおりです:
- 健康リテラシー(健康情報を理解する能力)の向上
- 長期的な視点の獲得
- 健康情報へのアクセスと理解力の向上
- 社会的ネットワークや規範の違い
- 自己効力感(自分で健康を管理できるという信念)の強化
研究者の中には、教育は「IQの代理指標」ともいう人もいます。
両者は密接に関連し、遺伝的影響も共有しているのです。
しかし、高いIQがあっても教育機会がなければ、その能力を健康行動に活かせません。
このように、IQ、教育、健康行動は三位一体となって影響し合っています。
IQと健康行動:職業選択が与える複合的影響
仕事の種類や環境も健康習慣に大きく影響します。
高IQの人は特定の職業に就く傾向があります。
そして職業環境が健康行動を形作るのです。
例えば専門職は座り仕事が多く、運動不足になりがちです。
一方で健康意識も高く、喫煙率は低い傾向があります。
職業が健康行動に影響する経路は様々です:
- 労働時間や勤務形態(シフト制など)
- 職場でのストレスレベル
- 同僚や職場文化からの影響
- 職場での飲食環境や運動機会
- 健康保険や福利厚生の違い
高IQの人が多い職場では、健康的な規範が形成されやすいです。
例えば禁煙や適度な飲酒が奨励される環境かもしれません。
また収入の違いも重要です。
健康的な食品は不健康な食品より高価なことが多いのです。
このように、IQと職業選択、そして職場環境が複雑に絡み合い、私たちの日々の健康習慣に影響を与えているのです。
社会経済要因を考慮した場合でも残る関連性
一部の健康行動は社会経済要因だけでは説明できません。
研究では、すべての社会経済要因を考慮しても残る関連性がありました。
つまり、IQは独自の影響力を持っているのです。
特に以下の健康行動では関連性が強く残りました。
これらはIQの直接的な影響を受けると考えられます。
社会経済要因を考慮しても残る関連性:
- 喫煙習慣(オッズ比0.81)
- 大量飲酒(オッズ比0.83)
- 運動パターン(中程度の運動を好む傾向)
- 食事を抜く習慣(オッズ比1.16)
- 間食行動(オッズ比1.38)
なぜこれらの行動では関連性が残るのでしょうか。
可能性としては、情報処理能力や長期的思考の違いがあります。
高いIQを持つ人は健康情報をより理解し、将来のリスクを考慮します。
また衝動性のコントロールや習慣形成能力の違いもあるでしょう。
このように、IQと健康行動の関係は社会経済的要因だけけでは説明できない複雑なものです。
知能の高さは、私たちの健康選択に直接的かつ間接的に影響を与えているのです。
このような研究結果は、効果的な健康促進策を考える上で重要な示唆を与えてくれます。
IQと健康行動まとめ
若年期のIQと中年期の健康行動には、確かな関連性があることが分かりました。
高いIQを持つ人は、運動習慣や食品ラベルを読む習慣、口腔衛生などで健康的な選択をする傾向があります。
また喫煙率も低く、大量飲酒も避ける傾向にあるのです。
しかし、すべてが単純ではありません。
高IQの人は間食や食事抜きの傾向もあり、適度な飲酒率も高いのです。
これらの関係は、社会経済的要因を考慮しても残るものがあります。
特に中庸を保つ傾向が見られるのは興味深いポイントです。
極端に運動しないよりも適度に運動する、全く飲まないよりも適度に飲む、といった「バランス感覚」が高IQと関連しているのです。
この研究からの最大のメッセージは、知能だけでなく、社会環境や教育機会も含めた総合的な視点で健康行動を考える必要があるということです。
賢さは健康的な選択の一助になりますが、それだけで健康が保証されるわけではありません。
日々の小さな選択の積み重ねが、将来の健康を形作るのです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。