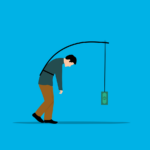「IQと収入」の関係について、多くの人が気になっているのではないでしょうか?
「頭が良い人ほどお金持ちになれる」というイメージがありますよね。でも、これって本当なのでしょうか?
実は科学的な研究でこの疑問に答えが出ています。アメリカのオハイオ州立大学のジェイ・L・ザゴルスキー氏が行った「頭の良さはお金持ちになる条件なのか?IQが富、収入、経済的困難に与える影響」という研究です。
この研究では7000人以上の若いアメリカ人を長期間追跡調査しました。その結果、驚きの事実が明らかになったのです。
IQは確かに収入に影響します。でも、資産形成(お金をためること)とは関係がないという意外な結果になりました。さらに、金銭トラブルとIQの関係も私たちの予想とは違っていました。
この記事では、IQと経済的成功の関係について詳しく解説します。あなたの将来設計や資産形成に役立つ情報が満載です。頭の良さよりも大切な「お金をためるコツ」も紹介していきましょう!
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

目次
IQと収入の関係:賢い人は本当に稼げるのか?
研究の背景:なぜIQと収入の関係が気になるのか
人は昔から「頭が良い人はお金持ちになれる」と考えてきました。
この考えは本当に正しいのでしょうか?
実は科学的に検証する必要があるのです。
「知能指数(IQ)」とは頭の良さを数値化したものです。
平均は100で、高いほど知的能力が高いとされます。
一方で、成功には様々な要素があります。
例えば:
- 努力
- 人脈
- チャンス
- 家庭環境
そこで研究者たちは「IQが高いと本当に収入が増えるのか」を調べました。
また「IQだけで人生の経済的成功が決まるのか」という疑問も浮かびます。
さらに社会全体としても、能力と報酬の関係は重要です。
公平な社会を目指すなら、この関係を知る必要があります。
実際、多くの企業がIQテストに似た適性検査を採用しています。
ですから私たちの生活にも大きく関わる問題なのです。
この研究は7000人以上の長期追跡データを使っています。
つまり信頼性の高い結果が期待できるのです。
IQと収入の関係を知ることで、自分の将来設計にも役立つでしょう。
研究で分かったIQと収入の明確な関連性
科学的研究によると、IQと収入には確かに関連性があります。
これは統計的に見ても明らかな結果です。
つまり、頭が良い人は平均的に稼ぎが多いのです。
ただし、完全な比例関係ではありません。
相関係数は0.3程度という中程度の関連性でした。
言い換えると、IQは収入の一部を説明するに過ぎません。
研究では様々な要因を考慮した上での結果です。
例えば以下の要素を調整しています:
- 年齢
- 人種
- 教育レベル
- 職業
- 婚姻状況
それでもIQと収入の関係は残りました。
特に興味深いのは、職種による違いです。
専門職や管理職では関連性がより強くなります。
一方、単純作業では関連性が弱まる傾向があります。
また男女間でも若干の違いが見られました。
男性の方がIQと収入の関連が強い傾向があります。
これは職業選択の違いも影響しているかもしれません。
結論として、IQは収入を予測する有効な指標の一つと言えるでしょう。
IQと収入:IQが1ポイント上がると年収はいくら増える?
IQが1ポイント上がると年収は234円から616円増えることがわかりました。
これは様々な要因を考慮した結果です。
つまり、教育や経験などの影響を除いた純粋な効果です。
一見すると少ない金額に思えるかもしれません。
しかし、IQポイントの累積効果を考えると違います。
例えば、IQが10ポイント違うと年間2,340円から6,160円の差になります。
さらに生涯を通じて考えると大きな金額になります。
40年働くと93,600円から246,400円の差が生じます。
また、IQの差がより大きいとどうなるでしょう。
平均IQ(100)と高IQ(130)では年収に大きな開きが出ます。
具体的には7,020円から18,480円の年収差になります。
これが毎年続くと生涯で数百万円の違いになるのです。
ただし、この結果には注意点もあります。
個人差が非常に大きいということです。
同じIQでも収入に大きな違いがある人はたくさんいます。
要するに、IQは収入に影響しますが、決定的要因ではないのです。
高IQと低IQの人の年収差はどれくらい?
高IQと低IQの人の収入差は約3.6倍にもなります。
研究によると、これは大きな違いです。
具体的に見ていきましょう。
IQ75以下の人の平均年収は約150万円でした。
一方、IQ125以上の人は約550万円を稼いでいます。
この差は単純計算で年間400万円です。
なぜこれほどの差が生じるのでしょうか。
いくつかの理由が考えられます:
- 高IQの人は高学歴になりやすい
- 複雑な判断が求められる高給の職に就きやすい
- 問題解決能力が評価される
- 昇進のチャンスが多い
特に上位1%のIQ(135以上)だと収入は更に上がります。
ただし、すべての高IQの人が高収入というわけではありません。
個人の価値観や選択も大きく影響します。
例えば研究職など、収入より興味を優先する場合もあります。
また、低IQでも経営者として成功する例もあります。
重要なのは、統計的傾向であって個人の可能性ではありません。
どのIQレベルでも、努力や人間関係で収入を上げられます。
結局、IQは収入の差を部分的に説明するだけなのです。
教育レベルと収入の関係:IQだけが重要?
教育レベルはIQと収入の関係に大きく影響します。
実は、IQと教育は密接に関連しています。
相関係数は0.6と非常に高い値です。
つまり、高IQの人ほど教育レベルが高い傾向があります。
では、収入に影響しているのはIQでしょうか教育でしょうか?
研究では両方の影響を分離して調べています。
その結果がとても興味深いのです。
教育レベルを考慮すると、IQの影響は小さくなります。
しかし、完全には消えません。
これは両方が独立して収入に影響することを意味します。
教育の効果を数字で見てみましょう:
- 高校卒業:年収約200万円アップ
- 大学卒業:さらに約200万円アップ
- 大学院修了:さらに約100万円アップ
一方、同じ教育レベルでもIQによる収入差はあります。
例えば同じ大卒でもIQの高い人の方が平均収入は高いです。
これは職場での能力発揮の差かもしれません。
また、教育とIQの相乗効果も見られました。
高IQの人ほど教育から得る収入上昇効果が大きいのです。
結局、収入には両方が重要であることがわかります。
IQと収入:頭の良さはお金持ちになる条件なのか
意外な発見:IQと純資産の関係性はほぼゼロ
研究の最も驚くべき発見は、IQと純資産にはほとんど関係がないことです。
これは多くの人の予想に反する結果でした。
純資産とは、所有物の価値から借金を引いた金額です。
つまり「本当の豊かさ」を表す指標といえます。
研究では様々な分析方法を使いました。
それでもIQと純資産の間に明確な関係は見つかりませんでした。
IQスコア別の純資産を見ても傾向は一定ではありません。
例えば:
- IQ75以下:中央値約57万円
- IQ100:中央値約575万円
- IQ125以上:中央値約1332万円
一見すると差があるように見えます。
しかし、他の要因を考慮すると差はほぼ消えるのです。
年齢や教育、収入などを調整した場合です。
特に収入を考慮すると関係性はさらに弱まります。
これは収入と貯蓄率が必ずしも比例しないためです。
高収入でも浪費する人もいれば、低収入でも貯蓄する人もいます。
結論として、頭の良さは稼ぎには影響しますが、資産形成とは無関係なのです。
お金持ちになるためにIQは必要ない?
お金持ちになるのにIQは重要な条件ではありません。
この発見は多くの人に希望を与えるものです。
ベストセラー『となりの億万長者』の主張と一致します。
著者は「富の蓄積に知性はほとんど関係ない」と述べています。
実際のデータもこれを裏付けています。
高IQの人々の中にも資産の少ない人はたくさんいます。
逆に、平均以下のIQでも大きな資産を築く人もいます。
お金持ちになるために重要なのは別の要素です:
- 貯蓄習慣
- 消費の抑制
- 長期的な計画
- 投資の知識
- 複利の力の理解
特に重要なのは「消費より貯蓄を優先する姿勢」です。
この点で、IQよりも自制心の方が重要かもしれません。
また、リスクを取る勇気も資産形成には必要です。
起業家の多くは必ずしも高IQではありません。
むしろ失敗を恐れない姿勢や粘り強さが特徴です。
結局、お金持ちになるには知性よりも行動パターンが大切なのです。
同じIQでも資産に大きな差がある理由
同じIQの人でも資産額に大きな差が生じる理由は多岐にわたります。
まず、収入の使い方が大きく影響します。
同じ収入でも貯蓄率は人によって大きく異なります。
研究によれば、貯蓄習慣はIQと無関係です。
また、消費行動にも違いがあります。
見栄のための消費をする人は資産が増えにくいです。
次に、投資判断の違いも重要です。
主な違いは以下の点に表れます:
- リスク許容度
- 投資期間の長さ
- 分散投資の理解
- 感情的な売買の有無
- 複利効果の活用
さらに、ライフイベントの影響も無視できません。
離婚や病気は資産形成に大きなダメージを与えます。
実際、離婚経験者は平均して約280万円資産が少ないのです。
また、親からの相続も大きな要因です。
相続は本人の能力とは無関係に資産を増やします。
職業選択も純資産に影響します。
自営業者は給与所得者より資産形成のチャンスが多いのです。
結局、資産形成はIQではなく多くの選択と習慣の積み重ねなのです。
資産形成に本当に重要な心理的要素
資産形成に重要なのは知能ではなく心理的要素です。
研究では三つの心理特性が特に重要でした。
一つ目は「自己コントロール感覚」です。
これは自分の人生を自分でコントロールできる感覚です。
この感覚が強い人ほど資産が多い傾向があります。
二つ目は「自尊心」の高さです。
自尊心が高い人は将来に対して前向きです。
そのため長期的な資産形成に取り組みやすいのです。
三つ目は「人生の主体性」の感覚です。
主体性を感じる人は以下の傾向があります:
- 計画的に行動する
- 問題に積極的に対処する
- 将来への備えを重視する
- 衝動的な消費を避ける
- 金銭管理に責任を持つ
これらの心理特性はIQとは異なり、努力で改善できます。
また、「満足の遅延能力」も重要な要素です。
今の楽しみを我慢して将来のために貯蓄できる能力です。
さらに「社会的比較の抵抗力」も資産形成に影響します。
他人と比べて消費を増やす衝動を抑える力です。
意外なことに、これらの特性はIQとほとんど関係ありません。
つまり、頭の良さより心の持ち方が資産形成には重要なのです。
貯蓄行動とIQの関係
貯蓄行動とIQには明確な関係がないことがわかっています。
どのIQレベルでも、貯蓄率には大きな個人差があります。
平均的に見ると、貯蓄額は収入の約18.6ヶ月分です。
これはIQによってあまり変わりません。
IQ75以下の人は約5ヶ月分の貯蓄があります。
一方、IQ125以上の人は約28.8ヶ月分です。
この差は主に収入の違いによるものです。
貯蓄率(収入に対する貯蓄の割合)はほぼ同じなのです。
また、貯蓄の目的もIQで大きく変わりません。
主な貯蓄目的はどのIQレベルでも以下のようなものです:
- 緊急時の備え
- 老後の資金
- 子どもの教育
- 大きな買い物
- 将来の楽しみ
さらに、貯蓄習慣の形成にはIQより家庭環境の影響が大きいです。
子どもの頃の経験が大人になってからの貯蓄行動を左右します。
貯蓄を増やすコツも、IQに関係なく同じです。
「先取り貯蓄」は特に効果的な方法です。
これは収入を得たらまず一定額を貯蓄に回す方法です。
結局、貯蓄成功の鍵は知能ではなく習慣形成にあるのです。
IQと収入:高IQは金銭トラブルを避けられるか
クレジットカード利用とIQの意外な関係
IQとクレジットカード利用には意外な関係があります。
一般的に、高IQほど賢い金銭管理をすると思われがちです。
しかし研究結果はそれを否定しています。
クレジットカードの限度額に達する割合を見てみましょう。
IQ75以下の人では約7.7%が限度額に達しています。
意外なことにIQ90の人では12.1%に上昇しています。
その後IQ115の人では5.4%まで下がります。
しかしさらに高いIQ140では再び14.2%に上昇するのです。
このU字型のパターンはとても興味深いものです。
理由としていくつかの可能性が考えられます:
- 高IQの人は複雑な金融商品を使いこなそうとする
- 自分の知性を過信して無理なローンを組む
- 忙しさで支払いを忘れることがある
- 収入に見合わない生活水準を維持しようとする
特に高IQの人は「自分は大丈夫」と考えがちです。
そのため、リスクの高い行動を取ることもあります。
また、多重債務者の割合もIQによって異なります。
複数枚のカードを限度額まで使う人はIQ90付近に多いのです。
結局、クレジットカードの賢い利用はIQより自己管理能力が重要なのです。
支払い遅延や破産とIQの複雑な関連性
支払い遅延や破産とIQの関係も単純ではありません。
研究では「過去5年間に支払いを2ヶ月以上遅延したか」を調査しました。
結果は意外なものでした。
IQ75以下の人では17.5%が支払いを遅延しています。
IQ85から90の人では約23%と最も高くなります。
そしてIQ125以上では11.8%まで下がります。
破産についても同様のパターンが見られました。
IQ75以下の人の14.5%が破産を経験しています。
IQ95の人では18.7%と最も高くなります。
一方、IQ125以上では5%まで下がっています。
この複雑なパターンには様々な要因が考えられます:
- 中程度のIQの人は無理な借金をしやすい
- 高IQの人は金融知識が豊富で回避策を知っている
- 低IQの人はそもそも信用枠が小さい場合が多い
- 中程度のIQの人は収入に見合わない生活をしがち
統計分析では「IQの二次関数」で説明できます。
これは「中程度のIQで金銭トラブルが最も多い」ことを示します。
また、教育レベルを考慮すると関連性はさらに複雑になります。
同じIQでも教育レベルが高いと破産率は下がる傾向があります。
つまり、金銭トラブル回避には知識教育が有効なのです。
最も経済的困難が少ないのは平均よりやや高いIQ
経済的困難が最も少ないのはIQ105〜115の人たちです。
これは平均(IQ100)よりもやや高い層になります。
具体的な数字を見てみましょう。
IQ110の人たちはクレジットカード限度額到達が6.3%と低いです。
支払い遅延も17%と平均的な水準です。
破産経験率も11.8%と全体平均(13.5%)より低めです。
なぜこの層が最も経済的に安定しているのでしょうか。
いくつかの理由が考えられます:
- 十分な収入を得られる知的能力がある
- 衝動的な消費に流されない自制心がある
- 複雑な金融商品のリスクを理解できる
- 将来を見据えた計画を立てられる
- 過度な自信過剰に陥らない
特に重要なのは「バランス感覚」かもしれません。
低すぎるIQだと収入確保に苦労します。
逆に高すぎるIQだと自己過信に陥りやすいのです。
中程度〜やや高めのIQがちょうど良いバランスなのでしょう。
また、この層は高すぎる生活水準を求めない傾向もあります。
無理のない範囲で安定した生活を好む人が多いようです。
結局、IQよりもバランス感覚が経済的安定には重要なのです。
なぜ高IQの人も金銭トラブルに陥るのか
高IQの人が金銭トラブルに陥る理由はいくつかあります。
まず、「自分は賢いから大丈夫」という過信があります。
高IQの人は自分の判断能力を過大評価しがちです。
そのため、リスクの高い投資に手を出すことがあります。
また、収入に見合わない生活水準を維持しようとします。
高収入を得ても、支出が収入を上回れば借金は増えます。
さらに、複雑な仕事や活動に忙殺される傾向もあります。
その結果、以下のような問題が起きやすくなります:
- 支払期日の管理が疎かになる
- 請求書の確認を怠る
- 予算管理の時間が取れない
- 複数の金融商品を適切に管理できない
- 緊急時の備えが不足する
高IQの人は「知的な挑戦」を好む傾向もあります。
そのため、複雑な金融商品や投資戦略に手を出しがちです。
また、将来の高収入を見込んで現在の借金を正当化します。
「将来返せるから今は借りても大丈夫」という考え方です。
さらに、金融知識と実践的な金銭管理は別物です。
頭では理解していても、実際の行動が伴わないことがあるのです。
金銭管理能力とIQは比例しない?
金銭管理能力とIQは必ずしも比例しません。
研究結果はこの事実を明確に示しています。
金銭管理能力は「知能」よりも「習慣」の問題です。
実際、金銭管理が上手な人には共通点があります。
それはIQに関係なく身につけられる習慣です。
効果的な金銭管理習慣には以下のようなものがあります:
- 収支の定期的な記録
- 予算の作成と遵守
- 自動的な貯蓄の仕組み作り
- 緊急時の備え金の確保
- 衝動買いの抑制
これらの習慣は知能よりも「規律」に関係しています。
また、親から学ぶ金銭感覚も重要です。
子どもの頃の家庭環境がお金の扱い方に大きく影響します。
さらに、金銭管理の知識教育も効果的です。
金融教育を受けた人は経済的困難に陥る確率が低いのです。
興味深いことに、自分の金銭状況を定期的に確認する習慣は、全てのIQレベルで効果があります。
また、単純な戦略ほど続けやすく効果的です。
複雑な投資戦略より基本的な貯蓄習慣の方が重要なのです。
結局、賢い金銭管理は頭の良さより継続的な習慣にかかっています。
IQと収入以外の成功要因:本当に大切なのは何か
誠実性と金銭管理の関係
まず誠実性は金銭管理の成功に強く関連しています。
誠実性とは「責任感が強く、計画的で勤勉な性格」のことです。
心理学研究によると、これは金銭管理に最も影響する性格特性です。
誠実性の高い人は以下の傾向があります:
- 期限を守る
- 計画的に行動する
- 約束を守る
- 長期目標に向けて努力する
- 誘惑に負けにくい
実際、誠実性の高い人はローン返済の遅延が40%少ないというデータがあります。
また貯蓄率も平均より25%高いことがわかっています。
クレジットスコアも誠実性と関連しています。
誠実性の高い人は平均して53ポイント高いスコアを持っています。
この特性はIQとは別の能力です。
つまり知能に関係なく、誰でも伸ばせる可能性があります。
誠実性を高める方法としては以下が効果的です:
- 小さな約束から必ず守る習慣をつける
- 長期目標を細かい段階に分ける
- 定期的に自分の行動を振り返る
- 時間管理ツールを活用する
- 自分への約束も他人への約束と同様に大切にする
結局、頭の良さより「約束を守る誠実さ」が経済的成功には重要なのです。
満足の先延ばし能力と資産形成
満足の先延ばし能力は資産形成の重要な予測因子です。
この能力は「今の楽しみを我慢して将来の利益を選ぶ力」です。
有名な「マシュマロ実験」はこの能力の重要性を示しています。
この実験では子どもに選択肢を与えます。
「今すぐマシュマロ1個」か「15分待ってマシュマロ2個」かです。
待てた子どもたちはその後の人生で様々な成功を収めました。
資産形成においても同じ原理が働きます:
- 今使うか、将来のために貯めるか
- 即時の満足か、将来のより大きな満足か
- 衝動買いをするか、計画的な買い物をするか
- 借金で今欲しいものを手に入れるか、現金で買えるまで待つか
- 見栄のための消費か、将来の安心のための貯蓄か
研究によれば、満足の先延ばし能力の高い人は:
- 貯蓄率が約30%高い
- 借金が約40%少ない
- 資産形成のための投資をしている確率が高い
驚くべきことに、この能力はIQと無関係です。
高IQでも衝動的な人はいますし、平均的IQでも忍耐強い人はいます。
良いニュースは、この能力は訓練で向上するということです。
小さな「先延ばし」から始めて徐々に大きな目標に取り組むのが効果的です。
資産形成の成功には知能より「待つ力」が重要なのです。
リスク許容度が資産に与える影響
適切なリスク許容度は資産形成に大きく影響します。
リスク許容度とは「不確実性や損失の可能性をどれだけ受け入れられるか」です。
人によって大きく異なるこの特性は、IQとは関係ありません。
高IQでもリスク回避的な人もいれば、低IQでも冒険的な人もいます。
資産形成におけるリスク許容度の影響は以下のような点に表れます:
- 投資商品の選択(株式vs債券vs預金)
- 起業の判断
- 転職や引っ越しの決断
- 借入の活用
- 不動産投資への姿勢
リスク許容度が低すぎる場合:
- 安全な投資だけを選ぶため、リターンが低い
- インフレによる資産価値の目減りを受ける
- 成長機会を逃しがち
一方、リスク許容度が高すぎる場合:
- 投機的な投資で大損する可能性
- 分散投資を軽視しがち
- 借入過多になりやすい
最適なのは「バランスの取れたリスク許容度」です。
年齢や状況に応じて適切なリスクを取ることが重要です。
例えば若いうちは株式比率を高め、高齢になるほど安全資産を増やすといった調整です。
結局、知能よりも適切なリスク管理が資産形形成には重要なのです。
自分のリスク許容度を知ることは金融計画の第一歩といえます。
それを基に適切な資産配分を決めていくことが成功の鍵なのです。
情動性と消費行動の関連
まず情動性の高さは計画外の消費につながりやすいです。
情動性とは「感情の起伏が大きい性格特性」を指します。
これは不安や怒り、落ち込みなどの感情を強く経験する傾向です。
研究によると、情動性と消費行動には明確な関連があります。
情動性の高い人は「感情的な買い物」をしがちです。
特に以下のような消費傾向が見られます:
- 気分を良くするための「ストレス解消買い」
- 不安を和らげるための「安心買い」
- 社会的な承認を得るための「見栄消費」
- 衝動的な「セール品の大量購入」
- 感情的な判断による「高額商品の衝動買い」
これらは計画的な資産形成の障害となります。
例えば、情動性の高い人は平均して18%多く消費するというデータがあります。
また、貯蓄率も約12%低い傾向があります。
重要なのは、情動性はIQとほぼ無関係だということです。
高IQでも情動性が高い人は消費のコントロールが難しいのです。
情動性による消費を抑える方法はいくつかあります:
- 大きな買い物の前に24時間の「冷却期間」を設ける
- 買い物をする前に感情状態をチェックする
- 買い物リストを作って計画的に購入する
- 買い物の理由を明確にする
- 感情的になったときの別の対処法を見つける
結局、感情の管理ができるかどうかが資産形成の重要な要素なのです。
社会的影響の受け方と経済的成功
社会的影響の受け方が経済的成功を左右します。
私たちは常に周囲の人々から影響を受けています。
特に消費行動や金銭感覚は強く影響されます。
この影響の受け方はIQではなく別の能力に関わっています。
経済的に成功している人には特徴があります。
それは「適切に社会的影響を取捨選択できる能力」です。
具体的には以下のような点が重要です:
- 周囲と比較して消費を増やす「見栄消費」を避ける
- SNSなどで見る「リッチな生活」に惑わされない
- 広告の心理的手法に気づいて対処できる
- 「みんなが持っているから」という理由だけで買わない
- 本当に自分に必要かどうかを判断できる
研究によると、社会的比較に弱い人は平均して23%多く消費します。
また、貯蓄率も約17%低い傾向があります。
社会的影響の受け方を変える方法はいくつかあります:
- 自分の価値観を明確にする
- 本当に尊敬できる人だけを参考にする
- 広告やSNSの影響を意識する
- 「みんなと同じ」である必要はないと自己肯定する
- 自分の財政状況に合った友人関係を築く
最も重要なのは「自分の経済状況に合った生活水準」を守ることです。
周囲に流されず自分のペースで資産形成できる人が成功します。
結局、知能より「社会的影響への耐性」が経済的成功には重要なのです。
最後に
IQと収入の関係について見てきましたが、意外な事実がたくさんありましたね。
研究によれば、IQが高いと確かに収入は増えます。しかし、資産形成(お金をためること)にはほとんど影響しないことがわかりました。お金持ちになるためには、IQよりも習慣や心理的特性の方が重要なのです。
特に大切なのは、誠実性(計画的に行動する性格)、満足の先延ばし能力(今の楽しみを我慢できる力)、適切なリスク管理、感情のコントロール、そして社会的影響への耐性です。これらはIQに関係なく、誰でも身につけられる能力です。
また、金銭トラブルについても、平均よりやや高いIQの人が最も安定していることがわかりました。高すぎるIQだと過信に陥りやすく、低すぎると収入確保に苦労するからかもしれません。
結論として、頭の良さより大切なのは健全な金銭習慣です。計画的な貯蓄、衝動買いの抑制、将来への備え、そして自分の経済状況に合った生活水準を維持することが成功への道です。それは誰にでも開かれた道なのです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。