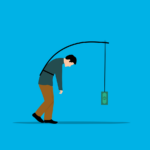「IQと宗教」の関係について、あなたは考えたことがありますか?
実は、知能が高い人ほど宗教的な傾向が低いという研究結果があるんです。これは単なる偶然ではなく、科学的に裏付けられた事実なんです。
「知能と宗教性の関係:メタ分析と提案される説明」という論文では、63もの研究結果を分析した結果、両者の間には負の相関関係があることが明らかになりました。
でも、なぜそんな関係があるのでしょうか?それには様々な理由が考えられます。
この記事では、IQと宗教の関係について科学的に解説します。あなたの考え方や信念を否定するものではなく、人間の心理をより深く理解するための手がかりとして読んでいただければと思います。
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

IQと宗教の関係:科学的研究が示す意外な事実
知能IQと宗教の関係とは?最新研究の発見
知能が高い人ほど宗教的な傾向が低いことが研究から明らかになっています。
これは偶然の一致ではなく、科学的に裏付けられた事実です。
「知能」とは問題を解決したり、新しい考えを理解したりする能力のことをいいます。
一方で「宗教性」とは神や超自然的な存在を信じる度合いを指します。
この二つの間には「負の相関関係」があるのです。
つまり、一方が高くなると、もう一方が低くなる傾向があります。
最新の研究では、63もの異なる調査結果を集めて分析しました。
この分析方法を「メタ分析」と呼びます。
結果として、知能指数IQと宗教心の間には明確な関連性があったのです。
ただし、この関係性は単純ではありません。
例えば、以下のような違いがあります。
- 大人と子どもでは関連の強さが異なる
- 宗教的な信念と宗教的な行動では関連の強さが異なる
- 文化や社会環境によっても影響を受ける
この発見は人間の心理や社会のあり方を考える上で重要な手がかりになります。
知能と宗教性の関係を理解することで、人間の思考パターンや信念形成の仕組みをより深く知ることができるのです。
負の相関とは?シンプルに解説
「負の相関」とは二つの要素が反対方向に変化する関係のことです。
例えば、一方が増えると、もう一方が減る現象を指します。
IQと宗教の場合、知能が高い人ほど宗教的な傾向が低くなっています。
逆に、知能が低めの人は宗教的な傾向が強くなりやすいのです。
相関関係は「r」という値で表されます。
この値は-1から+1の間で変動します。
0に近いほど関係が弱く、±1に近いほど関係が強いことを示します。
IQと宗教の間の相関係数は約-0.24と報告されています。
この数値はそれほど大きくありませんが、統計学的には意味のある値です。
ただし、ここで重要なポイントがあります。
相関関係は「因果関係」を示すものではないのです。
つまり、こうした事実から「IQが高いから無宗教になる」とか「宗教を捨てればIQが上がる」といった単純な結論は導けません。
相関関係にはいくつかの解釈可能性があります。
- 第三の要因が両方に影響している可能性
- 社会的・文化的背景の影響
- 思考スタイルの違い
負の相関関係は現象を示すだけで、その背後にある理由は別途検討する必要があるのです。
メタ分析で分かった研究結果の信頼性
メタ分析とは複数の研究結果を統合して分析する手法です。
個々の研究よりも信頼性の高い結論を導くことができます。
ザッカーマンらの研究チームは、IQと宗教に関する63の異なる調査を分析しました。
これによって、単独の研究では見えなかった全体像が明らかになったのです。
メタ分析の強みは、サンプル数の増加です。
調査対象者が多いほど、結果の信頼性は高まります。
今回の研究では何万人もの人々のデータが含まれていました。
また、様々な国や地域のデータを含んでいる点も重要です。
さらに、研究手法や測定方法の違いを超えた一貫性も確認できました。
これらの要素から、IQと宗教の関係は偶然ではないと言えるのです。
メタ分析で明らかになった興味深い点として:
- 時代を超えて一貫した関連性がある
- 様々な宗教で同様の傾向が見られる
- 異なる知能測定方法でも同様の結果が得られる
このように、メタ分析によって単一の研究では得られない強固な証拠が得られました。
ただし、完全に確定した結論というわけではありません。
今後も研究は続き、より詳細な理解が進むでしょう。
年齢層による違い:IQと宗教は子供と大人で異なる傾向
IQと宗教の関係は年齢層によって大きく異なることが分かっています。
特に、子供と大人では傾向に違いがあります。
研究では対象者を3つのグループに分けて調査しました。
小中高生、大学生、そして一般の成人です。
すると、興味深い結果が明らかになりました。
小中高生では、IQと宗教の負の相関は弱いのです。
この年齢層では相関係数は約-0.08しかありませんでした。
一方、大学生や一般成人ではIQと宗教の負の相関が強くなります。
大学生と一般成人の相関係数は-0.20から-0.25に達します。
なぜこのような違いがあるのでしょうか。
その理由としていくつかの説明が考えられます。
- 子供は親の宗教観に強く影響される
- 成長とともに自分自身の考えを形成していく
- 大人になるほど知的能力と宗教の選択に関連が生じる
- 教育や社会経験が増えることによる影響
このように、IQと宗教の関係は単純ではなく、発達段階によって変化するのです。
子供の頃は周囲の環境の影響が強いため、個人の知能による差が現れにくいと考えられています。
IQと宗教的信念と宗教的行動の違い
IQは宗教的な行動よりも宗教的な信念とより強い関連があります。
これは興味深い発見です。
宗教的信念とは、神の存在を信じるなどの内面的な考えのことです。
一方、宗教的行動とは礼拝に参加するなどの外面的な活動を指します。
研究によると、知能が高い人ほど宗教的信念が弱い傾向があります。
しかし、宗教的行動との関連はそれほど強くありません。
この違いはなぜ生じるのでしょうか。
重要な理由の一つは、行動の動機の多様性です。
宗教的な行動には様々な理由があります。
例えば:
- 社会的なつながりを求めて
- 文化的な習慣として
- 家族の伝統を守るため
- 地域社会への帰属意識から
つまり、宗教的行動は必ずしも強い信仰心から来るわけではないのです。
知能の高い人でも、社会的な理由から宗教的行動に参加することはあります。
ところが、内面的な信念となると、より論理的・分析的な思考の影響を受けやすくなるのです。
このことから、知能と宗教の関係を考える際には、信念と行動を区別することが大切だと言えます。
IQと宗教の負の相関関係が起こる理由
非同調説:知的な人は既存の考えに従わない?
知的な人は周囲の意見に合わせにくい傾向があります。
これを「非同調性」と呼びます。
研究によると、知能が高い人ほど集団の圧力に抵抗します。
つまり、みんなが信じていることをそのまま受け入れません。
多くの社会では宗教が主流の考え方です。
そのため、非同調的な人は宗教的でない可能性が高まります。
知的な人は自分自身で考え、判断する傾向があるのです。
彼らは情報を批判的に検討します。
また、複数の視点から物事を見ることができます。
こうした思考特性が宗教的な教えへの疑問につながるのです。
非同調性は以下のような特徴と関連しています:
- 独自の考えを持つ
- 社会的な圧力に屈しにくい
- 伝統や慣習に縛られない
- 新しい考え方に開かれている
ただし、全ての知的な人が非同調的というわけではありません。
また、非同調性が常に良いものとも限りません。
集団の知恵には価値がある場合もあります。
非同調説は、知能と宗教の負の関係を説明する一つの可能性です。
知的な人が宗教から離れる傾向にあるのは、既存の考えに従わない性質が影響している可能性があるのです。
分析的思考スタイル:直感より論理を重視
知能が高い人ほど分析的な思考スタイルを持つ傾向があります。
分析的思考とは、物事を論理的に考え、証拠に基づいて判断することです。
これは直感的思考と対照的です。
直感的思考は素早く、自動的に結論を出します。
一方、分析的思考はゆっくりと慎重に情報を処理します。
研究によると、分析的思考は宗教的信念を弱める効果があります。
なぜなら、宗教的な考えの多くは直感に基づいているからです。
例えば、多くの人は以下のような直感を持っています:
- 目的のある出来事には設計者がいるはず
- 心と体は別物である
- 死後も意識は存在し続ける
分析的思考はこうした直感に疑問を投げかけます。
証拠がないことや論理的矛盾を指摘するのです。
実験でも、分析的思考を活性化させると宗教的信念が一時的に弱まることが示されています。
知能の高さと分析的思考には強い関連があります。
そのため、知能が高い人は宗教的な考え方から距離を置く傾向があるのです。
分析的思考と宗教の関係は、IQと宗教の負の相関を説明する重要な要因の一つと考えられています。
機能的等価性とは?IQが宗教の役割を代替する
宗教と知能は似たような心理的機能を果たしています。
これを「機能的等価性」と呼びます。
宗教は人々に様々な心理的メリットを提供します。
例えば、不安の軽減や心の安定などです。
興味深いことに、高い知能も同様の効果をもたらすのです。
つまり、宗教が提供するものを知能でも得られるということです。
宗教と知能が共通して提供する機能には以下のようなものがあります:
- 世界を理解し、予測可能にする
- 困難な状況でコントロール感を与える
- 自己価値感を高める
- 社会的なつながりを促進する
知能が高い人は、こうした機能を宗教なしでも得られます。
彼らは問題解決能力が高く、ストレスへの対処も上手です。
また、社会的なスキルも優れている傾向があります。
そのため、宗教に頼る必要性が低くなるのです。
この考え方によれば、宗教は知能の低い人にとってより重要な役割を果たします。
彼らにとって宗教は、知能が提供できない心理的サポートを提供してくれるのです。
機能的等価性の考え方は、なぜ知能と宗教の間に負の相関があるのかを説明する有力な理論の一つです。
宗教と知能が同じニーズを満たすなら、一方が強ければもう一方への依存が減るのは自然なことなのです。
自己制御能力:知能が高いと自制心も高い?
知能の高い人は自己制御能力が優れていることが多くの研究で示されています。
自己制御能力とは、衝動を抑え、行動をコントロールする力です。
これは人生の様々な場面で重要な役割を果たします。
例えば、目標達成や対人関係の維持などです。
興味深いことに、宗教も自己制御を促進します。
宗教的な教えは多くの場合、自制を重視しています。
神の存在を信じることで、人は自分の行動を律しやすくなるのです。
研究によると、知能と自己制御能力の間には強い関連があります。
知能が高い人ほど:
- 誘惑に負けにくい
- 長期的な目標のために短期的な快楽を我慢できる
- ストレスを効果的に管理できる
- 計画的に行動できる
このような自己制御能力があれば、宗教がなくても自分をコントロールできます。
つまり、知能の高い人は宗教の助けなしでも自分を律することができるのです。
一方、知能が平均的な人は宗教を通じて自己制御を強化できます。
これが知能と宗教の負の相関関係の一因と考えられています。
知能と宗教はどちらも自己制御という同じ機能を提供するため、一方が強ければもう一方への依存度が下がるという仕組みなのです。
社会的環境の影響:教育と知能の複雑な関係
社会的環境は知能と宗教の関係に大きく影響します。
特に教育は重要な要素です。
教育レベルが高いほど、宗教性が低下する傾向があります。
しかし、この関係は単純ではありません。
教育と知能は密接に関連していますが、別物です。
知能が高い人ほど教育を長く受ける傾向があります。
また、教育自体が批判的思考を促進します。
そして、批判的思考は宗教的信念に疑問を投げかけることがあるのです。
さらに、社会環境の影響には以下のような要素があります:
- 大学環境での多様な価値観との出会い
- 科学的知識の獲得
- 伝統的な考えへの批判的視点の発達
- 異なる文化や宗教への理解の深まり
興味深いことに、研究結果では教育の影響を取り除いても、知能と宗教の負の相関は残ります。
つまり、教育だけでは説明できない関係があるのです。
また、家庭環境も重要な役割を果たします。
知的な親ほど子どもに宗教的な教育を施さない傾向があります。
このように、社会的環境は複雑な形で知能と宗教の関係に影響しています。
単一の要因ではなく、様々な社会的・環境的要素が組み合わさって、IQと宗教の間の負の相関を形成しているのです。
IQと宗教の研究から見えてくる人間の心理
宗教がもたらす精神的安定とは
宗教は多くの人に心の安定をもたらします。
これは宗教の重要な機能の一つです。
不確かな世界で生きる人間にとって、宗教は安心感を与えてくれます。
「なぜ生きるのか」という根本的な問いに答えを提供するのです。
宗教の精神的安定効果はいくつかの形で現れます。
まず、宗教は世界に意味を与えます。
偶然の出来事も神の計画の一部と考えられるからです。
次に、死の恐怖を和らげる効果があります。
多くの宗教は死後の世界を教えているからです。
さらに、宗教は以下のような心理的メリットをもたらします:
- 所属感と社会的支援
- 困難な時の心の支え
- 道徳的な指針
- 罪悪感からの解放
- 人生の目的意識
研究によると、宗教的な人は精神的健康度が高い傾向があります。
うつ病や不安障害になりにくいというデータもあります。
また、危機的状況においては特に宗教の効果が高まります。
例えば、病気や死別といった困難な経験の際には、宗教が心の支えになるのです。
このように、宗教は人間の心に安定をもたらす重要な役割を果たしています。
知能の高さに関わらず、多くの人が宗教から精神的な安定を得ているのです。
知能が高い人の特徴的な考え方
まず知能が高い人には特徴的な思考パターンがあります。
それが宗教観にも影響しているのです。
まず、抽象的思考が得意です。
複雑な概念を理解し、操作することができます。
また、批判的思考も特徴の一つです。
情報を鵜呑みにせず、証拠を求める傾向があります。
さらに、知能の高い人は以下のような思考の特徴を持ちます:
- 多角的な視点から問題を見られる
- 曖昧さや不確かさに耐えられる
- 因果関係を正確に理解できる
- 長期的な視点で考えられる
こうした思考特性は宗教的な考え方と衝突することがあります。
宗教は時に単純な答えや確実性を求めるからです。
また、知能の高い人は自分の信念を常に見直す傾向があります。
新しい証拠や論理に基づいて考えを変えるのです。
一方、宗教的信念は変わりにくい性質があります。
伝統や権威に基づいていることが多いからです。
これらの違いが、知能の高い人が宗教から離れる一因となっています。
ただし、すべての知的な人が非宗教的というわけではありません。
知的で宗教的な人も多く存在しており、彼らは信仰と理性を調和させる独自の方法を見つけているのです。
不確実性への対処法:宗教vs論理的思考
人は不確かな世界で安心するために様々な方法を使います。
宗教と論理的思考はその代表例です。
宗教は不確実性に対して確かな答えを提供します。
「神の計画がある」という考えは安心感をもたらすのです。
一方、論理的思考は不確実性を分析し、理解しようとします。
それによって、予測や対策が可能になります。
両者の違いは対処アプローチにあります。
宗教は外部の力に頼ります。
しかし、論理的思考は自分の能力を信頼します。
不確実性への対処方法には以下のようなものがあります:
- 宗教:祈り、信仰、神の存在を信じること
- 論理的思考:情報収集、分析、確率的思考
研究によると、知能が高い人ほど不確実性に耐える力があります。
彼らは曖昧な状況でも冷静に判断できるのです。
そのため、確かな答えを提供する宗教への依存度が低くなります。
また、知能が高い人は問題解決能力も優れています。
困難な状況でも自分で解決策を見つけられるのです。
このように、不確実性への対処方法の違いが知能と宗教の関係に影響しています。
知能が高い人は論理的思考で不確実性に対処できるため、宗教に頼る必要性が低くなるのです。
社会的つながりを求める心理と宗教の関係
人間には社会的つながりを求める根本的な欲求があります。
宗教はこの欲求を満たす強力な手段です。
宗教的なコミュニティは所属感を提供します。
同じ信仰を持つ人々との絆は強いものになります。
宗教が社会的つながりを促進する理由はいくつかあります。
まず、共通の価値観や信念があります。
また、定期的な集まりの機会があります。
さらに、相互扶助の精神が強調されています。
宗教的な集まりがもたらす社会的メリットには以下のようなものがあります:
- 情緒的サポート
- 実質的な助け合い
- 人生の重要な出来事の共有
- 孤独感の軽減
興味深いことに、知能の高い人も社会的つながりを求めます。
しかし、彼らは宗教以外の場でそれを見つけることが多いのです。
例えば、職場や趣味のコミュニティなどです。
また、知能の高い人は一人でいる時間も楽しめる傾向があります。
そのため、社会的つながりへの依存度が低いかもしれません。
さらに、知能の高い人は結婚率が高く、離婚率が低い傾向があります。
これは親密な関係を通じて社会的ニーズを満たしている可能性を示しています。
このように、社会的つながりを求める心理は宗教と知能の関係に影響しているのです。
両者は異なる方法で社会的ニーズを満たしているため、知能の高い人の宗教離れにつながっているのかもしれません。
文化による違い:世界の宗教観と知能の関係
宗教と知能の関係は文化によって大きく異なることがわかっています。
世界各地の研究では興味深い違いが見られます。
例えば、北欧諸国では宗教性が全体的に低いです。
そのため、知能との関連も他の地域と異なるパターンを示します。
文化による違いの主な要因は社会環境です。
宗教が主流の社会では、無宗教であることは非同調的です。
一方、世俗的な社会では、宗教的であることが非主流になります。
各文化での宗教と知能の関係には以下のような違いがあります:
- 宗教的な社会:知能と宗教の負の相関が強い
- 世俗的な社会:相関が弱いか異なるパターンを示す
- 宗教的多様性がある社会:複雑な関係が見られる
また、宗教のタイプによっても関係性が変わります。
教義を重視する宗教と実践を重視する宗教では違いがあるのです。
例えば、プロテスタントは個人的な信仰を重視します。
一方、ユダヤ教やカトリックでは実践や儀式も同様に重要視します。
さらに、教育システムの違いも影響します。
宗教教育が一般的な国と世俗的教育が主流の国では状況が異なります。
このように、文化的背景は知能と宗教の関係に大きな影響を与えています。
単純に「知能が高いから無宗教」という図式ではなく、文化的文脈を考慮することが重要なのです。
IQと宗教の研究が示唆する現代社会への影響
教育レベルの向上と宗教離れの関係
世界的に教育レベルが向上するにつれて宗教離れが進んでいる傾向があります。
これは多くの国で観察される現象です。
高等教育を受けた人の割合が増えるにつれて、宗教的な人の割合は減少しています。
この関係には複数の要因が影響しています。
まず、教育は批判的思考を促進します。
これにより既存の信念に疑問を持つようになるのです。
次に、教育は科学的な世界観を教えます。
これが宗教的な説明と対立することがあります。
教育と宗教離れの関係には以下のような要素があります:
- 多様な価値観への接触
- 論理的・分析的思考の訓練
- 科学的知識の習得
- 伝統からの自立
しかし、この関係は単純ではありません。
教育を受けても宗教的な人は多く存在します。
特に、宗教的な教育機関では異なる傾向が見られます。
また、宗教のあり方自体も変化しています。
伝統的な宗教から離れても、スピリチュアルな信念を持つ人は増えています。
このように、教育の普及は宗教のあり方に大きな影響を与えています。
しかし、宗教がなくなるというよりも、その形が変化していると考えるべきでしょう。
教育の普及とともに、より個人化され、柔軟な形の宗教性が広がっているのです。
デジタル時代の情報アクセスと宗教観の変化
インターネットの普及により宗教に関する情報へのアクセスが劇的に変化しました。
これは宗教観に大きな影響を与えています。
かつては宗教的知識は限られた人だけが持っていました。
しかし今では誰でも様々な宗教について学べます。
デジタル時代の変化には多くの側面があります。
まず、多様な宗教への接触が容易になりました。
また、宗教的教えへの批判的視点も広がっています。
さらに、オンラインでの宗教的コミュニティも形成されています。
情報アクセスの変化がもたらす影響には以下のようなものがあります:
- 宗教選択の個人化
- 伝統的な宗教機関の権威の低下
- 異なる宗教の混合(シンクレティズム)
- 「無宗教だが精神的」という立場の増加
知能が高い人ほどこうした情報を活用する傾向があります。
多様な情報を整理し、自分の考えを形成できるからです。
一方で、情報の氾濫は混乱も招いています。
誤情報や偏った情報も多く広がっているのです。
興味深いことに、デジタル時代でも宗教は消滅していません。
むしろ、新しい形で存続しています。
オンライン礼拝やアプリを通じた瞑想など、宗教実践も変化しているのです。
このように、デジタル時代の情報アクセスは宗教観を大きく変えています。
知能と宗教の関係も、こうした時代背景の中で考える必要があるのです。
若い世代の価値観の変化と宗教
若い世代は伝統的な宗教から離れる傾向が世界的に見られます。
これは単なる反抗期ではなく、価値観の本質的な変化です。
若者の宗教観には大きな変化が起きています。
特に先進国ではその傾向が顕著です。
若い世代の価値観変化には様々な要因があります。
まず、個人の自由や選択を重視する傾向があります。
また、多様性や包括性を重んじる姿勢も特徴的です。
さらに、環境問題や社会正義への関心が高まっています。
若い世代と宗教の関係に見られる特徴として:
- 組織化された宗教への不信感
- スピリチュアルだが宗教的ではない立場
- 複数の宗教からの選択的な取り入れ
- 科学と共存できる宗教観の模索
興味深いことに、若い世代の知能と宗教の関係も変化しています。
以前より相関が弱まっているという研究結果もあります。
これは宗教のあり方自体が変化しているからかもしれません。
伝統的な教義より個人的な精神性を重視する傾向があるのです。
また、若い世代は社会的なつながりを別の方法で求めています。
SNSやオンラインコミュニティがその役割を果たしているのです。
このように、若い世代の価値観の変化は宗教観にも大きな影響を与えています。
知能の高さに関わらず、若者は従来とは異なる形で精神性や意味を追求しているのです。
科学と宗教は対立するのか?共存の可能性
科学と宗教は必ずしも対立するものではないという見方が広がっています。
両者の関係は複雑で、単純な対立図式では捉えきれません。
確かに、科学的知識と宗教的教えが衝突することはあります。
進化論と創造説の議論はその代表例です。
しかし、多くの科学者は宗教を持っています。
また、多くの宗教的な人も科学的知識を受け入れています。
科学と宗教の関係には以下のような可能性があります:
- 別の領域として共存(非重複的教導権)
- 相互補完的な関係
- 対話を通じた理解の深化
- 異なる種類の問いに答える役割分担
非重複的教導権(NOMA)という考え方では、科学と宗教は異なる領域を扱うとされます。
科学は「いかに」という問いに、宗教は「なぜ」という問いに答えるのです。
また、現代の神学では科学的知見を取り入れる努力がなされています。
宗教的教えを現代の知識と調和させようとしているのです。
知能の高い宗教的な人々は、しばしばこうした統合的な視点を持っています。
彼らは批判的思考と信仰を両立させているのです。
このように、科学と宗教は対立するだけでなく、共存や対話の可能性も持っています。
知能と宗教の関係を考える際にも、こうした複雑な視点が重要なのです。
多様性を認め合う社会における宗教の役割
現代社会では多様な価値観や信念を尊重することが重要になっています。
そうした中で宗教の役割も変化しています。
多様性を認める社会では宗教間の対話が進んでいます。
異なる信仰を持つ人々が互いを理解しようとしているのです。
宗教は現代社会で新たな役割を果たしています。
例えば、コミュニティの形成を助ける役割です。
また、道徳的な指針を提供する機能も依然として重要です。
さらに、社会問題に取り組む原動力にもなっています。
多様性を尊重する社会での宗教の役割には以下のようなものがあります:
- 異文化理解の促進
- 寛容と尊重の価値観の実践
- 社会的弱者への支援活動
- 対話と和解の場の提供
知能の高い人々も、こうした宗教の社会的役割を評価しています。
批判的思考と宗教的価値観が両立する場面も増えているのです。
また、宗教組織自体も変化しています。
より開かれた姿勢や多様性への理解を示す傾向があります。
このように、多様性を尊重する社会において宗教は新たな意義を見出しています。
知能と宗教の関係も、こうした社会変化の中で再評価される可能性があるのです。
宗教は単なる信条体系ではなく、多様な人々が共生するための知恵や実践として捉え直されているのです。
最後に
IQと宗教の関係について見てきましたが、この二つの間には確かに負の相関関係があるようです。知能が高い人ほど宗教的傾向が低い傾向があります。
しかし、これは単純な「賢い人は宗教を信じない」という話ではありません。その背景には、分析的思考スタイル、非同調性、そして宗教と知能が提供する機能の重複などの複雑な要因があります。
また、文化や年齢によっても関係性は変わります。子どもの頃はほとんど関係がなく、大人になるにつれて関連性が強まるのは興味深い事実です。
重要なのは、これらの研究結果は個人の宗教的選択を否定するものではないということです。宗教は多くの人に心の安定や社会的つながりをもたらしており、その価値は知能の高さとは別次元のものです。
現代社会では、宗教のあり方自体も変化しています。科学と宗教の共存や対話の可能性も広がっています。これからの時代、多様な価値観を認め合いながら、それぞれの形で心の豊かさを追求していくことが大切なのではないでしょうか。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。