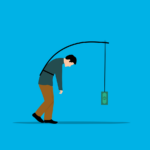知能の遺伝について、あなたはどのくらい知っていますか? 「頭の良さは親から受け継ぐもの?」「勉強しても無駄?」など、知能と遺伝に関する疑問を持ったことはありませんか。
実は、知能がどれだけ遺伝するかは年齢によって大きく変わります。科学者たちはこれを「ウィルソン効果」と呼んでいます。
「The Wilson Effect: The Increase in Heritability of IQ With Age」という研究が明らかにしたのは、子どもの頃は環境の影響が大きいけれど、大人になるにつれて遺伝の影響が強まるという驚きの事実です。
でも安心してください。遺伝率が高いからといって、努力が無駄になるわけではありません。むしろ、どの年齢でも適切な方法で学ぶことで知能は伸びます。
この記事では、知能の遺伝について最新の研究結果をわかりやすく解説します。あなたの知能をより良く理解し、効果的に伸ばすヒントが見つかるはずです。さあ、知能の不思議な世界を一緒に探検してみましょう!
今回も、性格研究者で悪者図鑑著者のトキワ(@etokiwa999)が解説していきます。
※HEXACO-JP性格診断を開発しました!MBTIより科学的根拠があります。詳細は以下タップしてください。

知能の遺伝とは?その基本を理解しよう
知能指数(IQ)と遺伝の関係性
知能指数(IQ)は遺伝と環境の両方の影響を受けています。
IQ、つまり知能指数とは、人の知的能力を数値化したものです。
平均は100点とされています。
この数値は、どれくらい家系から受け継いだものなのでしょうか。
実は、知能は単一の遺伝子では決まりません。
多くの遺伝子が複雑に関わっているのです。
また、環境も大きく影響します。
つまり、知能は「生まれ」と「育ち」の両方で形作られるのです。
しかし、その割合は年齢によって変化します。
これが「ウィルソン効果」と呼ばれる現象です。
科学者たちは、以下の研究方法で遺伝の影響を調べてきました:
- 一卵性双生児の比較(遺伝子が同じ)
- 二卵性双生児の比較(遺伝子が半分共通)
- 養子研究(環境の影響を分離)
最近の研究では、知能の遺伝的要素は年齢とともに強くなることがわかっています。
子どもの頃は環境の影響が大きいですが、大人になるにつれて遺伝の影響が強まるのです。
知能の遺伝と環境の関係を理解することで、自分や子どもの知的発達をより適切に支援できるようになるでしょう。
遺伝率とは何か?簡単に説明
遺伝率とは、ある特性の個人差のうち遺伝が原因となる割合のことです。
この値は0から1の間で表されます。
0は「全く遺伝の影響がない」という意味です。
1は「完全に遺伝で決まる」という意味になります。
例えば、身長の遺伝率は約0.8(80%)とされています。
これは個人の身長差の80%が遺伝によるものだということです。
残りの20%は環境の影響ということになります。
遺伝率は集団の中での違いを説明するものです。
個人の特性がどれくらい遺伝するかを示すものではありません。
また、遺伝率は研究対象となる集団によって変わります。
同じ特性でも、異なる国や時代では値が違うのです。
遺伝率を調べるには以下の方法が使われます:
- 双子研究(一卵性と二卵性の比較)
- 家族研究(親子や兄弟の類似性)
- 養子研究(生物学的親と養親の影響比較)
なお、遺伝率が高いからといって、環境が重要でないわけではありません。
遺伝と環境は複雑に相互作用します。
遺伝率は特性の変化しやすさを示すものではなく、現在の集団における遺伝的影響の大きさを示すものなのです。
「ウィルソン効果」とはどんな現象なのか
「ウィルソン効果」とは知能の遺伝率が年齢とともに増加する現象です。
この名前は研究者ロナルド・ウィルソンにちなんでいます。
彼は1970年代にこの現象を初めて明確に示しました。
子どもの頃は知能の遺伝率が比較的低いのです。
しかし、成長するにつれて遺伝の影響が強まります。
具体的な数字を見てみましょう:
- 5歳頃:遺伝率約40%
- 10歳頃:遺伝率約55%
- 18歳頃:遺伝率約80%
これは大変興味深い発見です。
年齢とともに環境の影響が弱まっていくのです。
特に18〜20歳で遺伝率はピークに達します。
そしてその後も高い水準を維持します。
なぜこのような変化が起こるのでしょうか。
その理由として以下が考えられています:
- 年齢によって異なる遺伝子が働く
- 成長とともに自分に合った環境を選ぶようになる
- 脳の発達パターンが遺伝的に決まっている
ウィルソン効果は、知能の発達における遺伝と環境の役割を理解する上で非常に重要な概念です。
知能研究における双子研究の重要性
双子研究は知能の遺伝率を測る最も強力な方法の一つです。
特に一卵性双生児は遺伝的に100%同じです。
二卵性双生児は普通の兄弟姉妹と同じく50%共通しています。
この違いを利用して遺伝の影響を計算するのです。
例えば、知能テストの点数の類似度を比較します。
一卵性双生児の方が二卵性より似ていれば、遺伝の影響があるといえます。
さらに興味深いのが「離れて育った双子」の研究です。
別々の家庭で育ったのに似た知能を持っていれば、遺伝の影響が強いと考えられます。
ミネソタ大学の研究では、離れて育った一卵性双子でも知能に高い類似性が見られました。
これは遺伝の重要性を示す強力な証拠です。
双子研究から分かった主な事実は以下の通りです:
- 一卵性双生児の知能の相関は0.8程度と非常に高い
- 二卵性双生児の相関は0.6程度
- この差は遺伝の影響を示している
- 年齢とともに差が大きくなる
双子研究は方法論的な批判もありますが、異なる研究手法でも同様の結果が得られており、知能の遺伝的影響に関する重要な知見を提供しています。
知能の遺伝に関する一般的な誤解
知能の遺伝について多くの誤解が広まっています。
まず「知能が遺伝するなら努力は無意味」という誤解です。
これは全く正しくありません。
遺伝率が高くても環境の影響は必ずあります。
次に「親が賢ければ子どもも必ず賢い」という思い込みです。
実際には確率的な傾向があるだけです。
多くの例外があり、予測は困難です。
また「知能は単一の遺伝子で決まる」という誤解もあります。
実際は数百から数千の遺伝子が関わっています。
「遺伝率80%なら環境の影響は20%だけ」という解釈も間違いです。
遺伝と環境は相互に作用するため、単純な足し算にはなりません。
他にもよくある誤解には以下があります:
- 「知能は固定されている」
- 「遺伝的に決まった能力の限界がある」
- 「環境を変えても知能は変わらない」
これらはすべて科学的に正しくありません。
知能は「頑丈で柔軟なシステム」であることが研究からわかっています。
環境の影響は年齢とともに変化しますが、完全になくなることはありません。
知能の遺伝に関する正確な理解は、教育や子育てにおいて適切な期待と支援を提供するために重要です。
知能の遺伝率が年齢とともに変化する理由
幼少期の知能と環境の影響
幼少期(0〜7歳頃)の知能は環境の影響を強く受けます。
この時期の知能の遺伝率は約40%程度です。
つまり、個人差の60%は環境によるものです。
子どもの脳は急速に発達しています。
新しい経験に対して非常に敏感な時期なのです。
親の関わり方が大きく影響します。
読み聞かせや会話の量も重要です。
栄養状態も脳の発達に影響を与えます。
家庭の経済状況も間接的に関わってきます。
幼少期の主な環境要因には以下があります:
- 親との愛着関係の質
- 言語的刺激の豊かさ
- 遊びや探索の機会
- 基本的な健康管理
- ストレスの少なさ
研究によると、同じ家庭で育った子どもたちは知能が似る傾向があります。
これは共有環境の影響を示しています。
しかし年齢が上がるにつれ、この影響は弱まっていきます。
それでも幼少期の環境は生涯にわたって影響を残すこともあります。
幼少期は知能発達の土台を作る重要な時期であり、良質な環境を提供することが子どもの将来の知的発達を支える鍵となります。
思春期における知能の遺伝的要素の増加
思春期になると知能の遺伝率は約60%まで上昇します。
この変化には重要な意味があります。
子どもは徐々に自分の環境を選び始めるのです。
本や趣味など、自分に合ったものを選択します。
これは「能動的遺伝」と呼ばれる現象です。
遺伝的傾向に合わせて環境を自ら選ぶのです。
また、思春期には脳の発達も進みます。
特に前頭葉の成熟が進行します。
これは理論的思考や判断力に関わる部分です。
この時期の遺伝的影響の増加は双子研究で確認されています。
一卵性双生児の類似性が維持される一方、二卵性双生児の類似性は低下していきます。
思春期における知能の発達に影響する要因には:
- 学校教育の質と適合性
- 友人関係や社会的環境
- 自己選択による学習機会
- ホルモン変化と脳の発達
- 新しい挑戦への取り組み方
この時期は自分の強みや弱みを理解し始める大切な段階です。
親や教師は子どもの遺伝的傾向を尊重しながら、適切な選択をサポートすることが重要です。
思春期は知能における遺伝と環境の相互作用が変化する転換点であり、個人の主体性が増す時期です。
18〜20歳で知能の遺伝率がピークを迎える現象
18〜20歳になると知能の遺伝率は約80%に達します。
これがウィルソン効果の最も注目すべき点です。
成人初期に遺伝率がピークを迎えるのです。
この時期は大きな変化の時です。
多くの人が親元を離れます。
進学や就職で新しい環境に移ります。
自分で人生の選択をする機会が増えます。
遺伝率が高いということは何を意味するのでしょうか。
それは環境の偶然の影響が少なくなるということです。
人は自分の遺伝的傾向に合った環境を選ぶようになります。
知的好奇心が高い人は刺激的な環境を求めます。
実践的思考が得意な人は別の環境を選ぶでしょう。
この現象が示すいくつかの重要な点:
- 知能は「壊れやすいガラス」ではない
- 脳は頑健で回復力のあるシステムである
- 成人期には自己選択が環境の影響より強くなる
- 個人の傾向に合った環境が重要になる
研究者たちはこの現象を「ジーン・エンバイロンメント・コリレーション」と呼びます。
遺伝と環境が相互に影響し合うことを指す言葉です。
18〜20歳で遺伝率がピークに達する現象は、自律性の獲得と自己実現の過程を反映しており、人生の選択における個人の主体性の重要性を示しています。
成人期の知能はどれだけ遺伝の影響を受けるのか
成人期の知能の遺伝率は約80%と非常に高い水準です。
この数値は20歳以降も安定して維持されます。
つまり、成人の知能差の大部分は遺伝に由来します。
しかし、これは個人の知能が変わらないという意味ではありません。
むしろ、変化の仕方に遺伝が影響するのです。
成人でも知能は向上することがあります。
新しいスキルを学ぶことで認知能力は高まります。
また、専門分野での深い知識も発達します。
遺伝率が高いと言われても、諦める必要はないのです。
重要なのは自分に合った方法で学ぶことです。
成人期の知能に影響する要因には以下があります:
- 職業や専門性の選択
- 継続的な学習と挑戦
- 認知的に刺激のある環境
- 健康状態の管理
- 社会的なつながり
高齢になると認知能力の個人差はさらに広がります。
健康状態などの影響も大きくなります。
それでも80歳を超える高齢者でも、健康な場合は遺伝率が60%以上あることが研究で示されています。
成人期の知能における高い遺伝率は、私たちが自分の強みを活かし、弱みを補う戦略を見つけることの重要性を示唆しています。
脳の発達と知能の遺伝率の関係
脳の発達パターンは知能の遺伝率変化と密接に関連しています。
まず脳は単純に大きくなるだけではありません。
発達には特定のスケジュールがあるのです。
幼少期は脳の「配線」が急速に形成されます。
シナプス(神経細胞の接続)が増加するのです。
その後、使われない接続は刈り込まれていきます。
これを「シナプスの刈り込み」と呼びます。
この過程は遺伝的に制御されています。
思春期には前頭前皮質という部分が発達します。
この部分は高度な思考や判断に関わります。
脳の構造自体も遺伝の影響を強く受けます。
例えば以下の特性には高い遺伝率があります:
- 脳の全体的な容積
- 灰白質の厚さ
- 白質の構造
- 脳領域間の接続パターン
- 神経伝達物質のバランス
面白いことに、脳の構造と知能の関係も部分的に遺伝します。
つまり、特定の脳の特徴が知能と関連する傾向も遺伝するのです。
年齢とともに脳の発達は遺伝的プログラムに従って進み、それが知能の遺伝率増加という形で表れます。
これは単なる偶然ではなく、進化の過程で形作られた適応的なパターンなのです。
知能の遺伝研究から分かった驚きの事実
一卵性双生児と二卵性双生児の知能の一致度の違い
一卵性双生児の知能の一致度は二卵性双生児よりはるかに高いです。
これは知能の遺伝的影響を示す重要な証拠です。
一卵性双生児は遺伝子が100%同じです。
二卵性双生児は平均50%が同じです。
研究によると、一卵性双生児の知能の相関は約0.85です。
これは非常に高い数値です。
一方、二卵性双生児の相関は約0.6です。
この差は遺伝の影響を示しています。
さらに興味深いのは年齢による変化です。
子どもの頃は二つの群の差は小さいです。
しかし年齢とともに差が広がっていきます。
一卵性双生児の相関は高いまま維持されます。
二卵性双生児の相関は徐々に低下します。
主な研究結果を見てみましょう:
- 5歳:一卵性0.7、二卵性0.6
- 10歳:一卵性0.8、二卵性0.5
- 18歳:一卵性0.85、二卵性0.4
この現象は「ウィルソン効果」の核心部分です。
年齢とともに遺伝的影響が強まっていくことを示しています。
一卵性と二卵性双生児の知能の一致度の違いとその年齢変化は、知能の発達における遺伝の役割を理解する上で最も説得力のある証拠の一つとなっています。
離れて育った双子の知能の類似性
別々の家庭で育った一卵性双生児でも知能に驚くほどの類似性があります。
これは「離れて育った双子」研究からの発見です。
このような双子は生まれてすぐに別々の家庭に引き取られています。
異なる環境で育つにもかかわらず、知能テストの結果は非常に似ています。
実際、相関係数は約0.74という高さです。
これは遺伝の影響を直接示す強力な証拠です。
共有環境の影響がないからです。
ミネソタ大学の研究は特に有名です。
100組以上の離れて育った双子を調査しました。
一部のケースでは、双子は成人まで会ったことがありませんでした。
それでも知能だけでなく、以下の類似点が見られました:
- 職業の選択
- 趣味や関心
- 認知スタイル
- 問題解決のアプローチ
- 学習の得手不得手
このような類似性は偶然では説明できません。
遺伝的要因が強く影響していると考えるのが合理的です。
一方で、離れて育った双子でも完全に同じではありません。
個人差は依然として存在します。
離れて育った双子の知能の類似性は、私たちの知能が遺伝的要因によって形作られる部分が大きいことを示す最も説得力のある証拠の一つです。
養子研究から明らかになった遺伝と環境の影響
養子研究は知能における遺伝と環境の役割を分離して調べる強力な方法です。
まず養子は生物学的親と異なる環境で育ちます。
これにより遺伝と環境の影響を区別できるのです。
主な発見は以下の通りです。
子どもの知能は生物学的親との相関が高いです。
養親との相関は年齢とともに低下します。
子どもの頃は養親との相関もある程度あります。
つまり、環境の影響は確かに存在するのです。
しかし成人になると、生物学的親との相関だけが残ります。
また、同じ家庭で育った血縁のない子どもたちを調べた研究もあります。
子どもの頃は知能に類似性が見られます。
ところが大人になるとほとんど類似性がなくなるのです。
養子研究から分かった重要なポイント:
- 10歳の養子の知能は養親と約0.26の相関
- 成人の養子の知能は養親とわずか0.04の相関
- どの年齢でも生物学的親との相関は約0.24
- 同じ家庭の血縁のない子どもは大人になると似なくなる
テキサス養子研究プロジェクトなど大規模な調査からも、同様の結果が得られています。
これらの研究は、幼少期の環境は確かに知能に影響するものの、その効果は一時的であり、長期的には遺伝的要因がより重要になることを示しています。
共有環境(家族環境)の影響は年齢とともに減少する
家族環境の影響は年齢とともに驚くほど減少します。
これは知能研究の最も意外な発見の一つです。
子どもの頃は家族環境の影響は約55%あります。
同じ家庭で育った子どもは似る傾向があるのです。
しかし10歳頃から急速に影響が弱まります。
12歳では約28%まで低下します。
18歳では約10%にまで減少するのです。
成人期もこの低い水準が続きます。
これはなぜでしょうか?
一つの説明は「能動的遺伝」です。
成長とともに自分の傾向に合った環境を選ぶようになります。
また、環境への反応の仕方も遺伝の影響を受けます。
同じ経験でも人によって影響が異なるのです。
家族環境の影響減少を示す主な証拠:
- 同じ家庭の非血縁者の類似性の低下
- 養親と養子の知能の相関の低下
- 離れて育った兄弟姉妹の類似性は変わらない
- 別々の家庭で育った一卵性双生児の高い類似性
この現象は多くの国や文化で確認されています。
西洋諸国だけでなく、ロシアや東アジアの研究でも同様の結果が得られています。
家族環境の影響が年齢とともに減少するという発見は、子育てや教育のアプローチに大きな示唆を与えており、個人の独自性と主体性を重視する重要性を示しています。
知能は「壊れやすいガラス」ではなく「回復力のあるシステム」
知能は環境の悪影響に対して驚くほど回復力があることがわかりました。
以前は「紡がれたガラス理論」が主流でした。
これは知能が環境から傷つきやすいという考えです。
人生の困難が積み重なり、知能が低下するという理論です。
しかし研究結果はこれと矛盾します。
実際には知能はかなり安定しています。
一時的な落ち込みからの回復も見られます。
ニュージーランドの「ダニーデン研究」は特に重要です。
1000人以上の子どもを長期追跡した研究です。
知能の一時的な変動はあっても、元の軌道に戻る傾向があることがわかりました。
この回復力を示す主な研究結果:
- 一時的なストレスの後に知能は回復する
- 思春期の知能低下は多くの場合一時的
- 適切な介入で知能は改善できる
- 高齢でも認知トレーニングの効果がある
- 特に健康な高齢者では知能の安定性が高い
この発見は希望を与えるものです。
人生の困難が必ずしも恒久的な知能低下につながるわけではありません。
脳には「自己修復」の能力があります。
適切な環境と支援があれば回復するのです。
知能が「壊れやすいガラス」ではなく「回復力のあるシステム」であるという発見は、教育や介入プログラムにおいて前向きな姿勢をもたらし、どの年齢でも知的発達を促進できる可能性を示しています。
知能の遺伝研究が示す子育てや教育への示唆
子どもの知能を伸ばすために親ができること
子どもの知能発達を支援する最も効果的な方法は「反応性」です。
まず子どもの興味や強みに応じて環境を整えましょう。
全ての子どもに同じ方法は効果的ではありません。
個々の子どもの傾向を観察することが大切です。
特に幼少期は環境の影響が大きいです。
この時期に豊かな刺激を与えることが重要です。
言語環境は特に重要な要素です。
子どもとの会話や読み聞かせを増やしましょう。
質問に丁寧に答えることも効果的です。
子どもの好奇心を尊重することが大切です。
具体的にできることには以下があります:
- 多様な経験の機会を提供する
- 子どもの質問に辛抱強く答える
- 年齢に適した挑戦を与える
- 成功体験を積み重ねさせる
- 学ぶ喜びを共有する
プレッシャーをかけすぎないことも重要です。
過度なストレスは学習を妨げます。
遊びを通じた学習も効果的です。
楽しく学ぶことで自発的な探求が促されます。
子どもの知能を伸ばすには、その子の遺伝的傾向を尊重しながら、適切な挑戦と支援のバランスを取ることが鍵となります。
個々の子どもの持つ遺伝的特性に合わせた教育の重要性
全ての子どもに同じ教育法を適用するのは効果的ではありません。
子どもには生まれながらの得意不得手があります。
これは「認知プロファイル」と呼ばれます。
ある子は言語処理が得意かもしれません。
別の子は視覚・空間認識が優れているかもしれません。
また別の子は音楽的才能があるかもしれません。
これらの違いには遺伝的基盤があります。
画一的な教育はこの多様性を無視してしまいます。
それぞれの強みを活かした教育が理想的です。
具体的なアプローチとしては:
- 学習スタイルの違いを認識する
- 複数の方法で同じ内容を提示する
- 得意分野での成功体験を増やす
- 苦手分野は別のアプローチを試みる
- 興味を引き出す教材を選ぶ
子どもの反応を観察することが重要です。
同じ教材でも反応は様々です。
効果的だった方法を記録しておきましょう。
子どもの特性は時間とともに変化することもあります。
個々の子どもの遺伝的特性に合わせた教育は、子どもの強みを活かし、弱みをサポートすることで、より効果的な学習と健全な自己肯定感の発達を促進します。
環境の影響が最も大きい幼少期の過ごし方
幼少期(0〜7歳)は環境の影響が最も大きい時期です。
この時期の過ごし方が将来に影響します。
脳は急速に発達しています。
新しい経験に対して非常に敏感です。
まず、安全で安定した環境が基本です。
情緒的な安定は学習の土台となります。
次に、言語環境の豊かさが重要です。
多くの言葉に触れることで語彙が増えます。
会話や読み聞かせの時間を増やしましょう。
また、自由な遊びの時間も大切です。
遊びを通して様々なスキルが育まれます。
幼少期に重視すべき経験には以下があります:
- 豊かな対話と読み聞かせ
- 自然と触れ合う体験
- 音楽や芸術活動
- 体を動かす遊び
- 簡単な問題解決の経験
過度な学習プレッシャーは避けるべきです。
楽しく学ぶ姿勢を育てることが大切です。
メディアの使用は適切に制限しましょう。
人との関わりがより重要です。
幼少期は知能の基盤を作る重要な時期であり、豊かで多様な経験と安定した情緒的環境が、子どもの将来の認知発達に長期的な好影響をもたらします。
思春期以降の知能発達をサポートする方法
思春期以降も知能は発達し続けることが研究でわかっています。
この時期は遺伝の影響が強まりますが、環境も重要です。
ただし、アプローチを変える必要があります。
押し付けよりも自主性を尊重することが大切です。
若者は自分の興味に沿って学ぶ傾向があります。
それを支援することが効果的です。
深い思考を促す質問をすることも有効です。
解決策を教えるのではなく考えさせましょう。
また、挑戦的な課題も大切です。
適度な難しさが知的成長を促します。
思春期以降の知能発達をサポートする方法:
- 個人の興味に基づいた学習機会の提供
- メンターや役割モデルとの関わり
- 複雑な問題解決の経験
- 異なる視点からの思考の奨励
- 独立した判断力の育成
この時期は専門性を深める時期でもあります。
得意分野での深い学びを支援しましょう。
同時に、多様な分野への関心も大切です。
異なる知識の統合が創造性を高めます。
思春期以降の知能発達は、主体性を尊重しながら、適切な挑戦と支援のバランスを取ることで、若者が自分の知的可能性を最大限に発揮できるよう手助けすることが鍵となります。
「遺伝決定論」の誤りと環境による可能性
「遺伝決定論」という考え方は科学的に誤りです。
遺伝率が高いからといって運命が決まるわけではありません。
遺伝は「可能性の範囲」を示すものです。
その範囲内でどう発達するかは環境で変わります。
例えば、音楽的才能には遺伝的要素があります。
しかし、訓練なしに一流の音楽家になることはできません。
逆に、遺伝的素質がなくても、適切な訓練で高いレベルに達することは可能です。
知能も同様です。
遺伝的基盤はありますが、変化の可能性もあります。
環境による可能性を示す重要な証拠:
- 採用試験の得点は適切な学習で向上する
- 貧困から抜け出した子どもの知能は向上する
- 認知トレーニングは特定のスキルを改善できる
- 教育機会の拡大は集団の知能を高める
- 異なる文化背景への移住は知能に影響する
「範囲-反応性理論」という考え方が重要です。
遺伝は「反応できる範囲」を設定します。
環境はその範囲内での「位置」を決めます。
環境が良ければ、潜在能力の上限に近づきます。
「遺伝決定論」ではなく「遺伝と環境の相互作用」という視点が重要であり、適切な環境と介入によって、遺伝的傾向にかかわらず知的発達を促進できる可能性があることを理解することが大切です。
最後に
知能の遺伝について理解することで、自分自身の可能性をより広げることができます。
ウィルソン効果が教えてくれるのは、知能の遺伝率は年齢とともに増加し、18〜20歳頃には約80%に達するという事実です。しかし、これは努力が無意味だという意味ではありません。
むしろ、自分の強みや特性を理解し、それに合った方法で学ぶことの大切さを示しています。
幼少期は環境の影響が特に大きいため、親や教育者は豊かな刺激を提供することが重要です。
思春期以降は、自分に合った環境を選び、興味に基づいて深く学ぶことで知的能力を伸ばせます。知能は「壊れやすいガラス」ではなく「回復力のあるシステム」なのです。
結局のところ、遺伝と環境は対立するものではなく、複雑に相互作用します。
自分の遺伝的傾向を知りながらも、環境や経験によって変えられる可能性を信じることが大切です。
自分に合った方法で学び続ければ、どの年齢でも知的成長は可能なのです。

ライター 兼 編集長:トキワエイスケ @etokiwa999
株式会社SUNBLAZE代表。子どもの頃、貧困・虐待家庭やいじめ、不登校、中退など社会問題当事者だったため、社会問題を10年間研究し自由国民社より「悪者図鑑」出版。その後も社会問題や悪者が生まれる決定要因(仕事・教育・健康・性格・遺伝・地域など)を在野で研究し、論文4本執筆(うち2本ジャーナル掲載)。社会問題の発生予測を目指している。凸凸凸凹(WAIS-Ⅳ)。